進行別 がん標準治療 徹底的な治療をする。これが精巣がんの治療方針
救済手術ができるのは大病院クラス
●残存腫瘍の摘出(救済外科療法)

腫瘍が消えれば、当然マーカー値も陰性化しますが、画像診断上、腫瘍が残存していてマーカーがマイナスを示すことがあります。この場合は、残存している腫瘍がすでに壊死したがん細胞の固まりである可能性があります。そこで、診断的な意味も兼ねて残存腫瘍の摘出手術が行われます。これを、救済外科療法と呼びます。
転移した部位によって、リンパ節切除が行われることもあれば、肺や肝臓などに残存した腫瘍を摘出することもあります。他のがんが肺に転移した場合、その個数が多いと手術の適応にはならないことが多いのですが、精巣がんの場合複数の転移巣があっても抗がん剤治療後手術で摘出すれば、治癒する可能性があるそうです。
それだけに、部位によってはかなり大がかりな手術になる上、泌尿器科の医師ではカバーしきれないこともあります。「後腹膜リンパ節切除だけならば泌尿器科のみでも手術できますが、胸の縦隔腫瘍をとったり、心臓や大動静脈の処置を必要とする、腸を切除する、肝臓を切除するとなると泌尿器科だけでは無理。他科の協力が不可欠です」と語っています。
抗がん剤治療の段階までは、ほぼ治療法が確立しているので経験のある泌尿器科ならどこでもできます。しかし、救済手術となると他科の協力も必要なので、大きな病院でないとできないことが多いのです。また、手術で摘出できない、例えば脳や骨の転移の場合は、放射線治療が行われることもあります。
進行がんでも5年生存率80%以上
こうして摘出した残存腫瘍は、病理検査でがんか否かを確認します。すでに壊死した組織であれば治療は終了です。経過を観察することになります。しかし、もしがんが残存していれば、再び抗がん剤による治療を2コース行うのが原則だそうです。
「手術の直前に行っていた化学療法を行うのが一般的ですが、それが効かなかったからがんが残ったのだという考えから、新薬を使うこともある」といいます。いずれにしても、徹底的に治療をするのが、精巣がんの治療方針です。
「化学療法でできるだけがんを叩いて、腫瘍マーカーを正常値に持っていく。それで残った腫瘍は摘出できるものは手術でとり、とれなけれ���放射線で治療する。残存がんがある場合は、また化学療法を行うというのが、基本的な考え方です」と垣本さんは語っています。導入化学療法が効かず、救済化学療法を行っても腫瘍が残存し、手術や放射線治療を行ったという人、つまり治療に手こずる精巣がんや再発したがんでも、約50パーセントの人が治癒しているのです。
2期以降の進行がんでも、全体で5年生存率が8割以上に上っているのも、これだけ徹底した治療を行うからなのです。「非常に進行した状態で発見されても徹底的に治療をしてそれで助かる人もいる。それが、精巣がんの特殊なところです」と垣本さんは語っています。
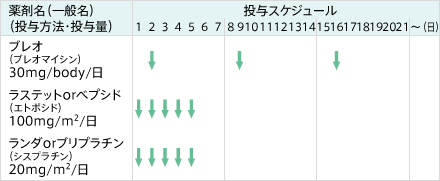
〈投薬期間〉3~4週を1コースとして3~4コース
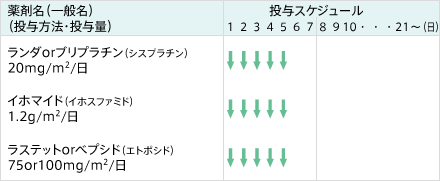
〈投薬期間〉3週を1コースとして行い腫瘍マーカーの陰性化を目指す
新しい抗がん剤治療
化学療法は、導入化学療法(ファーストライン)はほぼ確立されています。救済療法、つまりBEP療法で十分な効果が得られないときにどうするかが、まだ模索されている段階だそうです。今はVIP療法とVeIP療法に関しては、科学的に効果が証明されているので、それらがセカンドラインの標準治療になっています。
大量化学療法、つまり大量の抗がん剤を投与し、末梢血幹細胞移植を行う方法が有効という報告もありますが、これはまだ科学的な検証が行われているところです。
「もし、いい結果が出れば、あまり予後のよくなさそうな人のセカンドラインに組み込まれてくる可能性もあります」と垣本さん。セカンドラインの化学療法としてVIP単独療法とVIP療法+大量化学療法を比較する試験が海外で進んでいるそうです。
また、タキソールやジェムザール、カンプト(一般名塩酸イリノテカン)など新規抗がん剤を組み合わせた化学療法の効果も検討されています。


