進行別 がん標準治療 がんの「種類」を見定めることが治療選択のポイント
高危険度乳頭がんの治療
同じ乳頭がんでも肺などに遠隔転移を起こした怖いがんの場合、日本でも治療はアメリカと同様です。つまり、放射性ヨードによる治療に備えて甲状腺の全摘手術を行います。
とはいえ、必ずしも、放射性ヨードが転移巣に取り込まれるとは限らず、また取り込まれた場合でも、がんが消えるとは限りません。杉谷さんによると「転移したがんに放射性ヨードが取り込まれる人は、50~70パーセントくらい。がんが完全に消えるのは1割以下」だそうです。「若い人の分化の良いがん(元の甲状腺の細胞に近い顔つきをしたタチのいいがん)で、大きさが1センチ以下くらいの小さな肺転移なら消える可能性がある」といいます。つまり、放射性ヨードによる治療が効果をあげるのは、肺転移といってもおとなしいタイプのがんなのです。「肺に小さな転移が点々とあるといった状態なら、そう悪さはしません。しかし、胸水が溜まってくると、がんが胸膜まで広がっているということなので、かなり厳しくなります。骨転移の場合も治療は難しいです」と杉谷さん。
骨に転移を起こした場合は、それが痛みを起こしたり、神経を圧迫してマヒを起こすこともあるため、「できれば手術を勧める」そうです。あちこちに転移がある場合は、体外から放射線を照射する治療が行われます。ビスフォスフォネートという骨を溶けにくくする薬で骨転移の進行を抑える治療を行うこともあります。しかし、本当に怖いがんの場合の治療法には決定的な方法がないのが現状です。
一方、周囲の臓器にがんが浸潤している高危険度がんの場合には、拡大手術によってがんを摘出することもあります。声帯を動かす反回神経や気管、食道を甲状腺と一緒に切除した後で、機能を再建する手術が日本では進歩しているといいます。また、必要に応じて行う広範なリンパ節郭清の技術にも高いものがあります。
癌研病院では、こうした方針の下に治療を行った結果、高危険度乳頭がんの場合の10年生存率は69パーセントと出ています。しかし、甲状腺の周りへの浸潤や大きなリンパ節転移があるために高危険度乳頭がんに分類された人の場合、手術後3年間再発がなければ10年生存率は96パーセントに上っています。「つまり、遠隔転移がない場合、頸部のがんをきちんと治療できれば、治る確率はかなり高いのです」。ただし、術後比較的短期���で頸部に再発を繰り返したり、遠隔転移が出てくる場合の治療は困難で、やがてがんをコントロールできなくなることが多いようです。
低危険度乳頭がんの再発治療
ふつう、がんは再発が怖いとされます。しかし、低危険度乳頭がんの場合はやや特殊です。
再発は、頸のリンパ節に出ることが多いのですが、癌研病院では「リンパ節が1センチを越えて大きくなるとか、重要な臓器に近くて悪影響を及ぼす可能性が高いといった場合以外は、しばらく様子をみる」そうです。リンパ節に転移があってもこのがんの場合、大きくならずにずっとそのままということも多いのだそうです。
一方、肺など遠隔部に再発する例は極めて少数ですが、この場合は残した甲状腺を切除して、放射性ヨードで治療を行います。「状況によっては、様子を見ることもあります」(杉谷さん)。
甲状腺がんの種類別治療法/濾胞がん
遠隔転移の有無が大きな分岐
周囲の臓器に食い込んだりリンパ節に転移することは少なく、遠隔臓器に血行性転移さえなければ、大部分が手術で治るがんです。
ただ、濾胞がんは、細胞だけみても良性腫瘍(濾胞腺腫)と区別が難しく、実際にシコリを摘出して顕微鏡で検査しないと判断がつかないことがあるのです。つまり、手術前に診断をすることが難しく、「とってみないとわからない」のが問題点です。といっても、良性のシコリを濾胞がんかもしれないといって片端から摘出するのは問題なので、これを見極める方法がいろいろと工夫されています。細胞診や血液中のサイログロブリンの値を参考にしたり、通常の超音波検査に加えて*ドプラーエコーで血流をみることもあります。しかし、「絶対的な術前診断法はない」のが実情だそうです。
「濾胞がんは遠隔転移を起こすか起こさないかで、治療成績が大きく分かれる」と杉谷さんは語っています。濾胞がんの場合、遠隔転移を起こさずに甲状腺で大きくなる分には、生命にかかわることはあまりないのです。しかし、遠隔転移を起こすと、このがんも怖いがんということになります。実際には、骨や肺などの転移が最初に発見され、その火元を探したら甲状腺だった、という経過で濾胞がんが見つかることが多いそうです。
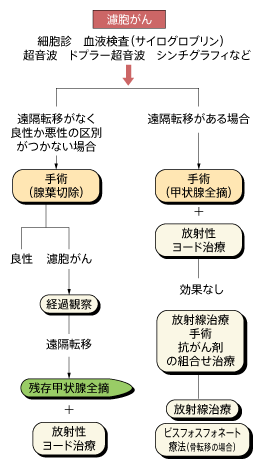
遠隔転移に対しては、やはり甲状腺の全摘を行って放射性ヨードによる治療を行います。「方法も効果も、乳頭がんの遠隔転移と違いはない」そうです。ただし、濾胞がんの遠隔転移は骨に起こることが多い分、厄介だといいます。遠隔転移をしても進行は遅いことが多いのですが、完全に治すことは難しく、一生付き合っていかなければならない場合がほとんどだそうです。
一方、良性腫瘍だと思って摘出して検査をしたら濾胞がんだったという場合もあります。この場合は、「まだ治療法に論議のあるところ」と杉谷さん。濾胞がんか腺腫か区別がつかない場合、癌研病院では甲状腺の片側を切除する腺葉手術を行います。それで、術後の病理検査で濾胞がんと判明した場合にも、追加手術はせずに経過を観察します。腺腫と区別が難しいような濾胞がんは、遠隔転移を起こすことはめったにないからです。万が一遠隔転移が出てくれば、その時点で残った甲状腺を切除して、放射性ヨードによる内照射が行われます。一方、欧米では濾胞がんと判明した時点で全摘、放射性ヨードによる治療が行われることが多いそうです。また、手術時の腫瘍の肉眼的所見などから遠隔転移を起こしやすい濾胞がんと判断された場合は、その時点で転移がわからなくても同様の治療を行うことがあります。
*ドプラーエコー=超音波のドプラー効果を利用して、がん内部の微細な血流の様子などを見て早期発見に役立てる


