渡辺亨チームが医療サポートする:原発不明がん編
渡辺亨チームが医療サポートする:原発不明がん編-3
安藤正志さんのお話
*1 TJ療法
原発不明がんの治療法はまだ確立したものがありません。原発がんが見つからなくても、「ここが原発ではないか」と考えられる場合は、そのがんに対する標準的な抗がん剤治療を行うべきです。しかし、原発がどこにあるか見当がつかない場合、通常はタキソールやタキソテール(一般名ドセタキセル)などタキサン系と呼ばれる抗がん剤と、カルボプラチンやブリプラチン(一般名シスプラチン)などプラチナ(白金)系と呼ばれる抗がん剤を併用する治療が行われます。
タキソールとパラプラチンを併用する治療をTJ療法といいます。この療法は、原発不明がんのほか進行肺がんや卵巣がんなどでも採用されている治療法です。
TJ療法では1回の点滴時間が約3時間で、3~4週間ごとに点滴を行い、これを6サイクル繰り返すことが基本です。
| 投与量 | 投薬スケジュール | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| タキソール | 60mg/㎡ | - | 1週 (休薬期間) | |||||
| パラプラチン | AUC:1.7 | - | ||||||
| デカドロン | 20mg | - | ||||||
| ザンタック | 50mg | - | ||||||
| ベナ | 50mg | - | ||||||
*2 原発不明がんに対する臨床試験
原発不明がんの治療として臨床試験が行われている治療法は、ジェムザール(一般名ゲムシタビン)+ナベルビン(一般名ビノレルビン)、ジェムザール+パラプラチン、そのほか分子標的薬と呼ばれる薬剤を用いた治療法などが実施されています。治療成績はいずれもTJ療法とだいたい同じくらいと考えられています。
*3 外来抗がん剤治療
これまで日本の多くの医療施設では、抗がん剤治療は入院した形で行われてきました。しかし、最近は、副作用が少なくて有効な薬剤が多く登場したことから、外来でも治療が行えるような体制を整える施設が増えています。患者さんにとって通院しながら治療を受けることができれば、通常の生活を維持することができるというメリットがあり、歓迎されています。
一方、入院治療のように医療者の指示や監視が行き届かないので、患者さん本人が治療のことを十分に理解し、自分の状態に注意を払う必要があります。
*4 TJ療法の副作用
プラチナ系の��がん剤は嘔気・嘔吐や食欲不振などの副作用が半数近くに現れ、全身倦怠感や脱毛も2割近くに見られます。白血球などの血球が少なくなる汎血球減少が起こり、また、血小板を減少させる場合があります。アレルギー反応として起こるアナフィラキシー様症状など命に関わるような副作用もごくまれに見られますが、通常はほとんど心配はありません。
タキサン系の抗がん剤は白血球を減少させることがあり、これにより感染のリスクが増加します。さらにアレルギー反応が起きる場合もあり、脱毛もほぼ100パーセント起こります。さらに6~7割の患者さんには何らかのしびれが起こり、1~2割は足にジンジンしたしびれを感じます。3分の1の患者さんには筋肉痛が起こり、2~3日続くのが普通です。
しかし、いずれにしてもTJ療法の副作用は、一般にそう深刻なものはないので、外来治療も可能です。
| 副作用 | TJ療法 | DJ療法 |
|---|---|---|
| グレード4の好中球減少 | 56% | 80% |
| 重篤な好中球減少 | 3% | 9% |
| 遷延的な好中球減少 | 1% | 12% |
| グレード2,3の末梢神経障害 | 28% | 10% |
| 治療関連死 | 1例 | 2例 |
*5 TJ療法の効果
TJ療法の原発不明がんに対する奏効率(腫瘍を小さくできる割合)は20パーセント前後、腫瘍制御率(腫瘍を大きくしない割合)は50パーセント強、1年生存率が約30パーセントといわれています(ASCO=米国臨床腫瘍学会2005)。
しかし、治療をしなかった場合に比べてこの治療に、延命効果があるかどうかはわかっていません。とくに肝臓への転移が認められる症例では予後が悪く、治療を行っても生存期間は一般に1年未満です。また、1回目の治療で腫瘍を小さくする効果が現れない場合は、2回目以降の治療を行っても、ほとんど腫瘍を小さくすることは期待できません。
*6 緩和的抗がん剤療法
症状を和らげ、生活の質を高めることを目的とした抗がん剤療法のことをいいます。そもそも原発不明がんは治癒を期待できないがんであり、また治療開始時点でかなり症状が出ている患者さんが多いので、これに対する治療はすべて緩和的抗がん剤療法ということができます。
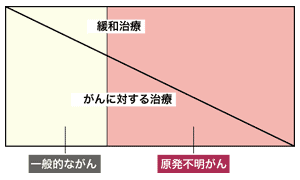
原発不明がんの抗がん剤治療は緩和治療の意味が大きい
*7 完全寛解
腫瘍が小さくなって、画像から消えることを完全寛解といいます。それでも目に見えないがんが散らばっている可能性も考えられる状態です。
*8 抗がん剤耐性
がんが抗がん剤に反応しないことを抗がん剤耐性といいます。原発不明がんでは、最初から抗がん剤がまったく歯が立たない例もあるし、最初は少しがんを小さくすることができても、治療中にがんが再び大きくなるという例もあります。こうした例では、別の抗がん剤に代えてもあまり効果がないのが一般的です。
一方、がんが最後の治療を終えるまで小さくなり続ける場合もあります。こうした例でも半年とか1年後くらいに、抗がん剤耐性が出てくる場合が少なくありません。ただし、このように反応がいい例では、違う抗がん剤を使った場合にもいい反応を示すことがよくあります。
*9 がん難民
医療者から見放されてしまったがんの患者さんをがん難民と呼びます。がんの医療では5年生存率などの治療成績を競うことが多いため、「治りにくい症例は他の病院へ」とか「他の診療科へ」というふうに、患者さんを押し付けるといったことがしばしば見られるのです。原発不明がんは、「治療法のわからないがん」「治らないがん」と考えられがちなので、患者さんはがん難民にされやすいところがあります。
国立がん研究センター中央病院には、毎週2名くらいの割で、他の医療施設から「原発不明がん」として患者さんが送られてきます。未治療の患者さん、すでにいろいろな治療を受けておられる患者さん、また抗がん剤への抵抗性が現れた患者さんなどケースはいろいろです。前の担当医が自信をもって「これは原発不明がんというものです」ということを患者さんに告げることができていないケースもよくあり、患者さんも途方に暮れていることが珍しくありません。「原発が見つからないがん」ということが納得できず、最後まで「自分のがん治療はこれでよかったのか」と悩みながら亡くなっていく患者もしばしばおられます。
検査をしても最後まで原発巣のみつからない「原発不明がん」というものがあることをぜひ知ってほしいと思います。そして、原発不明がんにも治療の手立てがあることをご理解ください。とくにサブタイプの原発不明がんなどは、的確な治療を受けていただくことにより、大きな延命効果を挙げられる場合もあるので、これを見極めることが重要です。


