進行別 がん標準治療 基本は子宮を摘出する手術。ハイリスク群には加えて補助療法を
分化度が低い場合などに郭清を行う
それだけ手術による侵襲が大きくなるので、腸閉塞や感染などの危険も増します。しかも、体がんの患者は閉経後の人が多いので、「高齢で肥満者が多く、糖尿病や高血圧などの合併症を抱えているケースも多い」といいます。手術によるリスクが大きく、深部静脈血栓症のハイリスク群でもあるのです。深部静脈血栓症は、いわゆるエコノミー症候群です。下肢の深部静脈などに血栓ができ、これが肺などに飛んで詰まり、命に関わることもある病気です。婦人科系の手術で起こることも多く、それを防ぐために弾性ストッキングや血行を促進する器具を用意し、血液凝固を防ぐ薬を投与するなどさまざまな準備をしなければなりません。
「加えて、卵巣がんほど傍大動脈リンパ節の転移は多くないので、実際には傍大動脈のリンパ節まではとらない医師も少なくないのです」と杉山さんは、現状を語っています。
杉山さん自身も、医学的な見地から「全ての患者さんに実施した場合には、過剰な治療になる可能性もあるのではないか」と考えています。といっても、万が一傍大動脈リンパ節に転移があれば、それを見逃す危険も出てくるわけです。
そこで、組織診でグレード3など分化度が低い場合、あるいは術前のMRIで筋層への食い込み方が深い場合に、傍大動脈リンパ節の郭清を行ってはどうかと杉山さんは考えています。
加えて、杉山さんは手術中に郭清した骨盤内のリンパ節をただちに病理で診断(術中迅速病理診断)してもらい、転移があれば傍大動脈リンパ節郭清を行うという方針をとっています。
「子宮体がんの場合、骨盤内のリンパ節に転移がなく、ポンと離れた傍大動脈リンパ節に飛んでいるということは、卵巣がんに比べて非常に少ない」のだそうです。ただし、こうした迅速な術中の病理診断は、どの病院でもできるわけではありません。そこで、分化度や筋層への食い込みの深さで判断してはどうかというのです。こうした点から、少しずつ体がんでも進行度による手術の個別化が進められようとしています。
妊娠希望と温存療法
子宮体がんは閉経後の女性に多いので、妊娠可能な年齢で発症することはむしろ少ないと言えます。しかし、40歳以下で強く出産を希望する場合、条件にあえば例外的に子宮を摘出せず、保存的な治療を行うことも可能です。
その条件とは、0期すなわち子宮内膜異型増殖症か高分化型の類内膜腺がんで1a期であること。つまり、極めて早期���段階であることが必要です。さらに、女性ホルモンに対する受容体が、がん細胞にあることが条件になります。ホルモン受容体があるということは、ホルモン依存性のがんで、ホルモン療法の効果が期待できることを意味するからです。杉山さんによると「体がんの場合、受容体がある人は3割ほど(高分化がんに限ると7~8割)」だといいます。この条件だけでも、かなり厳しい選別になるわけです。
こうした条件に当てはまる場合は、エストロゲンの働きに拮抗する黄体ホルモン療法を行って、「厳重に経過を観察することになります」と杉山さん。「厳重に」というのは、必ずしもホルモン療法が効果を現すとは限らず、リスクも大きいからです。ホルモン療法を行いながら、定期的に超音波検査や細胞診・組織診を行い、うまく異常が消えた場合では排卵誘発剤などを使ってできるだけ早く、妊娠をはかるようにします。
「自分ががんであることの告知を受け入れ、また、ホルモン治療の限界と副作用(体重増加、血栓症など)を理解した限られた人にのみ行われる治療法で、ただ子宮を残したいという理由では実施できません」と杉山さんは語っています。
術後補助療法
補助療法は抗がん剤治療が標準
手術後、ハイリスク群と判定された場合には、補助療法が行われます。杉山さんによると、実際には手術を受けた人の半数以上が、ハイリスク群の範囲に入るそうです。日本の場合、術後補助療法は抗がん剤による化学療法が標準です。
杉山さんによると、現在は「ブリプラチン(もしくはランダ、一般名シスプラチン)、アドリアシン(一般名アドリアマイシン)、タキソール(一般名パクリタキセル)のいずれかが使われる」そうです。これらの抗がん剤は、欧米でその有効性が確認されています。「日本でもやっと認可されたところで、以前はこの中で子宮体がん治療に認可された抗がん剤はなかったのです。最近はタキソールの効果が高いことがわかって、使われることが多くなってきましたが、まだ認可は下りていない状態」だといいます。
現状では、アドリアシンとブリプラチン(もしくはランダ)を併用するAP療法が中心です。アメリカでのデータによると、AP療法の奏効率(がんが半分以下に小さくなる率)は、約40パーセントと出ているそうです。ただし、アメリカで抗がん剤が使われるのは進行・再発がんの場合なので、この数字も進行・再発がんを対象としたものです。
注目されるタキソールの効果
化学療法は、「卵巣がんに準じて3~4週間の間隔をあけて、5~6コース行う」のが、標準的です。治療期間は、計5カ月ほどになります。入院して行う病院もあれば、外来の点滴センターなどで実施している病院もあるそうです。日本での効果は「5年生存率でみるしかない状態」と杉山さん。とすると、1期で2割、2期で3割が術後補助化学療法を行っても再発していることになります。
一方、現在はタキソールの効果が注目されています。すでにいくつかの臨床試験が進行していますが、最近タキソールとブリプラチン(もしくはランダ)の併用で奏効率67パーセント、タキソールとパラプラチン(一般名カルボプラチン)の併用でも、78パーセントという非常に良好な数字が報告されています。いずれも第2相臨床試験(少数で効果をみる試験)の成績ですが、今後期待できそうです。
ただ、ブリプラチン(もしくはランダ)は腎臓に対する毒性が強いので、日本ではパラプラチンとタキソールの併用でも、臨床試験が始まっています。杉山さんらもこれにアドリアシンを加えた3剤併用での第1相臨床試験(安全な用量を決定する試験)を行っています。結果が出れば、初めての日本オリジナルの化学療法のエビデンスになると期待されている試験です。化学療法はあらたな日本人のための標準治療ができる可能性も高いといえます。
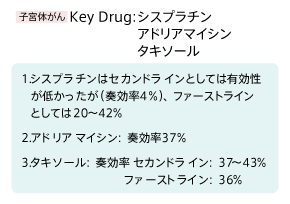
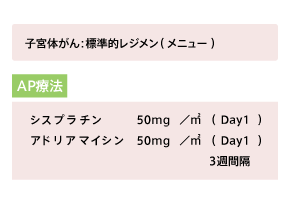
タモキシフェンと子宮体がん
乳がんの手術後、再発予防のためにタモキシフェンを飲んでいる人は、少なくないはずです。杉山さんによると、こういう人は「子宮体がんの検診が必要」なのだそうです。
タモキシフェンは、抗エストロゲン薬です。乳がんは、エストロゲンに依存し増殖するがんなので、エストロゲンの作用を封じ込めることが、乳がんの再発予防になるのです。ところが、同じタモキシフェンが、子宮内膜に対しては「エストロゲン作用を持ち、内膜に増殖性の変化を起こす」というのです。
つまり、体がんを促進する方向に働いてしまうのです。したがって、タモキシフェンを服用している人は、定期的に体がんの検査を受けることを忘れないでください。
再発したがん
子宮体がんの再発に関しては、日米を問わず治療は化学療法になります。「術後補助療法とは違う抗がん剤を使うのが基本で、AP療法を行っていればタキソールなどを選択することになります」と杉山さん。ただし、標準治療といえるほど確定した抗がん剤はまだないそうです。
同じカテゴリーの最新記事
- ICIとPARP阻害薬の併用療法が日本で初承認 進行・再発子宮体がんの新たな治療が今後も次々と!
- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在
- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~
- 症例数はまだ少ないが、高齢者や併存症を持つ患者にも対応可能 子宮体がんにおける重粒子線療法の今
- 子宮体がんの最新治療と今後の可能性 免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が本格的にスタート!
- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に
- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが
- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状
- 子宮体がんの術後補助化学療法で再発を防ぐ


