君を夏の日にたとえようか 第1回
夢はあえなく打ち砕かれた
私が初めて恭子のことを目にしたのは、四国の高校でのことだった。
利発で成績優秀、しかも活発な少女だった。決して目立ち過ぎる存在ではないが、恭子の周りには必ず友人がいて、笑顔が溢れていた。恭子の笑顔は、少年のようなカラっとした素直な笑顔だった。運動が得意で、高校の体育祭では応援団に所属していた記憶がある。ちょっと斜に構えた悪ぶった連中や、運動の得意な元気な連中が応援を担当していたように思う。
私のような美術方面を好む生徒の多くは、巨大な看板描きを担当することが多かった。その高校には普通科と商業科があって、学年ごとに、つまり6つのブロックが、運動会の競技の得点や応援や看板の出来ばえを競い合った。
2階建ての家くらいの高さのある足場を組んで、その背部に趣向を凝らしたブロックごとの看板を立てた。大きなベニア板2、30枚分くらいあったろうか、巨大な看板だった。学校の中庭にベニア板に紙を張ったものを広げ、構図やら色の具合やらを、美術の得意だった私が、校舎の5階の窓から首を突き出して大声で指示した記憶がある。勉強した記憶しかない無味乾燥な高校時代の唯一の若者らしい記憶が、私にとっては3回の運動会での看板描きだった。1年生のときからその看板の評価は高かった。
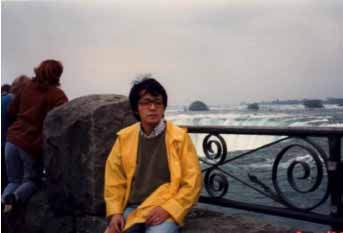

恭子は合唱部に所属していて、音楽にも早くから魅力を感じていたようだ。ビートルズのロックから、フォーク・クルセダーズや、日本の草分けのような古いフォークソングもよく聴いていたらしい。恭子に導かれて、ずっと後に、私もその魅力に気がつくようになるが、遅きに失していた。いや、遅くたって、恭子の音楽の世界観を一時でも共有できたことは喜ばしいことであった。高校のときから、恭子は人生の瑞々しさにすでに触れていたのだ。それに比べたら、私は高校時代まで死んでいたようなものだ。少なくとも、私の本当の青春や人生は、まだ始まっていなかった。
恭子の大学生活は、論理的な思考ができて、運動神経にも、素直な性格にも、人好きのする容姿にも恵まれていたから、活発で喜びと希望に満ちていた。笑顔にも。常に友だちに囲まれて、淋しいなんて思ったこともなかったろう。私と恭子は偶然、同じ大学に進学していたのだった。と、私は信じて疑わなかった、ずっと遠い先の日まで……。
恭子は教育学部。私は歯学部に。私自身が、自分がなぜこの学部にいるのかを知らなかった。まあ、私のことは兎も角、大学の合唱団で青春を謳歌し、飛び回って交友を深めながら教職の勉強をした恭子は、難なく大学を卒業して、教員採用試験にも合格し、4月から赴任する小学校まで決まっていたのだ。
その夢は――、あえなく打ち砕かれた。卒業前にまあ健康診断でもしておこうかと考えた恭子は、昔の病気のことなど一慮だにしていなかった。恭子の両親さえ、すっかり忘れていたのだから。
先天性股関節脱臼とその昔呼ばれていた変形性股関節症、股関節の関節窩が極端に浅いために、長時間の立位やそこそこの運動をすると関節が痛んで、人工関節置換術さえ必要になるかも知れない。医者は残酷にも「立ち仕事が多く子どもたちと飛び跳ねたりしなくてはならない教職は無理だ」と、諦めるようにと告げた。
〝紫の君〟と呼ばれていた
その当時の自分の辛さや絶望について、恭子は多くを語らなかった。いや、単に私に聞いてあげられるだけの度量がなかっただけなのかも知れないが……。恭子は教職を諦め、実家に帰った。しかし、恭子本来の優しさから、両親にさえ己が失望を露わにすることはなかったようだ。ただ、両親が夜更けまでひそひそと悩ましい思いや恭子の行く末を案ずる堂々巡りの話し合いをしていたと、恭子は寂しそうに私に語ってくれたことがあった。いずれにしても、子も親も相手を慮って表面を取り繕うという優しさがあった恭子の実家では、物事は淡々と穏やかに過ぎて行ったようだ。
そうして、何年かの気持ちを落ち着かせるに足る期間を経て、恭子は私の勤務する大学病院の整形外科で、片方の股関節の関節窩を深くして安定させる手術を受ける決断をした。思えば、それが、私たちの運命の再会だったのだ。恭子にとって、それが幸せな再会であったという自信が私にはない。が、少なくとも私はその運命の再会によって恭子という伴侶を得たことで、思ったことを何でもずけずけと論じたり実行したりすることに臆することのない横柄な私が、人並みな世間とのつき合いのできる、まっとうな人生を送ることができるようになったのだ。
その病院の同室者のあいだで、私が〝紫の君〟と呼ばれていたことがあった。
愛というものの発端が、病気と闘っている者へのいたわりであってはならないだろうか。そんなことはないだろう。愛の始まりが、この人を守りたいという気持ちであってなにが悪かろう。
恭子は一生のうちに、2回の腰椎麻酔による手術と、全身麻酔による3回の手術を受けた。最初の手術が、股関節の関節窩(かんせつか)形成手術だった。その当時は、腰椎麻酔による手術だった。
その最初の手術後の恭子の病室を足繁く訪ねた私は、近所の花屋で偶然に紫色の花束を選び取ることが多かった。私が好きな華美でない草のような花であったのと、手頃な価格で入手できたからだ。紫の花が多かったのは、単なる私の好みに過ぎなかった。そうして、私は、恭子の同室のおばさん連中から〝紫の君〟と呼ばれるようになった。
骨転移が決定的に
9月7日のNaF-PET検査によって、骨転移は決定的となり、しかも、転移の疑わしい部位は、何カ所もあった。同じ日の造影MRI検査で、脳転移は否定された。転移部位が骨にのみ限局していたことがどんなに幸運なことであったか、不幸中の幸いと言わざるを得なかったかを、そのときの私と恭子には知る由もなかった。
谷本先生は、ご自身の叔母さんの乳がんの経過にも触れながら、乳がんが抗がん薬の感受性の高いがんであること、新しい抗がん薬が年々開発されていること、案外長生きできることを、希望を持つべきことを噛み砕いて説明していただいた。我々夫婦には力強い励ましのことばであったが、その本当の意味を理解するための知識を、そのときは持っていなかった。(つづく)


