医師としてより人間同士として 患者さんの最期の日々に寄り添う
お互いにがん患者、垣根を感じなくなっていく
自らのがん体験を通して、細井さんは患者さんがもつ「ひとりの人間として見てほしい」という思いを実感した。
「がんを患ったときのように、自分という存在そのものに影響が及ぶときは、とくにそうでしょう。自分の人生とか、いのちとか、自分の存在そのものを見てほしい。患者さんの存在そのものを見るには、私が医者という立場で何かできることをしようと思うその前に、まず話を聴くことなのです」
外科医時代は手術で、ホスピス医になってからはモルヒネを使った除痛で患者さんを楽にしてあげることが使命だと思っていたと振り返る細井さん。自分が腎がん患者になってからは、「患者さんの苦しみを分かち合おうと思うけど治してあげようとは思っていない」という。
「患者さんが求めているのは、誰かがそばにいてくれること。だから、隣人として傍らに行き、話を聴く。お互いに弱さを持つ人間としてです。ただ、私は医者を兼ねてやっているので麻薬が扱えますし、ちょっと使ってみましょうかという感じです」
「お互い様」という感覚で患者さんと接するようになると、患者さんとのコミュニケーションが楽になり、患者さんとの間の垣根を感じることが少なくなっていった。
「明日をも知れないお互い様同士が、今ここで時間を共有している。患者さんにとってそれこそが大切なのではないか、変わらず見ていてくれていると患者さんに感じてもらえることが、ケアではないかと思うようになりました」
裾野が広がる緩和ケア 質の確保はできているか
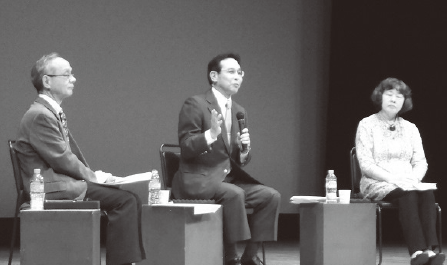
12年の新たながん対策推進基本計画によって、患者さんの療養生活の質の向上にも焦点があてられるようになり、緩和ケアの推進強化が図られている今日の状況を、細井さんは「それは、あくまで医療の問題」と強調する。
「死ぬというのは医療の問題ではなく、人生の問題です。がんだから死ぬのではなく、人間だから死ぬのです。医療システムとしてのきちんとしたネットワークでなくてもいいから、患者さんの生活基盤のある地域で、誰かがそばにいて緩やかにつながり合う関係があれば、よい最期が迎えられるのではないかと思います」
また、緩和ケアの裾野は広がってきてはいるものの、その質が確保されているのかは疑問だと指摘する。
「緩和ケアといいながら、症状コントロールが中心の『緩和キュア(=治療)』になっていないでしょうか。ケアというのは、気持ちを通わせることだと思うのですが、医者が患者を診る関係ではキュアに傾いてしまい、気持ちが通うところまで辿り着きません。医者と患者という立場を超え、同じ死にゆく人間同士として相手に接することができて初めてケアになるのです。そういう関わりを見出していけるのかというと、非常に難しいのです」
受け継がれていく「いのち」
「ホスピスは死んで終わりというイメージを持たれていますが、決してそうではありません。たしかに漢字で書く『生命』は、生命体としての死がその終わりだと思いますが、平仮名で書く『いのち』は終わることなく受け継がれていくものだと伝えたかったのです」
ホスピスをテーマにしたドキュメンタリー映画『いのちがいちばん輝く日~あるホスピス病棟の40日~』に撮影協力した理由を、細井さんはそう説明する。

映画では、最期のときを迎えた患者さんが、死をまっとうする姿が描かれている。肉体的な生命の死は、ホスピスにあるかもしれない。しかし、その人の死によって残された人たちは生かされていく。心に刻まれ、受け継がれていく「いのち」がある。だから、ホスピスに死の悲しみではなく、新たに生まれる喜びがあることを教えてくれる。
「人間同士として出会い、お互いに存在そのものとして関わると、その人が亡くなった後も消えてなくなるのではなく、私の中では生き続けています。あるいは私たちが生きていく力になります。私やホスピスのスタッフは、患者さんからエネルギーをもらって仕事の糧にしているところがあります」
希望館の玄関に立つと、次のような言葉が書かれたポスターが出迎えてくれる。
「ホスピスってどんなとこ ホスピスは『ここに来ればもう終わり』という場所ではなく、ここから始めようという場所です」
URL:http://www.inochi-hospice.com/
残された時間を自分らしく生きる4人の患者さんとご家族、献身的にケアを続ける医療スタッフたちの姿を追ったこの作品は、21都府県で劇場上映のほか自主上映会が開催されている
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


