末期の転移性大腸がんから生還を果たした弁護士の苦悶とは がんと真剣に向かい合う、そのプロセスこそが尊い
「5年生存率ゼロパーセント」という衝撃
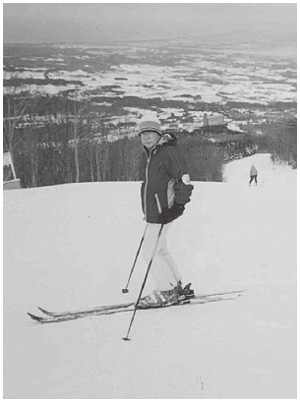
お腹にがんはなかった──小野さんはホッと安堵したものの、肝臓と脾臓にがんを抱えていることには変わりがない。腹膜にいつがんが再発するかもわからず、不安で鬱々とした日々が続いた。
内科医の方針で、抗がん剤の種類も替えることになり、9月上旬からイリノテカン(*)+マイトマイシン(*)による化学療法を開始。イリノテカンの副作用で猛烈な下痢や排便痛、嘔吐などに悩まされたが、顧問の仕事などは断るわけにはいかない。薄氷を踏む思いで、広島への出張などもこなさざるを得なかった。
秋も深まったころ、小野さんを、さらなる絶望の淵に突き落とすような出来事が起こる。それまで、腹膜播種のリスクについてはあまり理解していなかったが、ついに、その恐怖に直面する日がやってきたのだ。
ある日、中島みちさんの著書『奇跡のごとく』(文藝春秋)を読んでいると、スキルス胃がんから生還した20歳の女子学生の症例が紹介されていた。
「(腹腔内洗浄細胞診の結果が陽性であれば)肉眼的に腹膜播種がなくても腹膜播種性転移があるのと同じぐらいの予後(*)しか期待できない」「長期生存つまり五年生存の可能性は非常に低率で、限りなくゼロパーセントに近いということになる」
このくだりを読んで、小野さんは愕然とした。目に見える腹膜播種がなくとも長期生存が難しいのなら、自分はどうなのか。最初の手術の時点で腹膜播種が4カ所にあったということは、5年生存率は、ほぼゼロということになる。腹膜播種の恐ろしさを、初めて思い知った。自分は考えていた以上に、死の淵に 立たされていたのだ──自分が置かれている状況の苛酷さに、ただ茫然とするほかなかった。
「『5年生存率ゼロパーセント』という記述を見たときは、『もうだめだ。先生、うまくだましたな』と思いました。でも、知らなくてよかったんです。もし知らされていたら、生きる気力をなくしてしまったでしょうから」
*イリノテカン= 一般名
*マイトマイシン= 一般名
*予後= 今後の症状の医学的な見通し
万感の思いで迎えた長女の結婚式
この日を境に、小野さんは、それまでとはまったく異質な「恐怖の日々」を送ることとなる。
以前から家族に勧められていた、にんじんジュースやゲルマニウム、ハナビラタケなどの健康食品にも関心を示すようになったが、結局ネット検索で見つけた鮫のエキスを飲用し始めた。藁にもすがる思い、とはまさにこのことだった。
���立がん研究センターで3度目の手術を受けたのは、あくる年の03年1月8日のことである。肝臓の一部を切除し、脾臓を摘出したが、イソジンと抗がん剤が効いたのか、病理検査ではがん細胞は確認されなかった。また、腹膜播種の存在も認められなかった。
3月からイリノテカン投与を再開することが決まったが、体内からがんが消えたという事実は、小野さんを深く安堵させた。羽田空港のレストランで次女と一緒にワインを傾けながら、小野さんは久しぶりに、生きることへの希望をかみしめていた。
その後は腸閉塞の症状が悪化し、7月に腸閉塞の手術を実施。過度のストレスからくる過喚気症候群などに悩まされながらも、病状は徐々に快方に向かった。
そして11月1日。小野さんは、長女・志保さんの結婚式に出席するため東京に向かった。生きて、この日を迎えることができようとは――新婦の父として式に出席できたことを、小野さんは神に感謝したい思いだった。

患者から聞かれない限り、余命は告知すべきではない
02年にがんが発覚してから、小野さんは今年で丸9年を迎えた。現在は半年に1度、定期検査で国立がん研究センターに通院している。
それにしても、大腸がんで腹膜4カ所に17個もの播種があり、一時は「5年生存率ゼロパーセント」とまでいわれた小野さんが、生還できた理由とは何だったのか。その理由として、小野さんは次の4つを挙げる。
(1)最初の手術で、肉眼で見えるがんをすべて取り切ったこと。さらに、肉眼で見えなくても、がんが存在する可能性があると思われる部位を切除したこと
(2)イソジンによる消毒で、目に見えないがんを死滅させたこと
(3)適切な抗がん剤の投与
(4)がんの性質
ふつう、腹膜播種は深く根を張っていることが多いが、小野さんのがんはフニャフニャとしたキノコ状の珍しいがんであった。赤須医師はそこに一縷の希望を見いだし、17個もの腹膜播種をすべて切除していった。この、がんの特殊な性質もまた生還の一因となったのではないか、と小野さんは語る。
さらに、がんについての理解不足や、病状を一部しか知らされなかったことも、結果としてプラスに働いた。「5年生存率ゼロパーセント、余命半年」という宣告を受けていたら、自分の心は完全に破綻していただろう、と小野さんは振り返る。
「患者から聞かれない限り、医師は余命を告知すべきではない。家族から患者の性格についてよく聞いた上で、どのような告知をするか、熟慮したほうがいい。仕事の関係などで、患者本人が知る必要がある場合は別として、心の弱い人や繊細な人に、何もかも話すべきではないと思います」
小野さんは著書のなかで、「がんと真剣に向かい合うプロセスこそが尊い」と書いている。
「人生、そう遠くない先に終わるかもしれない──そう思えば、おのずと家族との会話も多くなり、自分の気持ちも話すようになる。新婚時代を過ぎると、夫婦の会話もだんだん少なくなりますよね。でも、なんとか助かりたいと一生懸命にがんばっていると、その思いが家族にも伝わり、家族とのコミュニケーションが濃密になる。家族一丸となって病気と闘い、バラバラになっていた家族が絆を取り戻すこともある。病気で亡くなったとしても、そのプロセスこそが尊いのではないでしょうか」
「今日やるべきことは今日やろう」
がんとの闘病が一段落した今、小野さんは「老い」との闘いに直面している。
「老いが突然やってきた、という感じです。がんとの闘いに明け暮れて、自分が老いていくという実感がなかった。肉体の衰えはがんのせいだと思っていたけれど、実は老化のせいだった。ある日突然、そのことに気がついて、愕然としたんです」
病気との闘いを克服したと思ったら、死は目前に迫っていた。その実感は、小野さんの人生観にも影響を与えたようだ。
「60代後半に入ってから、人生には一定の賞味期限がある、と実感するようになりました。迫りくる期限への不安を、痛切に感じるようになった。それだけに、今やっておきたいことは何かということを、よく考えるようになりましたね」
古稀を迎えた今、小野さんは、著書の続編執筆を計画中だという。がんを克服した自分自身が、60代後半から70代にかけての人生をどう生きたのか。悲喜こもごもの心境を書き綴り、1冊にまとめたい、と抱負を語る。
「今日やるべきことは今日やろう、と思うようになりました。仕事に限らず、家族への孝行という意味でも。妻に対しても、なるべく『ありがとう』と言うようにしています。感謝を言葉で言うのは照れくさいけれど、その気持ちは表れているんじゃないでしょうかね」
そう言って、小野さんは、はにかむように微笑んだ。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


