妻の病を機に始めた闘病記探しが、自身の闘病を支えてくれた不思議 「闘病記」の魅力に取りつかれたネット古書店店主の大腸がん奮闘記 オンライン古書店「古書 パラメディカ」店主・星野史雄さん
妻の死から13年後、自分が大腸がんに
発端は、2010年6月末に腹痛でトイレに1時間ほどこもったことだった。7月に入ると下痢が続き、下旬に血便が出たのを機に、星野さんは近所の消化器系クリニックを受診。直腸内視鏡でモニターを見ながら、星野さんは自分ががんに侵されていることを知った。
「モニターに血が混じった腸壁が映った時点で、医師と看護師が無言になってしまったんです。これはまずい、と思いました」
大腸がんです――とは、医師ははっきり言わなかった。だが、渡された血液検査の表を見ると、肝機能のところに「異常」を示すダッシュがついている。
「ショックでしたね、肝転移しているのかと。闘病記を読んできて、『大腸がんが肝臓に転移すると予後(*)が悪い』ということは知っていましたから」
数日後、クリニックから紹介された社会保険病院を受診。担当医に「大腸がんですか」と尋ねると、医師はうなずいた。
「大腸がんというと、肝転移が考えられますよね」
「……ほかの臓器からの肝転移よりも、選択肢や対処方法はたくさんありますから」
医師の言葉に、星野さんは肝転移を確信。医師はその場で検査や入院、手術日などのスケジュールを決めた。生検(*)の結果は、肝転移を伴うステージ(病期)4の大腸がん。8月18日に手術を受け、大腸の一部と肝臓の4割を切除した。
9月6日に退院し、翌日から抗がん剤治療を開始。現在は、アバスチン(一般名ベバシズマブ)とXELOX療法〈ゼローダ(一般名カペシタビン)+エルプラット(一般名オキサリプラチン)〉の併用療法を行っている。治療のかたわら仕事も続けているが、副作用がつらい。
「夜、外にゴミ出しに行くと、指先にズキンと針を刺したような痛みがくる。それから、飲食店で氷入りの水を飲むと、口がしびれてしまうんです。味覚が変わり、手足がしびれて箸を使うのに不自由することもあります」
ともあれ、これまでに闘病記から学んだ知識が、自らの闘病生活に大いに役立っていることはいうまでもない。
「大腸がんの闘病記は110冊ぐらいあるんですが、手に入れた本にはざっと目を通しているので、病状や治療法については大体見当がつく。だから、不安や驚きはそれほどなかったですね。同じ病気の闘病記を3冊ぐらい読むと、経済的負担も含めて、今後の病気の見通しが立つ。女房のために始めたことが、こんな形で自分に役立つとは思いませんでしたね」
*予後=今後の症状の医学的な見通し
*生検=患部の一部をメスや針などで切り取って、顕微��などで調べる検査
闘病プロセスを数時間で追体験できる
闘病記の収集を始めて15年。その間に闘病記の世界も大きく変貌を遂げたと星野さんは言う。
「仮に大腸がんの患者さんを初級・中級・上級に分けるとすると、初めてがんの告知を受けて茫然とするのが、初級レベル。『がんがどの部位にできると、ストーマ(人工肛門)になる可能性が高いか』と疑問を持って調べ始めるのが、中級レベル。上級レベルになると、『肝転移に有効な肝動注療法が受けられる病院はどこか』と、海外のデータベースにまでアクセスして調査する人もいます」
近年、医療の情報公開や患者の意識の変化に伴い、中・上級の患者さんが増えている。だが、初級レベルの患者さんにとって、ある程度の知識が一晩で得られる闘病記のメリットは大きい、と星野さんは語る。
「キューブラー・ロス博士が指摘したように、がんと直面した患者さんは、否認・怒り・取引・抑うつ・受容の5段階を経験しなければならない。そのプロセスを数時間で追体験できるのは闘病記以外にないと思います」
一方で、最近はインターネット上にさまざまな情報があふれ、ネット闘病記を発表する患者さんも増えている。個人のブログやホームページに掲載された闘病記から、闘病記を集めた投稿サイトに至るまで、その数は膨大だ。時々刻々と医療の技術が変わるなか、インターネットのリアルタイム性や利便性は無視できない。そんななか、書籍としての闘病記にはどんな意義があるのか。星野さんはこう語る。
「ネットで問題になるのが、情報の信頼性です。出版された闘病記のメリットは、出版社を見るだけで内容の“ 見当” がつくこと。プロの編集者が介在しているという点で、信頼性もある程度保証されている。その意味では、ネットの闘病記にも編集者が必要ではないか、と僕は思っています」
どんな闘病記からも学べる余地はある
一方、自費出版には「編集者のレベルが保証できない」という難点があるが、なかには一読に値する作品もあるので、十把ひとからげにくくることは難しい。本の内容が千差万別であると同時に、受け止め方も読者によって千差万別なのが、闘病記の特徴なのだと星野さんは言う。
「たとえば、絵門ゆうこさんの闘病記を読んで疑問を感じる人もいるでしょうが、『あれだけ迷って怪しげな治療に走る気持ちもわかる』という人もいるはずです。性同一性障害の人が書いた乳がんの闘病記『ぽっかり穴のあいた胸で考えた』などは、ちょっと哲学的なことを考えさせる内容になっています。ある人にとってはその闘病記が有益ではなかったとしても、他の人がそこから何かを学ぶ可能性はある。ただし、宗教の勧誘など怪しい臭いがするものや、読んで腹が立つようなものは、古本屋の主人の特権で『見なかったこと』にしています(笑)」
では、患者さんにとって、闘病記の賢い利用法とは。星野さんはこうアドバイスする。
「自分の病気に関する闘病記、それも自分と年代や環境が近い人のものを3、4冊探し出して読んだほうがいいですね。闘病記で発病からのプロセスを追体験し、その上で冷静に自分のことを考えてほしい。同じ乳がんでも、再建手術をした人もいれば、抗がん剤を拒否した人もいる。まずは闘病記でさまざまな選択肢の実例を知り、そこから先は、雑誌やネットで知識を深めていくことをお勧めします」
パラメディカの情報資産を「闘病記文庫」に託して
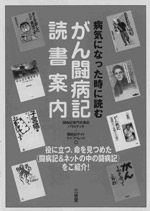
闘病記専門古書店<パラメディカ>+闘病記サイト<ライフパレット>編(三省堂)
定価1,680円(税込)
現在、星野さんが取り組んでいるのが、全国の図書館や病院に「闘病記文庫」を設置する「健康情報棚プロジェクト」の活動だ。これは、患者や家族の視点から、病気について学べる健康情報ステーションを全国に展開することを目的としたもの。東京医科歯科大学の図書館司書・石井保志さんらが中心となり、04年に発足した。星野さんも、発足当初からこのプロジェクトに参加。闘病記の古書収集を手掛けてきた長年のノウハウを活かし、闘病記文庫の研究と実践に貢献している。
「アメリカでは病気になったときに図書館に行くと、大学院出身の司書が情報収集の相談に乗ってくれる。それを考えると、僕がやってきた仕事は本来、図書館がやるべきことなのではないか。闘病記文庫はすでに約100カ所の図書館や病院にできています。僕が死んでも、僕の仕事は闘病記文庫という形で引き継がれていくのかもしれません」
仮に自分がこの世を去っても、苦心して作った闘病記リストは貴重な情報資産として後世に受け継がれていく。そのことに、星野さんは大きな意義を感じているという。
今もつらい抗がん剤治療は続いているが、闘病記探しを続けるためにも、「早く体力をつけて元気になりたい」と星野さんは思いを語る。
妻のがん再発をきっかけに始めた、闘病記探しの終わりのない旅。それが、回り回って自分自身の闘病を支えてくれたことに、星野さんは不思議な巡り合わせを感じているという。
「僕はもともと“ ネコ型” 人間で、人とベッタリかかわりたいと思うほうではないんです。ただ、この仕事をやっていると、メールのやりとりを通じてネコ型なりにお客さんと深くかかわることになる。そのやりとりから学ぶことも多いし、自分自身も大きく変わった気がしますね。
うちのお客さんは、少なくとも、自分の病気から逃げようとしない人たちばかり。そういう人たちとの交流は、自分にとっても大いに勉強になります」
パラメディカが星野さんにもたらした最大の財産とは、多くの勇気ある人々との出会いでもあったようだ。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


