がん医療の最前線で働く医師が、がんになって得たものとは 再発したら、そのときはそのとき。今は1日1日、ベストを尽くすだけ
「悪い考えは断ち切れ」大学の先輩の言葉に救われた
そんな植田さんを支えたのは、家族と友人たちだった。
植田さんは妻と3人の子供に頼んで、習字で「生きる」という字を書いてもらった。墨痕鮮やかな4枚の半紙を病室の壁に貼り、それを眺めては気合を注入した。当時高校生の長男と小学生の娘2人、そして妻――それぞれの個性が宿った字が半紙のなかで躍動している。それは、闘病中の植田さんにとってずいぶんと励みになったようだ。
入院先が母校の病院で、1年前まで勤務先であったこともあり、学生時代の仲間や同僚もひんぱんに見舞いに訪れた。主治医は母校の1年先輩で、互いに酔いつぶれるまで酒を酌み交わした仲。大学のバスケットボール部の先輩だった泌尿器科の教授も、毎日のように顔を見せてくれた。
「孤独とは無縁の闘病生活でした。本当に恵まれてましたね」
と、植田さんは当時を振り返る。
当時、仲間たちからもらったアドバイスのなかで、今も心に残っている言葉がある。やはり大学の先輩だった精神科の教授が、あるとき植田さんにこう語りかけた。
「悪いことを考えてもしようがない。悪いことが頭に浮かんだら、その思考はいったん断ち切って、いいことばかり考えるようにしなさい」
マイナス思考を続けていると負のサイクルに入り、ストレスが高じて免疫力が低下してしまう。マイナス思考と決別し、プラス思考に切り替えることが大切――なまじ医療の専門知識があるだけに、治療の見通しを悲観しがちだった植田さんにとって、このアドバイスは大きな助けとなったようだ。
骨髄移植が成功し退院、そして復職
入院の3カ月後、やっと適合するドナーが見つかった。移植の日は9月1日と決まり、2カ月前から移植の準備段階に入った。植田さんは、移植ができる喜びで胸をふくらませた。
とはいうものの、移植に先立つ前処置の苛酷さは想像をはるかに超えていた。
骨髄移植を行うためには、事前に、自分の骨髄を徹底的に破壊しなければならない。致死量ぎりぎりまで抗がん剤を投与し、合計12グレイの放射線を全身に照射。
「抗がん剤の投与が終わり、放射線の照射が始まると、もう自力では立ち上がれない。全身がだるくて、口では表現できないようなつらさでしたね。思考能力が落ちているから、どうにでもしてくれ、という感じでした」
移植の当日、抜け殻のようになってベッドに横たわり、移植部屋で骨髄液が来るのを待った。移植は見事成功し、2週間弱で白血球が上昇。発熱をステロイドで抑えながら、移植した骨髄液が定着するのを待った。恐れていたGVHDの出現もなく、2週間ほどで移植部屋から個室に戻ることができた。
そしてその年の12月中旬、植田さんは晴れて退院の日を迎える。移植から数えて約100日、入院してから9カ月が経過していた。
大好きなお酒はやめられない
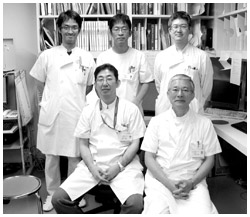
千葉県がんセンターで職場のみんなと
07年4月、植田さんは千葉県がんセンターに復職した。リハビリも兼ねて体力の回復に努めた後、半年後に本格的に仕事を再開。08年4月には泌尿器科部長に就任した。
近年、千葉県がんセンターは地域のがん医療を担う中核病院として、その重要性をますます高めつつある。前立腺がんや膀胱全摘出、腎がんの手術に関しては全国でも有数の手術実績を誇っており、泌尿器科全体の手術件数も、以前と比べて1.6倍に増えているのだという。
現在、植田さんの勤務時間は、朝7時から夜8時ぐらいまで。激務というほかないが、部長として泌尿器科をあずかる立場だけに、仕事を減らすことはできないのが実情だという。
「もし僕が仕事を減らしたら、泌尿器科のみんなにしわ寄せがいってしまう。若手がだいぶ育ってきたので、もう少し経てば楽になるんじゃないか、と期待しているんです」
とはいうものの、体調が悪いと、やはり再発の不安が頭をよぎる。そんなときは、自分でこっそり採血・検査をし、異常がないことを確認しては胸をなで下ろしているという。再発を予防するため、「なるべく睡眠をとるよう心がけている」という植田さん。朝はトマトジュースと牛乳をコップ1杯、昼は野菜入りジュースを飲むことを習慣にしているという。しかし、大好きな酒はやめられない、とも。
「仕事のストレスを和らげるためにも、酒は必要ですね。最近はビールや焼酎が中心です。酒がないと、この仕事、やってられませんしね(笑)」
患者とともにがんと闘う医療者に課せられた、責任とプレッシャーの重み――植田さんの言葉の端々から、それをうかがうことができる。
「この仕事をしていると、常に患者さんのことが頭から離れないんです。でも、気がかりなことは毎日たくさん出てくるので、『今、考えてもしようがないと』と頭を切り替えることも大事。そうしないと、気持ちが引きずられてしまいますから」
悪いことばかり考えるのはやめて、気持ちをプラスに切り替える――入院中に先輩から教えられたメンタルケアは、重圧の大きい激務をこなす上でも大いに役立っているという。
死生観を持つことの大切さを痛感
がん患者の立場を経験したことで、植田さんの医師としての姿勢はどう変わったのだろうか。
「患者さんに対して、少し、優しくなりましたね。もっとも、医者は患者さんをリードしていかなければならないので、優しいだけではダメなんです。その意味では譲れない部分もありますが、なるべく時間を作って、患者さんとできるかぎり話をするようにしています。患者さん1人ひとりの人格や個性を重視して、その人に1番ふさわしい治療をしてあげたいと思っています」
自分が患者の立場になったことで、気づかされたことも多かった。その1つが、患者とのコミュニケーションのとり方だ。
「最初の人間関係の作り方によって、医者と患者さんのコミュニケーションがうまくいかなくなることもある。だからこそ、医者は患者に向き合うとき、言葉を選ばなくてはならない。患者さんが理解できるように、相手に合わせて言葉を選び、文章や絵を描きながら、かみ砕いて伝えることが大切。そして、説明したときは必ず、『わかりましたか?』と確認するようにしています」
植田さんが臨床の現場で最近気になるのは、死生観を持たない患者があまりにも多いことだという。
「最近は死生観というものがなくなっているから、病気になって初めて右往左往する人が多いんですね。病気になったら、今後の自分はどうすべきか、自分の人生はどうあるべきかを考えて欲しい。今は人口の3割ががんになる時代。前もって、心の準備をしておくことは大切だと思いますね」
植田さん自身、がん体験により死生観は大きく変化したという。
病気になる前は10年単位で人生設計を描き、それを着実に実現してきた。だが、厳しい闘病生活のために自慢の体力が失われたことで、「いずれ開業して自分のために仕事をしたい」という未来はなくなったという。
「以前と比べると体力がないので、開業するには健康面でも資金面でも不安がある。今となっては開業もできないので、専門医療機関の勤務医として患者さんのお役に立てれば、と思っています。人間、結局はなるようにしかならない。どうやって医師としての最後をしめくくろうか、といつも考えていますね」
1日1日、患者さんのためにベストを尽くしたい
再発の不安と向き合いつつも、自分の死を受け入れる準備はできている、と植田さん。
「人間はいつか必ず死ぬ。再発したら、そのときはそのときです。今は医者として毎日のように手術も診療も行っているわけですから、1日1日、無事終わってくれればいいな、と。手術の質を上げ、治療後の合併症を最小限にとどめ、患者さんのために誠心誠意ベストを尽くしたい。それから、部長として若い後輩を育て、次の世代への橋渡しができれば、と考えています」
植田さんはがん体験を持つ医療者として、声高に自らの使命を語ることはしない。だが、病身を押して激務に身を投じるその姿には、鬼気迫る覚悟のようなものが感じられてならなかった。
「安心できる医療を、患者さんに提供したいですね」
その淡々とした言葉の底には、患者さんへのたしかな共感が脈打っていた。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


