「命を使ってやるべきこと」に気づいたのはラッキーです 他人の痛みを自分の痛みとして感じられるようになった 元NHKキャスター/フリーアナウンサー・松本陽子さん
がんを経験して見つけた人生の道しるべ
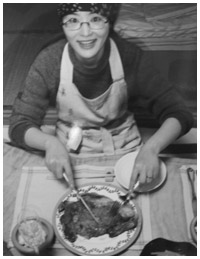
入院中は夫(当時)のほか、幼なじみの友人の母と中学時代の友人がシフトを組んで見舞ってくれた。また、患者仲間の存在も大きな心の支えとなった。
「同室の患者さんが副作用で吐いて苦しんでいる姿を見て、『こんな苦しい思いをしているのは自分だけじゃないんだ』と安心する気持ちにさえなりました。髪が抜け始めたとき、同室だった先輩患者さんが帽子を編んでくれたこともありました。苦しみを共感し合える仲間がいるということに救われました」
この頃、松本さんはノートにこんな言葉を書いている。「もし元気になれたら、後に続く患者さんのためにできるだけのことをしたい」――このとき芽吹いた思いは、人生の道しるべとして、後に大きく育っていくことになる。
一方で、仕事で取り残されていく焦りもないわけではなかった。あるとき、こんな夢を見た。職場の仲間が連れ立ってどこかに行こうとしている。自分も一緒に行きたいのに、隔絶された感じで体が動かない。皆から置き去りにされるリアルな感覚に、松本さんは胸を衝かれた。
5カ月間の入院加療の末、11月に退院。年明けに念願の復職を果たしたものの、がん患者の復職はまだ珍しく職場での微妙な違和感を感じた。
「周りは腫れ物にさわるみたい。どのように接したらいいか、わからなかったんでしょうね」
さんざん迷った末、松本さんはNHKとの契約を更新しないことに決めた。
「『もしがんが再発したら、私は何を後悔するだろうか』と、思いつくままに書き出してみたんです。仕事を続けなかったことを後悔するか、それとも、後に続く患者さんのために何もしなかったことを後悔するのか。それを自問したとき、答えは明らかでした」
これからはフリーのアナウンサーとして働きながら、患者さんのために活動していこう。そう決意したものの、新たな目標に向けて歩き始めるまでには、さらに10年近くを要した。
理由の1つは、母の病気である。松本さんが退院して1年ほど経った後、母の糖尿病が悪化して入退院をくり返すようになった。やがて認知症も現れ、受け入れてもらえる施設を求めて転々としなければならなかった。3年前にようやく落ち着き先を見つけるまで、介護保険の手続きや施設探しに忙殺される日々が続いた。
ちなみに松本さんは、がん��なったことを、母には1度も打ち明けていない。病名は「子宮内膜症」で、入院中は「東京に出張」していることにした。
「母は弱い人だから、父が死んだとき、もう母には頼れないと思った。たった1人の子供ががんになったと知ったら、体が弱い母は心臓発作を起こして死んでしまうかもしれない。そう思ってウソを突き通してきたんです」
「棚ボタより醤油せんべい」という考え方

がん対策推進計画検討委員会に患者委員として参加した
松本さんに再び転機が訪れたのは、07年秋のことである。
NHK時代から取材先であった四国がんセンター高(*)嶋成光院長(当時)の推薦で、県のがん対策推進計画検討委員会の患者委員に選ばれたのだ。自分の経験を、ようやく患者さんのために役立てることができる。松本さんは委員会で毎回資料を提出し、「患者力の活用」について熱く語った。
その年の暮れには、東京で開催された第1回がん政策サミットにも参加。全国から集まった患者委員との交流を通じて、松本さんは目からウロコが落ちるような思いを味わったという。
「いかに自分が井の中の蛙だったかを思い知らされました。いただいたどの名刺にも患者団体の名前があり、皆、患者会の代表として会議に参加している。個人の肩書の名刺を出しているのは私ぐらいでした。自分1人の経験でいえることには限界がある。患者や家族の声を行政に反映させていくためにも、患者会を作ることの大切さを思い知らされました」
当時、愛媛にはすでに2つの患者会があった。だが、どちらも傾聴や共感を活動の基本にしており、対外的な情報発信には積極的ではないのが実情だった。
互いの交流をベースとしつつも、患者の側から現状の改善を求めていくことも必要ではないか」
そんな思いから、松本さんは08年4月、「愛媛がんサポートおれんじの会」を発足。四国がんセンターの高嶋院長(当時)はじめ、がん拠点病院の医師を顧問に迎え、活動は順調に拡大していった。松本さんは、政策提言にも患者・家族が関わるべきだと考えている。
「私は『棚ボタより醤油せんべい』説を唱えているんです。今までのがん政策とは、いわば棚の上からボタ餅が落ちてくるのを、患者が下で待っているようなもの。棚の上には役人や医療者がいて、『これがよかろう』とボタ餅を患者に放ってくれる。でも、患者がほしいのは、実はボタ餅ではなくて醤油せんべいかもしれない。つまり、『何がほしいかは自分たちで決めるべき』だということです。私たち自身が棚までよじ登って行き、何が欲しいか伝えない限り、いつまでも上から与えられるものをありがたく受け取ることしかできない。それでは本当の意味で、患者のためのがん医療にはならないそれが私の基本的な考え方なんです」
おれんのじの会では今、「ピアサポーター(*)養成事業」を行っている。
がん経験者が、他の患者・家族の役に立てるかもしれないということを知ってもらうための、ピアサポーター“入門編”は、県内4カ所で、一般の方を対象に講演会を開催。経験に加えて傾聴やコミュニケーション技術などを身につけ、患者サロンなどで活動できる人材を育てる“中級編”はおもに患者会会員を対象に勉強会を実施。そしてすでにサロンなどで活動しているスタッフを対象に、疾病の基礎知識やカウンセリング技術向上ための“上級編”として集中講座を開いている。
家族会員が多いおれんじの会。家族ケアとして、日本医療政策機構市民医療協議会がん政策情報センターとの協働事業も動き始めた。家族が知っておきたい情報を集めた小冊子の作成や家族のための勉強会開催などを今後予定している。
松本さんは、個人的な活動として子宮頸がんの啓蒙にも力を入れている。そこには「若い女性が、発見が遅れることで生殖機能を失う悲しみを減らしたい!」という思いがある。2009年秋から配布が始まる女性がん検診無料クーポンを機に、子宮頸がんの正しい知識の普及と検診呼びかけに取り組む予定だ。
*高=はしご高
*ピアサポーター=同じ病をもつ人自身がカウンセラー(ピアサポーター)となって、悩みや問題について相談に応じるもの
「命を使って」生きていきたい
後に続く患者さんのために、できるだけのことをしたい――その強い思いを原動力にして、多忙な毎日を送る松本さん。自らのがん体験を振り返って、今何を感じているのだろうか。
「がんにならなければ、仕事の成果を上げ、それが収入に結びつくことが人生の価値だと信じて疑わなかったでしょう。そういう生き方も否定はしませんが、人生にはもっと大事なこともあると思う。『命を使ってやるべきことは何か』ということに、30代半ばで気づくことができた。それは本当にラッキーだったと思います」
「患者さんのために」を自分の使命と感じ、松本さんが活動を始めて1年半がたつ。
「『患者さんや家族の、言葉にできない本当のつらさにどこまで寄り添えているのだろうのか』と、自分の非力に気力が萎えることもあります。そんなとき、私を奮い立たせてくれるのは、逃げ出すことも放り出すこともできず病気と闘い続けなければならない患者さんたちの姿なんです」と松本さんは話す。
「ある日の夕方、がんセンターの待合室で、女性の患者さんがテレビの大画面を見るともなく眺めていたんです。背中を丸め、ただ、ポツンと座って。それを見たとき、数年前の自分の姿が重なり、胸がいっぱいになった。患者さんが少しでも楽な環境で病気に立ち向かえるようにしたい、と心から思いました。そんな象徴的なシーンの1つひとつを思い出すたびに、がんばろうと思えるんです」
他人の痛みを自分の痛みとして感じられる、豊かな感受性と共感力――それこそが、松本さんの強さの秘密なのかもしれない。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


