多重がんに襲われた脳外科医が、がんになって学んだものとは? がんで死ねたら幸せと思い込む。それが私の死との向き合い方
上からの目線ではなく水平の目線で
ターミナルケアにかかわっていた自分自身が、がんに罹患するという運命の皮肉。それは、冨田さんの医療者としての姿勢を変えずにはおかなかった。その1つが、外来患者への接し方である。「がんになって以来、患者さんの話によく耳を傾けるようになった」と、冨田さんはいう。
「外来に来る患者さんは、前の日からずっと悩んでいるんです。だから、診療のときにはやさしく話を聞いてあげなくちゃいけない。患者さんと話をしながらキーボードを打つ、というのは論外です。医者がいくらキータッチに慣れているからといって、それで患者さんの気持ちがよくなるとは思えない。患者さんと話をしながら医者がキーボードを打つとき、患者さんは苦痛を感じるのだということ、それが、健常な医者にはなかなかわからないんです」
医師の席から患者の席へと座る場所が変わったとき、それまでの自分がいかに「上から」の目線で患者に接していたかを思い知らされた。医師の前に座ったとき、患者は大きな緊張と不安にさらされる。だからこそ、医師は患者に対して、上からの目線ではなく水平な目線で接しなければならない――緩和ケア医・小澤竹俊氏の著書に書かれていた言葉が、冨田さんの心に響いた。
「患者さんと医療者との関係は、上下関係から出発する。だからこそ、医療者が1歩下がって互いの関係に一致点を探すしかない。とくに注意しなければならないのは、『医者は患者を怒ってはいけない』ということです。医療者である以前に1人の人間であること、それが、医療にかかわる者の基本なんです」
先達の言葉にふれ死生観を深める
1人のがん患者として死に向き合う経験は、冨田さんの内的生活も大きく変えていった。がんを患ってからは、小説を読んでも面白いとは思えなくなった。虚構の世界にリアリティを感じることができなくなったのだ。死に対する考えを自分なりに構築しなければ、苦痛ばかりが押し寄せてくる。気持ちをしっかりと立て直すために、生と死にかかわる実体験にもとづいた本をむさぼるように読んだ。
冨田さんが深い印象を受けたもののなかに、小説家で精神科医でもある帚木蓬生氏が紹介していた次の言葉がある。
「神様 私にお与えください/変えられないものを 受け入れる落ち着きを/変えられるものは 変えてゆく勇気を/そして この2つのものを見分ける賢さを」
帚木氏は元気に診療していた頃、患者の自助グループと共に「セレニティ・プレイヤー(平和の祈り)」を最後に唱えた。それがこの言葉だったという。
「帚木さんも、自分が急性骨髄性白血病になってはじめて、この言葉が身にしみたと語っています。病気になると、願望や希望と現実の世界とが、だんだん離れていく。『こうなったらいいな、こうであればいいな』と願う『たら、れば』の世界と、現実との乖離。それを、この言葉は���現しているのではないか。大事なのは、『今、ここ』に生きることであり、それに満足することだと思うんです。『たら、れば』の世界にとらわれてしまったら、まず、よいことはありませんから」
だれもが逃れることのできない死の諸相についても、あらためて思いをはせるようになった。世界には悲惨な死が満ち満ちている。ユダヤ人強制収容所での死、太平洋戦争下の硫黄島での戦死。刑死、事故死、内戦による死、虐殺による死。こうした死に比べたら、病気で死ねる自分は幸せといえるのではないか。
「こんなふうに比較するのは失礼で傲慢なことかもしれません。でも、そう思い込まないと、自分の気持ちが救われない。家族や看護師、医師の皆さんに支えられて、病気による死を迎えられる。『がんで死ねるとは、なんと幸せなことか』と思い込むこと。それが、私なりにたどりついた死との向き合い方なんです」
死とは絶対的な苦痛からの解放である
聖マリアンナ医科大学の精神科教授だった岩井寛氏の著書からも、冨田さんは大きな影響を受けた。岩井氏ががんの全身転移と闘いながら、口述筆記で著した『生と死の境界線』のなかに、こんな1節があるという。
「仏門の苦行は耐えて悟り、自らを解放する。仏門の苦行の向こうには、希望と救いがある。しかし、がん終末期の自分の苦行は、死によって完全な自由を得る。どんなに苦しくとも、最後は死によって完全な自由を得るのである。だから、亡くなるまでは、どんなに苦しくとも生を選び、生に意味を求めていく。岩井先生はこう書いているんです」
このつらさの向こう側には、苦痛からの解放と絶対的な自由がある。だれもが最後は死によって完全な自由を得るのだ――。
「これは自分にとって、とても大事な言葉。そう思い込まなければ、死が不幸になってしまうから。死の瞬間までは、どんなに苦しくともがんばって生きていく。明日には世界が終わるとしても、今日、1本の木の苗を植える。その気持ちが大切だと思うんです。連れ合いには、『まだ本当に死に直面していないから、そんなことが言えるのよ』と言われますけどね(笑)」
人生の伴侶に代役はない
冨田さんの言葉の端々からは、奥さんが人生のパートナーとしていかに大きな存在であるかがうかがえる。
「40年間連れ添ってきて、1日の半分以上は喧嘩をしています。『今の電話の出方は“医者”だよ』って怒られちゃう。私が馬鹿だからね」
そう苦笑する冨田さん。冨田さんにとって奥さんとは、心から自分のことを思い、叱咤激励してくれる、かけがえのない存在なのだろう。
「冨田さんにとって奥さんとは、どんな存在ですか」
そう尋ねると、冨田さんはこう答えてくれた。
「空気みたいな存在。それが、夫婦というものじゃないかな。限りある命なんだから、きわめて普通のことがいかに大事かってことですよ。これで最後かな、と思いながら、2人一緒にご飯を食べるありがたみ。こればっかりは、病気してみないとわかりません」
人生の伴侶に代役はない。ささやかな日常を伴侶とともに生きることが、どんなに大きな力を与えてくれるか。その大切さを、講演を通じて冨田さんに教えてくれた人が、もう1人いる。映画監督・大島渚氏のパートナーとして知られる、女優の小山明子さんだ。
小山さんは脳卒中で倒れた夫の介護をしているうちに、うつ状態になり、自殺まで考えたことがあるという。泥沼から抜け出すきっかけとなったのは、ある気づきだった。
「女優は代役可能でも、パートナーは代役不可能。そう気づいたときに、小山さんは自分を立て直すことができたわけです。仕事によって決して自分を崩壊させてはいけない。自分が崩壊してしまえば、家庭を立て直すことができなくなる。仕事は人に代わってもらえるけれど、連れ合いに代役はいない。それだけに、連れ合いを失ったときの精神的な喪失感は非常に大きいんです」
苦しみを経験しなければ、伴侶のありがたみなどわからない。冨田さんもまた、がん体験をきっかけに、妻との1日1日を大切にするようになったという。
「俺がいなくなったら、1人でさびしく飯食うことになるんだよ」
「あんただってそうよ」
他愛のない会話を交わしながら、2人そろって食卓を囲む。その一瞬一瞬に、かけがえのない夫婦のときが刻まれていく。
「妻は『後に残されるほうがつらい、先に死ぬほうがいいよ』という。子供たちは、『お父さんが後に残されたら、私たちにとって最大の不幸』だってさ(笑)」
そういいながら、冨田さんはまた笑った。
「がんで死ねたら幸せ」そう思い込むことが大切
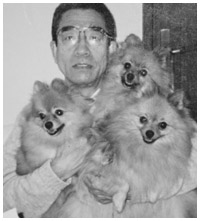
今でもこの写真は、冨田さんの手帳に大事にしまってある
2009年末、冨田さんは65歳で定年退職の日を迎える。
「定年後は、自分の技術や知識を活かしながら、がんの患者さんを一生懸命診ていきたい」と語る冨田さん。もし可能であれば、がん体験を持つ医師とネットワークを作り、勉強会や講演をしながら在宅医療などに取り組みたい――そんな夢を打ち明けてくれた。
「だれもが最後は死を迎える。死は絶対的な自由への解放であり、がんで死ねたら幸せなのだ、と。そう思い込むことが、私にとっては、苦しみから解放される唯一の方法。あせらず1歩1歩、今を大事に生きていきたいと思います」
思い込みを1つひとつ積み重ねて、人生の果実を味わいながら、今を大事に生きる――模索の果てにたどり着いた死生観に支えられて、冨田さんは今日も、患者や家族と向き合っている。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


