会社を守るため、家族を守るために彼女は病気を隠すことを決意した 孤独な女性経営者の闘病生活。支えたのは患者仲間だった
最優先は会社と認知症の母親の介護
大東さんの会社では新しい年を迎えると早々に健康診断を行う。この年、健康診断で便潜血反応が出た大東さんは、精密検査を受けることにした。かかりつけ医から京都医療センターを紹介してもらい、かつて夫の主治医であった小泉さんと30年ぶりに再会した。
「これもご縁なのでしょうか。小泉先生に主人のことをたずねたら、『大変な闘病でしたね』と覚えていてくれました。それで冗談で『私は殺さないでね』とお願いしたものです」 検査の結果、発見された大腸がんは進行性であり、術後「余命1年程度」という厳しい宣告を聞くことになった。
進行がん患者の多くは告知されたときのことを「頭の中が真っ白になって何も考えられなかった」と振り返る。しかし大東さんは、自分が生きている間にすべきことをリアルに思い浮かべながら、帰路についたという。大東さんにとって最優先は会社であり、認知症の母親の在宅介護であって、勤めていた会社を辞めて専務になってくれた息子に迷惑をかけないためにも、自分のがんなんかにかまっていられない。そんな心境だったようだ。
会社関係者や友人知人には、ポリープの手術をするといって入院し、大腸回盲部を切除する手術を受けた。
「ポリープ」というので、見舞いに来る人たちもそれほど深刻ではなかった。ちょうどバレンタインデーの日に病室を訪れた友人は「あなたのことだから、きっと素敵な先生を何人も見つけてると思って、これ、持ってきてあげたよ」とチョコレートを差し入れしてくれた。
「気楽な入院生活でしょう(笑)。がん患者としての扱いを受けなかった。でも、私にとってはそれがよかったです。人に頼って甘えてしまうほうが私にはストレスですから(笑)」
がん患者として扱われることがストレスになる。そんなケースとして、大東さんはある知人の顔を思い出す。
知り合いになったがん患者さんで海の好きな男性がいた。今年も海に行くのですか、とたずねると「行きたいけれども家族の気持ちを考えたら行けない」という返事。
「海には行けないけど、家族みんながぼくの体を心配してくれているから幸せだ」といって彼は亡くなった。彼の死後、奥さんは「私たちが彼を守りすぎたから、彼は遠慮して好きなことをできずに逝ってしまった」と、とても悔やんでいた。
「心配しすぎるとがん患者さんは、周りに気兼ねして、自分のやりたいことをいえなかったりするんですね。ですからサロンでは『やりたいことをしなくちゃいけないよ』といいます。今までできていたことが、がんだからできないなんていってほしくないのですよ。やりたいことを我慢するなんてもってのほか。患者さんには最期まで普通の生活をしてほしい。それが私の望みです」
責任ある立場での闘病は孤独
仲間の存在を求めて
悩みを打ち明ける相手は主治医だけ。それ以外の誰かに気持ちを訴えることはしないと、大東さんは心に決めた。とはいえ、昼間はがんを忘れて過ごすことができても、認知症の母と2人きりになる夜は、そうもいかなかった。
不安と悲しみで押し潰されそうになる。「なぜ?」という思いが溢れてきて叫びだしたくなる。あまりにつらい夜、車で家を出て闇雲に高速道路を走り続けることもあった。1人走らせる車の中なら、泣くのも大声を出すのも自由。そして翌朝には鏡の前で「今日はこんなふうに笑おう」と、笑顔を作ってみせる……。
あるとき、深夜の高速道路で事故があり、巻き込まれて帰れなくなった。明け方に帰宅すると寝ているはずの母が起きていたので「ごめん! 車がパンクしちゃった!」と謝ったが、その後、母は大東さんが出かけようとするたびに、「パンク、せんといてね」というようになった。
「『がんって、死ぬんやなぁ』と母がぽつりというのですね。さすがにその言葉で泣きました。『あんたを残して死なへんよ』って答えながら感じる孤独。そして周りに気づかれないように普通の生活を意識することに神経を使いました」
仲間がほしいと思った。同じ気持ちの仲間と話す。交わる。そんな集まりを探した。京都新聞で東京にある患者グループの記事を見つけ、すぐさま連絡先を問い合わせて手紙を出した。文通が続き、京都にもそういう場が必要だと強く思うようになった。そして大東さんは、そんな願いを小泉さんには伝えていた。
医師の姿を見て……
信頼が揺るぎないものに
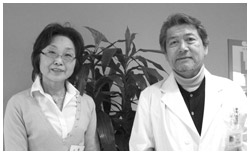
大東さんは術後予定していた抗がん剤治療を、著しい白血球減少という副作用のため断念していた。すると「あとは自宅でのんびり余生を」というコース。もうできる治療はないのか……肩を落とす大東さんに、担当医の医師はいった。
「転移が見つかれば、一緒に闘いましょう」
手術をしてから8年が過ぎたが、常に再発の恐れはあるし、だるさが続けば肝臓がんではないか、咳が出たら肺がんではないかと不安がよぎる。しかし大東さんにとって「一緒に闘う」と言い切った医師の言葉は大きな支えになっている。
「私の体は先生が守ってくれるから、あとは自分の精神をどうコントロールするかだと思うようになったのです」
そして、亡夫と自分の主治医であり、「仲間がほしい」という多くの患者の思いを理解し、がん患者サロン設立に奔走した小泉さんの存在は、大東さんにとって、ことのほか大きい。
患者と医療者の垣根を低くしようとサロンの椅子に腰を落ち着け、患者たちの質問に丁寧に答える医師の姿に、「お医者さんを信頼していいのだということを教えられた」とある患者は語った。
患者同士同じ仲間としてつながり合う

2009年3月、小泉さんの退官のパーティーの席で、大東さんは白いバラがピンクのバラを取り囲むようにアレンジした花束を小泉さんに手渡し、次のような言葉を添えた。
「白いバラは先生です。ピンクのバラは先生方に囲まれた私たち患者です。先生方に守られて患者の精神がきれいに色づき、ピンクになりました。私たちはこれからも白いバラに囲まれて生きていきたいです。患者は病院や先生に守られていることに感謝しています」
患者自身は心をきれいな色にしようと自覚しなければいけないし、その努力が必要。医療者は患者の思いに気づき、患者を守ろうとしてくれる。それが患者と医療者の関係ではないか。
「私、自分で守ることは慣れているけど守られることが下手だと思っているんですよ。損な性格なのかしら。でも先生方に守られていることは実感できるんです」
そして大東さんはこう続ける。患者同士、同じ立場の仲間としてつながり合う、と。
「サロンへの参加者がフラットな関係がいい」
患者サロンの世話人である大東さんだが、決してリーダーではないと強調する。
「患者さんが『来てよかった』とおっしゃるのは、問題が解決してよかったというより、仲間と過ごして『私も元気でいられるかな』と励みになってよかったということではないでしょうか。みなさんがそんなふうに思えるサロンを続けていきたいですね」
「優しさと癒やしと強さ」がものづくりの原点
介護をしていた母を見送り、会社を息子に引き継いで会長となった大東さんは、がんを秘密にしていたことをカミングアウトした。それからは長年培ってきた知識や技術を生かして、これまで以上に商品開発に没頭するようになっていった。
「オノックス」と名づけられた寝具もその1つ。自分の心身をいたわるものがないかと探るうちに出合ったのが小野砿石と呼ばれる石。詳しく調べると、体温や血液循環に影響を及ぼすことがわかり、疲労回復や免疫力強化が期待できるというので誕生させたのが、石をそのまま織り込んだ掛けシートや敷きパッドだった。
「人を快適で心地よく思える空間にするインテリアやファブリック(繊維製品)を作っています。優しさと癒やしと、使う人を包み込む強さを備えたものというのがコンセプトです」
ものづくりの根底に流れるその精神は、大東さんの、自分以外の大切な誰かを、かけがえのない何かを守るという生き方から来ている。商品を愛用する人の笑顔。サロンに来る患者さんたちのほっとした表情。そして息子たちが頑張っている姿。そうしたものを見ることが大東さんの何よりの喜びのようだ。
「うずらプラナスの会」連絡先
〒604-8822 京都市中京区壬生町31-1-526
TEL/FAX 075-803-3233 e-mail
京都がん医療を考える会内 理事長 佐藤好威
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


