「1人じゃないよ」30代でがんを患った女性が贈る“生きる”メッセージ 思いもよらなかった術後の後遺症。それでも彼女は生きる意味を探し求めた NPO法人HOPEプロジェクト理事長・桜井なおみさん
「お風呂場にはどうして鏡があるの?」
04年9月から翌年1月まで入院し、術後の化学療法が行われた。エンドキサン(一般名シクロホスファミド)、ファルモルビシン(一般名エピルビシン)、5-FU(一般名フルオロウラシル)の3剤併用によるCEF療法である。
吐き気などの副作用は思ったほどではなかったが、抗がん剤の点滴により、血管が炎症を起こす血管炎には苦しめられた。一方、脱毛についてはあまり気にならなかったものの、胸を失ったことのショックは大きかった。手術後、初めて入浴したときのことだ。浴室に入ると、のっぺらぼうになった胸が鏡に映っていた。
(全摘って、こんなふうになっちゃうんだ……)
自己の奥深く秘めていた女性性がうずき出し、やるせない思いがこみ上げてきた。
(なんでお風呂場って鏡があるの。胸って、こういうものじゃなかったよね。砂漠みたい……。なんて呼べばいいの?)
触診を重視する主治医の方針で、リスク期間中は乳房再建を行わないことになっている。だが、失った胸への違和感は未だに払拭できていない。
「今でもフィットネスクラブに行くと、イヤだなあと思いますよ。競泳用の水着って胸パッドがないから、形がいびつなのがわかっちゃうんです」
化学療法終了後、05年4月1日付で職場に復帰。隔週1回のペースで通院し、ホルモン療法をスタートした。最初の2年間はゾラデックス(一般名ゴセレリン)を月1回ずつ投与し、3年目以降は3カ月に1回のリュープリン(一般名リュープロレリン)投与に切り替えた。
更年期障害で心身ともにボロボロに
桜井さんの誤算は、復職と同時に始めたホルモン療法の副作用が、化学療法以上につらかったことだ。更年期障害の症状が集中的に出てしまったのだ。
仕事中もホットフラッシュやイライラが続き、早朝覚醒で深夜2時頃には目が覚めてしまう。3カ月ほど不眠状態が続き、歯ぎしりで歯もボロボロになった。
病気休職明けといっても、仕事のほうは手加減してはくれない。復帰したとたん、休職前と変わらない激務が待っていた。通院治療を受けるために、5日分の仕事を4日でこなさなければならない。リンパ浮腫もあり、設計に必要な複雑なマウス操作も夕方にはできない身体になっていた。「元に戻りたい」と願う自分と、「元に戻るのは怖い」と思う、2人の自分がそこにいた。役職から下りたものの、うつ症状はひどくなり、何もやる気がしなくなっていた。
大塚病院の女性専��外来を受診したところ、適応障害と診断された。手術・化学療法・ホルモン療法、そしてその後の職場復帰――ジェットコースターのように乱高下する環境の激変に、体と心が悲鳴を上げたのだ。このまま仕事を続けていけば、いずれダメになってしまう……。桜井さんが退職したのは、職場復帰から2年半後のことだった。
だが、仕事を辞めたことによる精神的ダメージは予想以上に大きかった。退職して初めて、仕事が自分のアイデンティティそのものだったことを悟った。
「環境デザインがやりたくて大学に入り直し、一生懸命仕事をしてきたのに、その仕事を辞めてしまった。それは、がんの告知以上に心の傷として残りました。『あんなに無理な生活をしたから、がんになったんだ』と仕事を恨む気持ちもありました。病気になるほどがんばったのに、結局全部失っちゃった。大学入学後の人生をすべて否定されたような気分になってしまったんです」
会社は辞めたものの、今さら専業主婦にはなれない。職業人としてのプライドから、治療費だけは夫に頼りたくないという気持ちも強かった。昔のクライアントから仕事を受注し、フリーランスで仕事を始めたものの、これまでの仕事とのギャップがこたえた。収入も激減し、1カ月の収入が治療費ですべて消えることも。「ワーキングプアってこういうことなんだ。やっぱり正規雇用でないとだめなんだ」と痛感した。
そんな折、たまたまハローワークで求人を見つけた(社)日本植木協会に応募し、08年2月、正職員に採用された。50~70代の職員が中心で、上司や同僚は病気や通院にも理解を示してくれる。それが何よりもありがたかった。
病気になったことにはきっと意味がある
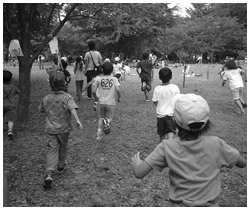
更年期障害に苦しみ、仕事と治療との両立に悩み続けた桜井さん。その苦しい時期を乗り切る上で支えとなったのが、HOPEプロジェクトの活動だった。この組織を立ち上げたきっかけについて、桜井さんはこう語る。
「手術が終わって病院のベッドで寝ていたときに、『30代の乳がん患者が大学に入り直して心理学の資格をとり、体験を活かして、今は相談員をやっている』という記事を読んだんです。『これだ!』と思いました。『病気になったことには意味がある。若いからこそできることがあるはず。その意味をこれからの人生の中で探してみよう』と思ったんです」
以前から、病院の中で隔絶された小児病棟の存在が気になっていた。緑の仕事に関わってきた自分のスキルを活かして、病気の子供たちのために何かできないか。公園の福祉的利活用が必要なのではないか。そんな思いから生まれたのが、06年に始めた「ボタニカルキッズクラブ」である。
従来から子供向けのネイチャー・プログラムは行われていたが、病気を抱える子供を対象にしたものは見当たらなかった。そこで、化学療法の期間中に資料を集め、企画書を作成。「財団法人がんの子供を守る会」に企画を持ち込み、協力を求めた。その後、国営昭和記念公園の「夢プラン」に計画を申請。公園事務所の理解も得られ、ボタニカルキッズクラブの活動拠点になった。「病気に背中を押されました」と桜井さんは話す。
ボタニカルキッズクラブは、患児やその兄弟姉妹に自然とふれあう機会を提供するプログラムだ。
「木に聴診器を当てて樹液が流れる音を聞いた後、自分の心音を聞いてみる。命の音に耳をすませると、新鮮な驚きを感じます」
この活動が1年ほど続いた頃、桜井さんはがん患者をサポートするジャパンウェルネスの会合で、エッセイストの岸本葉子さんや毎日新聞記者の故・生長恵理さんと出会う。
「がん患者と社会を隔てる垣根をとりはらいたい。がんに対する社会の意識を変えていきたい」――そんな思いを共有したことで、同世代の3人は意気投合。既存の組織とはちがう発信方法を模索しようと、07年にNPO法人HOPEプロジェクトを立ち上げたのだった。
現在、桜井さんは仕事のかたわら、HOPEプロジェクトの理事長として多忙な日々を送っている。前述の出版プロジェクトやボタニカルキッズクラブの他、07年9月からは1年間、東京大学医療政策人材養成講座にも参加。筆頭研究者として「がん患者の就労・雇用支援に関する提言」をまとめ、最優秀成果物賞とDREAM賞を受賞した。この活動は現在も続いており、CSRプロジェクトとしてがん罹患と就労を患者自らが考える様々なプログラムがスタートしている。
「日本初のサバイバーによるサバイバーのためのプログラム。患者もN値(調査対象)から脱出しなくちゃ」
「1人じゃないよ」と多くの人に伝えたい

それにしても、治療と仕事に加えて、こうした活動を続けるのは並大抵のことではなかっただろう。なぜ、そんなことが可能だったのだろうか。
「むしろ、この活動が支えになったからこそ、あのつらい時期を乗り切ることができたんだと思います」と桜井さん。
桜井さん自身、病気を経験したことで変わった部分も大きいという。
「健康だった頃は、自分は1人で生きられると思っていた。でも病気を経験してみてそうじゃないということに気づかされました。出会いがすごく増えたし、皆の話を聞いて学ぶことも多い。友人たちの生き方から教えられたことが本当に多いんです」
だからといって『病気になってよかった』とは思わない。身体的には明らかにマイナスだし、病気にならずにすむものなら、なりたくなかった。でも、前の自分と比べて、人間として豊かになったな、と思うんです」
今、桜井さんの左手には、2つの結婚指輪が光っている。夫から贈られたもので、2つ目の指輪には「2004.7.30 HOPE」という文字が刻まれている。「手術日を境に生まれ変わった。この日が新しい結婚記念日なんだ」――そんなメッセージがこめられているという。
「ずっと多忙ですれ違い夫婦だったけれど、病気をきっかけに、いろんな話し合いをするようになりました。この指輪を触っていると、なんとなく安心するんですよ。自分は1人じゃないって思えるんです」
HOPEプロジェクトの活動を通じて、少しでも多くの人に「1人じゃないよ」と伝えたい。
そう言って、桜井さんはとびっきりの笑顔を見せてくれた。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


