がん闘病中の自分を自分で撮った映像作家が学び直した「病は気から」 酒もタバコも「お気に召すまま」、映像作家の仰天がん哲学
「病は気から」を再認識酒もタバコも復活
入院生活の末期、「このまま楽をしていたら、病人になってしまう」と感じた。病院のベッドに横になっている患者のかわなかさんが、「このままでは病人になってしまう」と思ったという感性が、いかにも「わが道を行く」映像作家らしい。
約1カ月の入院生活が続く中で、お尻の筋肉が衰え椅子に座るとお尻が痛くなってきた。そのうちに、「点滴で栄養は補給できるが、人間は本来、口から食べ物を入れ、お尻から出さなきゃダメなんだ」ということに気がつき、かわなかさんは予定通り、2月末に青山病院をあとにした。
退院するとき、奥さんが病院の栄養士から言われた。「酒は1年間飲まないよう。肉類は半年間食べないよう。高野豆腐はお奨めです」と。自宅に戻った日、かわなかさんが冷蔵庫を開くと、山盛りの高野豆腐の煮物が目に飛び込んできた。かわなかさんは瞬間的に叫んでいた。「こんなもん食っていたら、病人になってしまう。トンカツ買ってこい!」と。
退院してから1週間ほど、かわなかさんは自宅で神妙にしていたという。しかし、トンカツを3分割して、3分の1ずつ食べたころから、「このまま楽をしていたら引きこもりになってしまう」と覚り、最寄りのJR中央線の阿佐ヶ谷駅まで、歩いて往復するよう努めた。さすがに最初はしんどかったが、1週間で慣れた。心身ともにエネルギーがあふれてくるような気がした。「病は気から。昔の人は本当によく言ったもんです」
酒も、退院2週間後から再開した。最初、新宿ゴールデン街の行きつけの店に行き、いちばん好きな日本酒を1合注文した。1合の酒を1時間かけて飲んだ。目がカッと開いてきて、薄暗いはずの店内がまぶしかった。久しぶりの酔い、かわなかさんの「飲んべえ」が再び目覚めた一瞬だった。
かわなかさんの酒は、基本的に「外酒」である。ただ、その「外酒」が半端ではない。
「外で飲み始めたら、カネが無くなるまで飲みます。最近は焼酎が主体ですが、20杯は飲みますね。何軒もハシゴをするんですよ、酒場に何の義理もないんですが。酒飲みなら、この気持ち、わかってもらえると思いますけど……」
かわなかさんは、こちらの気持ちを見透かしたように、そう言って、呵々大笑した。
復活したのは酒だけではない。タバコは現在、何と1日5箱! かわなかさんは「クセですから。それで死ぬのなら、いいんじゃないですか」と、こともなげに言う。さらに「ボクは今、肺がんに挑戦しているんです。ただ、肺がんは痛いらしいね。今年からIDカードがないとタバコが買えなくなるそうだけど、それを機にタバコを止めてやろうかとも思ってるんですよ」���煙に巻いた。
「人間はどう生きたって100年ちょっと」
手術後3年目の春を迎えた現在、3カ月に1回、執刀医が転院した吉祥寺の病院で診察を受けている。昨年1回、胃カメラをのんで検査をした以外、医師と話をするだけで診察は終わる。「がんは発症しなきゃ、がんではないんです」と、かわなかさんは恬淡としている。
「胃がん手術を乗り越えて、改めて思うことは?」と水を向けると、即座に次のような返事が返ってきた。
「人間の身体には、60兆個の細胞があるそうです。それだけの細胞があれば、多少悪くなった細胞が必ずあるはずです。それががんになるかどうかは、神のみぞ知る。あまり気にしてもしようがない。だから、ボクは再発についても平常心です。
もともと人間の死亡率は100パーセント。例外はありません。どう生きたって、寿命は自分では決められないし、死ぬのが当たり前だと思えば、この歳になって、もういつ死んでもいいと思うんです。ボクが死ぬと、多少、仕事で迷惑がかかる人がいるかもしれませんが……。
ボクががん患者の仲間に伝えたいことは、『病は気から』ということだけです。
医師の言うことは聞かなければなりませんが、自分の気の持ち方、自分のチョイスも大事ですよ。新宿ゴールデン街の酒場の主人も言っていました。『猥褻と猥雑がなければ新宿ではない』と。
私の身体も60兆からの細胞で構成されてるわけですから、少しぐらい悪いのを背負っていて当然でしょう。悪い部分を背負って生きていくのが人間です。がんになっても、そのくらいの開き直りが大事だと思いますね」
苦労に苦労を重ねた映像作家への道程

母、富代さんに抱かれたかわなかさん
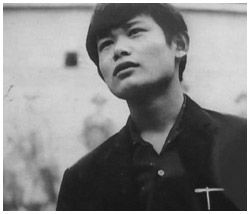
上京したてのころのかわなか青年
ふっと「無頼派」という言葉を思い出した。かわなかさんのがんに対する意識、人生に対する向き合い方は、まさにいい意味で「無頼」的である。同時に、いのちに対する恬淡とした心持ちは、衆生の煩悩を突き抜けていると言おうか、一種、覚りの境地に達した人の雰囲気を感じさせる。「無頼」であって「覚者」、ただものではない。
それは、かわなかさんが映像作家に辿り着くまでの人生行路をうかがって、得心がいった。
昭和16(1941)年に東京・錦糸町で生まれたかわなかさんは、母親に連れられて、安来節で有名な安来の豪農であった父の実家に疎開した。合金の研究者だった父は東京に残った。かわなかさんは戦後、東京に戻るが、間もなく母親が亡くなり、再び、安来の父の実家に預けられる。
その後、一時期、埼玉県川口市で父と兄弟の3人暮らしをした。しかし、父親が自殺、みたび安来の父の実家の世話に。父の実家でいじめられ、遂にぐれた。児童相談所に預けられ、養護施設を経て、やがて感化院に。
見かねた米子市の叔母が引き取ってくれたが、ほどなく飛び出した。職安で求人票を見ては大企業の試験を受けに行き、当時としては破格の弁当代1000円をもらっては、糊口を凌いだ。最後は、ヤクザの世界にも足を入れかけた。「かっこいい裕次郎の世界とは全然違う」と思って、東京へ戻る決心をする。
東京へ戻って、森永牛乳の販売店、裕次郎が常務だった四谷のステーキレストラン、歌舞伎座の軽食堂など、職場を転々と変えた。その間に、映像作家になりたいという夢が明確になっていたが、映像作家の道は容易ではなかった。
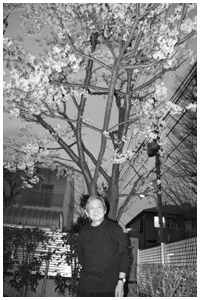
桜の樹の下に立つ。
タバコを口に得意のポーズで
自分で映像を作るしかない。そう考えたかわなかさんは、当時人気があった「小型映画」という雑誌を参考書にして、8ミリカメラで映像を撮り始めた。自ら「実験映画」と称して、閉店後の喫茶店で作品の上映会を催した。映像作家かわなかのぶひろの誕生であった。しかし、実験映画で生計が立つはずはない。浅草6区のトキワ座とロキシーの間にあったカレースタンドで、美味しいカレー作りに精を出したこともあった。
映像作家としての人生が開け始めたのは、1970年前後からだった。個人映画の制作者組織を設立したり、「アンダーグラウンド・センター」を立ち上げて個人映画の上映活動を行ったりして、実験映画のオルガナイザーとして活躍、映像作家としての地位を不動のものにしていった。
その後、東京造形大学に招かれて教壇に立つまでになった。この一筋縄ではいかない苦難の人生を歩いてきたからこそ、がんに対して突き抜けた態度が取れたのであろう。
長時間に及ぶ取材を終えて玄関を出ると、いつしか夕暮れが迫っていた。その薄暮れの中、重そうな花を満開に咲かせた1本の若い桜の樹が、庭の片隅で存在感を主張していた。「この下には亡くなったうちの猫が埋まっています」と言いながら、かわなかさんは満開の桜の下にすっくと立った。その様子は「ねがわくば花の下にて春死なんそのきさらぎの望月のころ」と詠んだ西行法師もかくや、と思わせるものがあった――。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


