「そんな軽い命なら私にください」と訴えながら命の尊さを説く 「余命1年半」を宣告されてから始めた「いのちの授業」
退院し元の生活に戻るが再発で余命1年半を宣告
すい臓がんの手術にともなう最初の入院は、3カ月、90日間に及んだ。その間、渡部さんが入院した当時の同室メンバーは、スーさんをはじめ全員亡くなった。
渡部さんは退院後、生きていることに喜びを感じながら、生きたくても生きられなかったスーさんたちの分まで一生懸命生きようと、毎日散歩をし、リハビリに通った。
そんなある日、散歩の途中、近所の公園で満開の桜を見た。仰ぎ見ると、桜の花びらの向こうに、透けるように青空が広がっていた。毎年眺めてきた桜であったが、その美しさが格別であった。今まで見てきたどんな桜よりも美しく、特別な桜に映った。
そのとき渡部さんは、「幸せはなるものではなく、感じるものだったんだ」と悟った。
順調に回復した渡部さんは、退院してから半年後には仕事に復帰し、ブランクを取り戻すかのように、懸命に働き始めた。
婦人服加工の仕事はもちろん、放課後や土曜日に小学校の校庭や体育館で子どもたちが遊んだり、学習したりする、江戸川区の「すくすくスクール」事業のクラブマネージャーになるなど、ボランティア活動にも専心した。
渡部さんは以前から、地域の少年野球の代表や、子供会の会長を務めたり、PTAの役員や江戸川区の青少年委員を務めるなど、青少年教育に関わるボランティア活動には熱心な人として知られていた。社会奉仕に対するエネルギーも復活して、渡部さんの生活は完全に元に戻ったかに見えた。
しかし、渡部さんの身体に残っていたがん細胞が、渡部さんの身体を容赦なくむしばんでいたのである。
すい臓がんの手術から2年半経った平成17年5月、渡部さんは手術を受けた病院から国立がん研究センターを紹介してもらい、検査を受けた。担当医師から非情な検査結果が告げられた。
「落ち着いて聞いてください。すい臓がんの手術は成功しています。しかし、その前に目に見えないがん細胞が身体じゅうに回り、肺に転移して、2センチの転移性肺がんになっています。もう身体じゅうにがんが回っており、手術をしても体力を落とすだけです」
医師は渡部さんが選択すべき2つの道を教えた。1つは、副作用があってつらいけれども、抗がん剤を打って肺がんの進行を遅らせる。もう1つは、何の治療もせずに、好きなことをやり、痛みが出てきたり、他の場所に転移したら、緩和療法のホスピスに行く、この2つだった。
要するに、「もう治せない」という宣告であった。元気になり、日々、仕事にボランティアに励んでいる渡部さんにとって、まさに青天の霹靂とも言うべき残酷な宣告であった。
渡部さんは腹の底から絞り出すような声で聞いた。
「先生、では、このまま何も治療しなかったら、あとどれくらい生きられますか?」
医師はやや沈黙をおいて答えた。
「1年半です」
渡部さんも奥さんも、にわかには受け入れられない短い余命であった。その夜、自宅に帰って、ほとんどのどを通らない夕食を上の空で少しだけ食べた後、渡部さんは自室で奥さんと2人、朝まで泣き明かした。
新聞記事から思いついた講演「いのちの授業」

渡部さんは苦しくて、苦しくて、何もできない状態に陥った。自分自身も奥さんも、睡眠剤なくして眠れない日々が続いた。家庭の空気が日ごとに沈んでいった。渡部さんは運転中、高速道路のインターチェンジで、分岐点の壁に衝突して自殺することも、瞬間的に考えたこともあったと言う。
そんな絶望的な日々を送っていた平成17年12月15日、読売新聞夕刊の「いのち」という欄に、「『生と死を考える』授業」という記事が出た。いじめによる自殺が相次ぐ中学校や高校で、命の大切さを考える授業を行う取り組みが広まっているという、女子高生も取材に参加・協力した記事であった。渡部さんはその記事に釘付けになった。
「若い中高生たちが生と死について真剣に考えている、という記事を読み、私がお役に立てるのではないかと直感しました。今日、明日にも死のうと思っている私にも、やることがある。生きる目的はそこにある。よし、講演していこう。私はそこで、限りある余命の生き方を、はっきりと自覚しました」
渡部さんはすぐさま、江戸川区教育委員会を訪ね、その気持ちを告げた。長年、青少年教育に関するボランティア活動を続けてきた渡部さんと、教育委員会の職員は旧知の間柄であり、渡部さんの気持ちはすぐに了解された。「渡部さんが生徒たちに話したいことを、1度教育委員会で話してくれませんか」ということになった。
平成18年2月8日、江戸川区教育委員会の幹部会で、渡部さんの講演が行われた。「いのちの授業」の第1回であった。
渡部さんは、生と死は一対のものであること、人間は1人で生きているわけではなく、周りの人々に助けられて生きていること、幸せはお金や物ではなく、感じる心であること、他人にやさしく、感謝の気持ちが大切であること、努力は決してムダにならないこと、失敗は成功への足がかりであること、魂を磨くことが人生の本当の目的であることなどを、余命1年足らずの自身の境遇を加えながら、切々と説いた。
そして最後に、「どうしても1歩も前に踏み出せない」「もう、生きてはいけない」、そんな気持ちになったときには、私の言葉を思い出してほしいと言いつつ、渡部さんはありったけの力を込めて叫んだ。
「そんな軽い命なら私にください!」
第1回の「いのちの授業」は感動のうちに終わった。その話が口コミで江戸川区の校長会などに伝わり、区内の小中学校で「いのちの授業」が相次いで行われるようになった。今回の鎌田小学校での講演で73回を数える。長野県や福島県など、地方で行われたこともあったという。
「そんな軽い命なら私にください!」
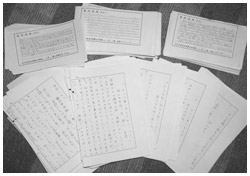
講演を聞いた子どもたちからの感想文が渡部さんの宝物
「いのちの授業」が各地で続けられるうちに、マスコミが取り上げるようになった。今年4月頃、テレビを見た大和書房の社長が訪ねてきて、単行本化を提案された。自分が本になるなど、まったく予想もしていなかった渡部さんは、一瞬とまどったが、社長の熱意に打たれ了解した。
「渡部さん、あなたが筆者ですから、あなたの条件はすべて飲みます。ただ1つ、タイトルだけは譲れません。『そんな軽い命なら私にください』、これで行きます。これは渡部さんしか言えない言葉です。この一言を聴いて、私は本を作ろうと思いました。これだけは譲れません」
『そんな軽い命なら私にください』は今年8月に出版された。渡部さんの講演「いのちの授業」のCD付きである。
渡部さんは今、まさに「余命ゼロ」の日々を送っている。取材中も咳き込んだように、決して体調は良くない。毎日、何10錠という痛み止めの薬も飲んでいる。
「こんど入院したら、もう戻ってこれない、一方通行です」と覚悟を決めている渡部さんだが、「もうそろそろマイクを使わなくてはならなくなるかも知れません」と言いながら、「いのちの授業」にかける情熱は衰えていない。
「自分の思いを子どもたちに伝えたい。きれいごとではなく、私の最後の言葉、一途な言葉を、子どもたちにわかってほしい。子どもたちの感想文を読むと、私の心が十分伝わっていることがわかり、新たな力が湧いてきます。感想文は私にとって宝物です。私は子どもたちから勇気、気力をもらって命をつないでいるようなものです」
そう言って、渡部さんは子どもたちから送られた感想文の山を見せてくれた。
1字1字ていねいに書かれた子どもたちの感想文が、神々しく輝いて見えた。
* * *
鎌田小学校での「いのちの授業」も、「そんな軽い命なら私にください!」という渡部さんの渾身の叫びで終わった。生徒たちの拍手はしばらくやまなかった。

生徒代表から花束と千羽鶴を渡され何度も「ありがとう」と言った
その後、生徒の代表から花束と千羽鶴を渡された渡部さんは、「ありがとう」「ありがとう」と言いながら、会場をあとにした。通路側の生徒の中には、「ありがとうございました」「がんばってください」と言いながら、渡部さんに握手を求める生徒もいた。渡部さんの命の叫びは、たしかに生徒たちの心に伝わっていた。
校長室に戻った渡部さんは、さすがにぐったりと椅子に座り込み、肩で大きな息をした。「素晴らしかったですね」と声を掛けると、「ともに同じ人間だという気持ちで、子どもたちに魂でぶつかっていくと、わかってくれますね。こういう話は、子供も大人もないですよ」と言って微笑んだ。
鎌田小学校の「いのちの授業」では、20~30名ほどの母親たちも参観した。帰り際、2人の母親が校長室に立ち寄り、渡部さんに直接、お礼の言葉を掛けていた。
「余命ゼロ」の渡部さんは多くの人たちに生きる力を与えている。その命が1日も長くつながることを祈らずにはいられない。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


