治療の適応と限界を知って、自分らしい生き方を選ぶ なだらかな下り坂を豊かに過ごす「がんとの共存」人生
豊かな人間関係のなかでのがん告知を選んだ
2004年秋、額田さんは腹部超音波検査で前立腺肥大を指摘された。そこで前立腺がんの腫瘍マーカーであるPSAという血液検査を受ける。検査結果の伝票には「がんの疑いがきわめて濃厚」という但し書きがつけられていた。
経験上、こういう類の但し書きがついている場合はほとんどがんであるということを、額田さんは知っている。早急に組織を採取して診断を確定しなければならない。さて、そのための針生検をどこで受ければいいだろうか……周囲の医師たちから著名な専門医を紹介しようとの申し出もあったが、悩んだ末に額田さんは、医学部時代を過ごした鹿児島へ飛ぶことにした。
鹿児島で額田さんを出迎えたのは、旧知の友、K医師たちである。そして額田さんの検査は、K医師の関係する病院で、額田さんとK医師の共通の友人である泌尿器医、T医師によって行われた。
翌々日には鹿児島の旧友たちとの宴席が設けられていた。その日、「迎えにいくから」というK医師からの電話をホテルの部屋で受けた額田さんは、しばし桜島の噴煙を窓越しに眺めて物思いにふけっていたという。
宴席に向かう車中、運転するK医師と額田さんは雑談に興じていたが、しばらくしてK医師は痺れを切らしたように「検査結果、報告していいですか?」と言った。お互いの視線があい、どちらからともなく、にやりと笑った。……そこですべての了解がついた……額田さんが受けたがんの告知はこのような風景のなかにあった。 人間的な告知というのは、案外、こういうものなのではないか、と額田さんは思う。ともに医師で友人同士である以上に、人間同士のふれあいのなかにあるもの……。
「がんと言われても、がんの闘病はそこからが長い。だから明るくさわやかにスタートさせたい。そのためには治療の水準だけを基準に東京の専門病院に行くよりは、親身になってくれる友人のところへ行こうと決めました。鹿児島にある人間関係を選んだわけです」
同年代の人たちが経験する普通のできごととしてのがん
前立腺がんは治療の選択肢が多い。額田さんは放射線治療か手術かで迷ったが、手術を選ぶ。泌尿器科医の助言や病巣把握のしやすさ、入院期間など種々の事情を勘案しての決断だった。
2005年6月、神戸市内の大病院で手術を受け、直径2.4センチと1.9センチの2つのがん病変を取り除いたが、主治医から再発の可能性を告げられている。
現在、多忙な日常のなかで、治療を継続。日常生活はそう変化していないし、生活の質も落ちていない。自分が患者として特別な体験をしている気はしないという。
「��の年代にはありがちなことです。年齢相応になったら慢性の病気は避けられない。私はがんにならなくてもほかの病気になっていたかもしれない。1つの病気としてがんがある、ということですね」
がんは年齢とともに増え(加齢が関与)、がんの発生から発見、その治療の経過には長い時間を要し(慢性)、ある臓器に発生したものが他の臓器に飛び散ることもあり、また、病の進行とともに、全身状態の悪化を招く(全身性)。そういうがんの姿を見誤ると「共存」は受け入れがたいのだという。

「日常の力が落ちていき、治療が増えていく、それがあいまって重なり収束するのが人間本来の老とか死へのプロセスです。その典型的な例ががんです。
がんは当初、生活の質を高く保つことができます。それがなだらかに下がっていき、最後にがたんと落ち込む。そのなだらかに下がっていく期間を豊かに過ごそうというのが、がんとの共存です。治すことしか眼中にないと次々と医療機関を渡り歩いて、無謀な治療で悲惨な事態になり、失うものがあまりにも多い……」
今、2人に1人ががんになる。そしてがんになって治る人が5割、あとの5割の人は治らない。
「つまり、5割の人は治らないがんと共に生きているわけです。それに積極的な意味を付与して、がんと共に生きる内容を豊かにしていきたい。『がんとどう向き合うか』はそういう文化をつくっていきましょうというメッセージです」
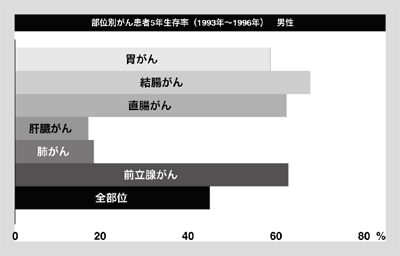
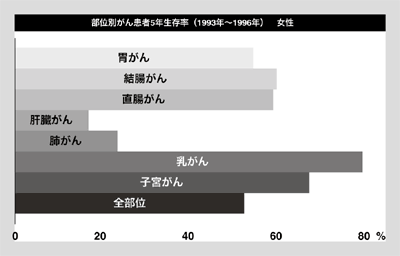
「共存」は治療の放棄ではない


講演中の額田さん
額田さんの知人Iさんは、胆管がんで、それもきわめて予後の悪いタイプだった。Iさんは実績のある東京の病院での手術を希望していた。しかし額田さんは関西に住むIさんが家族と離れてひとり東京で治療を受けることに不安を覚え、地域のがん専門の医療センターでの手術を提案した。
手術の翌年、Iさんのがんは再発。Iさんはさらなる治療へと駆り立てられていく。結果的には抗がん剤も放射線治療も効果がなく、Iさんは自宅療養に移っていった。額田さんの役目はIさん自宅・家族と、センター病院とをつなぐ接着剤のようなものだった。Iさんは最期、自宅近辺の病院に運ばれ、亡くなった。
「医学的にできることはない」と告げられたIさんに、何ができたのだろうか……当初、そう考えると無力感でいっぱいになった。
額田さんは「共存という考え方の最大の柱は、実は治療です。決して、もうすることがないから手をこまねいて死を待つのではない」と強調する。
「再発したり、転移したがん、難治性がんは治す医学からみれば『医学的にすることはありません』となります。しかし、がんが転移した人に対する治療はたくさんある。治療と平行して、自分の仕事や、やりたいことをする日常生活を維持していくのがポイントでしょう。治らないがんにどう対応するのか。それを『がんとどう向き合うか』という本のタイトルにも込めました」
がん対策基本法にみられるように、治らない患者へのケアへの関心も高まっているのが今の流れだと額田さんは実感している。患者の要求にこたえるには、専門医だけでは無理がある。がんの医療は複雑多彩。医療界が多面的、重層的に立ち向かっていかなくては……。そんな思いを強くする。
「これまでは健康な日常があるのみでしたが、そこにがんという病としての非日常が入ってきました。それで自分の日常を維持しながら治療を積極的に行なっていく。いうなれば日常の生活と、治療などがんにまつわる非日常がうまく重なっていく。イメージとしては空と海が水平線で交わるような……それが、がんと共存するということだと思います」
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


