がんとの出会い。ホスピス医ががんから学んだもの 人生は出会い。自然の摂理に身を任せて生きる
「ああ、自分の番が来たのかな」
職場検診で発見された悪性リンパ腫

淀川キリスト教病院が職員を対象に行っている胃がん検診では、全員35歳で1度受け、40歳以降は毎年胃カメラか造影剤による検査をする。実は病院の若いスタッフが胃がんで亡くなったのを機に作られた、このような周到な検診のシステムによって恒藤さんの胃にできた悪性リンパ腫は早期に発見された、といえる。
恒藤さんには若いときから空腹時におなかが痛くなり食事を摂ると治る、胃薬を飲むと大丈夫という症状があった。それを「消化性潰瘍という医者の自己診断」で放置していた。そして迎えた35歳の検診。
「潰瘍ではなさそうだからと精密検査をすることになりました。その結果、悪性リンパ腫という診断でした」 当時、淀川キリスト教病院ではがんの告知が進んでいた。その病院で働く医師である恒藤さんにも、「リンパ腫だよ」とストレートに伝えられたという。
「『え、なぜ?』とか『頭の中が真っ白』とかはなくて、『ああ、自分の番がきたのかな』と、非常に冷静に受け止められました」
ホスピスで働いて8年になっていた。その間に20代や30代の若い患者も看取った。幼い子どもがいたり、やりがいのある仕事の途中だったりという厳しいなかでも、身辺整理をし、子どもに遺言状を残す人たちの姿を見てきた。
「人には寿命があり、私たちは誰でもみんな死を迎えます。いつか自分の番がくるし、それが年の順番とは限りません。たとえ早く順番がきても、文句は言えませんからね」
そんな恒藤さんに対して、動揺したのはまわりの人たちだったという。
「私はクリスチャンなので、牧師さんには報告しておこうと、夜の8時くらいだったかな、電話をしました。すぐに駆けつけてくれました。牧師さんと奥さんが1時間もたたないうちに。スタッフたちも、えぇ~ほんとですかっ! って感じ。あと家内。当時3人の子どもが小さかったからね」
命は不可思議で、不条理で、不公平なもの……それを自分の人生として受け止めることが大切だと、恒藤さんは思う。
「生きているとはキリスト教的にいえば『生かされている』ということです。だからいかに充実させるかが重要なのであって、長さが問題ではないと考えています」
カテーテル1つでも必要最小限に


恒藤さんの家族
1995年は阪神淡路大震災が起こった年という、京阪神に住む人には忘れられない年である。恒藤さんにとっては「生まれてはじめて患者になった」ということでも忘れられない年になった。
恒藤さんの悪性リンパ腫は早期だったので手術でとれるだろうということ、リンパ腫は抗がん剤治療がけっこう有効であるということで、第1選択肢は手術。それ以外の治療については手術が終わってから考えようと思っていた。
さて、手術となると、どこで手術を受けるかを決めなければならない。これもあまり悩まなかった。自分が勤める病院でするのが、いろいろと融通が利いていいだろう……。
その読みどおり、入院期間は2週間という短期間ですんだ。術前に必要な検査などは仕事の合間に行い、入院したときにはほとんど終えていた。当初考えられていたより病巣の広がりがあり、予定より大掛かりな胃の4分の3を切り取る亜全摘手術になったが、術後の経過もよかった。
「執刀してくれた外科部長は一般の患者さんと同様に普通に接してくれました。1人の患者として接してくれたのがよかったですね。私が病院の医師だからということで特別扱いというか、腫れ物に触るような気遣いをされるとかえって居心地悪かったと思いますね」と振り返る恒藤さんだが、「でも、いざ、自分の病院の患者になると、スタッフに迷惑をかけないでおこうと思って努力しましたよ」と苦笑い。
入院中の恒藤さんを憂鬱にさせたのは、意外にも「管」であった。
「思ってもみませんでした。胃管チューブが鼻から喉に入っていると、痛いというよりしんどくてうっとうしいのですね、早くこの管を抜いて! って感じでした」
もうひとつ、膀胱カテーテルはわずか2日間だったが、あの不快感は忘れられない。
「自分が体験して、思っていたよりずっと苦痛なのだと知りました。現場では安易に管を入れがちですが、患者さんによっては亡くなるまで管を入れたままという人もいるのだし、管もできるだけやわらかくて細いものを、必要最小限にしようと思いました」
一方、新鮮な経験もあった。手術前や直後はわりとケロッとしていたものの、さすがに気が滅入って、うつうつとした気分ですごす日もあった。
そんなある日、ひとりの看護師が「いい天気ですよ! カーテン、開けますね」と言うなりさーっとカーテンを開けた。窓の外に真っ青な空が見えた。
「ぱっと目の前の霧が晴れたような気分になりました。看護師は私の気分を変えてあげようって考えてなかったと思いますよ。でもね、ちょっと視点を変えるだけで、ぜんぜん気持ちが違ってくる。なにげない1言、さりげないしぐさ1つで、ものの見方や考え方が変わる。人間って1歩自分をはなれて外に目を移すと、違った考え方や感じ方を知ることができるのだな、と、それは新鮮な経験でした」
あきらめるとはあきらかにきわめること
淀川キリスト教病院のホスピス病棟は7階にある。地元の人たちは「キリストはん(病院の愛称)の7階に行ったらあかんで」という。入院する患者さん自身「いよいよだめだな」と落胆の色を隠さない人もいる。
「『患者満足度』といわれますが、医療で患者さんが満足するのは病気が治ること。しかし治らない患者さんにとって『満足する』なんてことがあるのでしょうか。満足というより納得がいく、合点がいくということではないかと思うのです。『治らないけど、この病院で、この先生やスタッフに診てもらったら、まあ、いいかな』って思ってもらえるかどうか……」
現代医療で治らないといわれたら、藁にもすがる気持ちになる。それでも、と恒藤さんは思う。必要以上にがんばって、必要以上に執着するとうまくいかないような気がする、と。
「『あきらめ』とは『あきらかにきわめる』という仏教用語が語源だそうです。私たちの命というのは、生まれるときに生まれ、この世を去るときには去るようにできている。それにさからうより、生まれて死ぬという自然の摂理に身をゆだねるほうが、より良い生き方ではないかと思うのです」
恒藤さんはホスピスの患者が「万一、癒されたらボランティアをしたい」と言うのをよく耳にした。それを「この世はお互い様」という意識に目覚めていくようだと感じていた。「スタッフやボランティアさんと接して、今までいかに自分のことしか考えてなかったかがわかる」と語る患者たち。
配偶者をがんでなくした人が、その後、ボランティアをはじめることもある。
「今の社会では、健康で若いことが価値のある、いいことだとされています。それは病気がだめ、年をとればだめというメッセージにもなりますが、そうでしょうか? たしかに病気は避けたいけど、病気が人間的な深まりをもたらすことだってあるわけです。病気やつらいことを経験して自己中心性から解放されるのですね。難しいことですが、残される家族のためにも、最期のときをよりよく過ごしてほしいと願っています」
2001年に大阪大学大学院人間科学研究科に移るまでの14年間、淀川キリスト教病院のホスピス病棟で、多くの患者と出会い、緩和ケアを行ってきた。

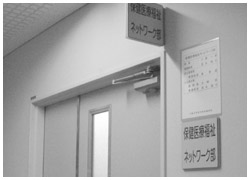
日本で初の緩和医療学の講座が開設された大阪大学
2006年10月、大阪大学大学院医学系研究科に日本で初の緩和医療学の講座が開設され、その教授に就任した。
「治療に重きがおかれる今の医療体制のなかで、治らない人に対しては必要なケアがなされていません。見捨てられたという思いや、医療不信、人間不信で最期のときを過ごす患者さんがおられます。治療と平行して治らない人にも必要かつ十分なケアが提供できるように、使命感と情熱をもって緩和ケアの啓発と普及に励みたいと思っています」
緩和ケアの普及、人材の育成のために現場から教育の場に身をおくようになったわけだ。
とはいっても、大阪大学医学部付属病院の緩和ケアチームの医師として、また他院でも診療に携わっているので臨床からまったく離れたわけではない。
「緩和ケアは新しい領域で、日本のシステムは十分ではなく、働きたいという医療従事者も多くありません。教育・研修機関が必要で、そのお役に立てたらというのがこの講座です」
最後に、逝く運命にある患者とともに歩んできた人が、日常心がけていることをたずねてみた。
「食べること、眠ることをおろそかにしない。それとお風呂に入ること」
シンプルな答えである。
「1日に3回、お風呂に入るのです。帰宅したときに1回、寝る前に1回、朝起きたときに1回、ぽちゃんとお風呂につかります」
「食べて」、「眠り」、「気持ちいい」と感じる、つまり、人間が「生かされる」基本的な欲求に忠実である、ということなのかなと思った。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


