西洋医学と東洋医学との間で絶妙な間合いをとる 管理栄養士のがん闘病の記録・円藤弘子さん
癌研付属病院に転院陳瑞東医師との出会い


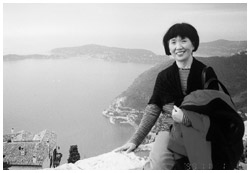
文献の乱読を通じて、円藤さんは、自分の前にさまざまな治療の可能性が開けていることを知った。当時、*癌研究会付属病院にいた陳瑞東医師のことを知ったのも、そんな折のことである。陳医師は漢方に通じたがん専門医で、東洋医学をとり入れたがん治療を実践していた。「漢方好き」の円藤さんにとって、陳医師は次第に特別な存在となっていく。
「私、昔から大好きなんですよ、自然の生薬を使った漢方が。東洋医学ということでは鍼灸も好きですね。40代前半のころ、軟式テニスで膝を脱臼して腫れ上がったときに、中国鍼をやったらあっという間に治ったことがあるんです」
それ以来、漢方や鍼灸などの東洋医学に興味を持った円藤さん。抗がん剤の治療中も、「阪神デパートの地下で漢方薬を勝手に買い、研修医と相談しながら飲んでいた」。そんな円藤さんに、陳医師の治療を受ける絶好の機会が訪れる。夫の転勤で東京・田無市に引っ越すことになったのだ。10月に東京に着くと、さっそく癌研病院を訪問。たまたま初診で陳医師と出会い、主治医になってもらえるという幸運にも恵まれた。
「どうも今までの抗がん剤が効いていないようですね。別の方法を考えましょう」
初診の2週間後、陳医師の提案で、鎖骨下静脈から携帯用ディスポーザブル注入ポンプを挿入する『バクスターインフューザー』を使った在宅化学療法を開始。ドキソルビシン、カンプトテシン、塩酸ピラルビシンなど、経口投与のエトポシドの服用で腫瘍マーカーのCA125が700台からようやく500近くまで低下した。休薬。
翌95年3月、癌研の主治医からは漢方薬を処方してもらって体調を整えながら、6月8日に骨盤内リンパ節転移の手術を受けた。主治医の陳医師を全面的に信頼していたこともあって、「手術に不安は感じなかった」と円藤さん。だが、術後の再発に不安を感じなかったといったらウソになる。そんな円藤さんにとって、心の支えとなったのは健康食品だった。手術から退院までの入院期間中、円藤さんは病室でせっせと健康食品を飲み続けたという。
「特定の宗教を信仰しているわけでもないので、精神的なよりどころを健康食品に求めていたんでしょうね。今思えば愚かしいことですが……当時は真剣でしたね」
手術後、13日目に退院。陳医師の方針で、術後の化学療法は行われなかった。
「術後に抗がん剤治療をすると、免疫力が落ちてしまいます。見える範囲のがんがなくなったら、あとは自己免疫、自然治癒力を大切にする、というのが陳先生の方針でした」
術後の治療は漢方薬中心で行われた。ふと目にした週刊誌の別冊漢方特集で、「術後のQOL向上には、化学療法よりも漢方薬が役に立つ」という記事が紹介されていた。やはり、この術後ケアは間違っていない――円藤さんは意を強くした。
実際、リンパ節切除手術と漢方薬による術後ケアの効果はあったようだ。2月下旬に770まで上がり、手術前も500台をキープしていたCA125の値が、退院2日後の6月15日には150に急降下。8月下旬には正常値の18まで低下した。円藤さんは今も、癌研病院から独立開業した陳医師のクリニックで定期検診を受けている。
「去年の11月以来行っていないので、そろそろお邪魔しないといけませんね」
そう語る円藤さんの表情には、陳医師に寄せる深い信頼がうかがわれた。
*現・癌研有明病院(東京都江東区)
食養生で自己管理
心のケアも大切だった
すべての治療から解放されてからが、平常心を保つ努力が必要になる正念場との思いが強かった円藤さんは、英国ブリストルキャンサーヘルプセンターの所属だったH・エリオット女史を講師に迎えた「ギリシャの瞑想療法」を受講。イメージしたのは米国の自然療法家アンドルー・ワイル博士。その著作にある食の考え方に強い影響を受け、今も共感を覚えているようだ。
円藤さん自身の選択での反省点は、3年は、はたまた5年目は、無事に迎えられるのだろうか……との不安感がもたらした情報選択の判断力が鈍っていたことだ。当時の代替療法の書籍やニュースレターの情報を信じて大量消費した20グラムから60グラムものサメの軟骨粉末その他健康食品の長期飲用で、多額のお金を使ってしまったことなど。円藤さんは自分で選び、「他人には決して勧めることはしてこなかったのは正解だった」と痛感している。
とはいうものの、円藤さんは健康食品を過信しているわけではない。むしろ、健康食品のがん治療効果については懐疑的だ。プロポリスにしても、抗菌作用や体調維持などの効き目はあったかもしれないが、それでがんが治ったわけではない、と円藤さんは言う。
健康食品に関しては「一石二鳥」主義

円藤さんの最近の「朝食」のメニュー
「私のがんが治ったのは、抗がん剤に反応しやすいがんであったこと、がんの悪性度が低かったこと、腹水がたまらないうちに治療を受けたこと、この3つの理由によるものだと思います。あくまで現代の西洋医学の治療効果によるもので、代替療法で治ったわけではないのです。
私は健康食品に関しては“一石二鳥主義”。たとえがんの治療に役立たなくとも、健康面でプラスアルファがあればいいという考え方なんです。キトサンなら、食物繊維として便秘解消に役立つ。サメの軟膏にはカルシウムやマグネシウム、コンドロイチン・グルコサミンが含まれているので、カルシウム補給と膝の関節をやわらかくする効果があります」
円藤さんは今も、整形外科的悩みを持っているご夫君ともどもサメ軟骨の服用を続けているという。
「サメ軟骨(カプセル入り)を20日ほど飲まないでいたら、駅の階段を上がるときに膝が痛くなってしまって……。主人が畑仕事を続けていられるのもサメ軟骨のお蔭かなあ。私のテニスのコーチも、膝の関節にはこれが一番いい、と言っていますよ」
ちなみに円藤さんは、阪大付属病院時代から6年半、自己選択で丸山ワクチンを続けている。6年目に入り、「もう必要ないのでは」という医師のアドバイスでワクチンを中止。その後しばらく白血球の数が減少し、「ワクチンは白血球の数を上げる効果があったんだなあ」と、身をもって実感したという。
とはいうものの、代替療法の妄信は危険、というのが円藤さんの持論だ。代替療法と上手につきあうポイントとして、円藤さんは次の3つを挙げた。
「現代西洋医学によるがん治療を否定する医師を選ばないこと」、「まずはがんの専門病院や大学病院を受診し、治療の最適な時期を逸することのないように気をつけること」、「代替療法の本を手に取ったらまず著者の経歴を見て、社会的に認知できるがん治療の臨床経験や研究実績がある人かどうかをチェックし、書物の信頼性を判断すること」
身銭を切って自ら代替療法を実践した円藤さんならではの、貴重なアドバイスといえよう。
一方で、円藤さんは持ち前の好奇心で闘病生活をエンジョイし、自己治癒力に磨きをかけてもいるようだ。退院後はテニスやフォークダンス、端唄踊り、墨彩画などスポーツや趣味にいそしむかたわら、海外旅行にも年に1、2回は出かけた。病院見学でパリを訪問したのを皮切りに、主にヨーロッパ方面。アジアはベトナムのみ。1度に1カ国訪問というゆとりの旅は、免疫力アップに貢献したという。
無論、余暇を楽しむばかりではない。がん体験を持つ管理栄養士として、食生活の指導や啓蒙活動に取り組んでいる。
長い闘病期間を体験した円藤さんに「生活面で気をつけるべきこと」について尋ねてみた。
「平常心を保つことに努力が必要でした。よく体を動かし、感動と笑いを積極的に求め、よく眠ること。そして、バランスのよい食事をおいしく、楽しみながら食べることですね」
では、闘病中はどのような食事を心がけたらいいのだろうか。
「魚の油に含まれるEPAやDHAには、がん抑制効果があるというデータがあります。できるだけ青背の魚を刺身で食べるか、煮魚にして煮汁ごと食べること。せっかくの有効成分が落ちてしまわないような調理法で食べるのがポイントです。その意味でも、最高なのは魚の刺身。世界中にスシ・バーがあるのもうなずけますね」
では、同じタンパク源である肉はどうなのか。円藤さんによれば、闘病中は体力勝負なので、ときには血のしたたるようなビフテキを食べることも大切だという。
「肉の摂取ががんに悪いというデータはありません。ただし、肉を食べるときは量と頻度に注意しましょう。とくに、抗がん剤治療中は、骨髄機能の維持や気分の落ち込みに有効で、消化吸収にすぐれた肉の補給をしたいものです」
また、サラダ油や紅花油、コーン油などリノール酸系の油も避けたほうがいいという。
「リノール酸系の油を使いすぎるとHDLコレステロールの値を下げてしまうので、循環器系の疾患にもつながりかねない。オレイン酸系の油も割合よいのですが、いちばんお勧めできるのはオリーブ油。なかでも一番絞りのエクストラバージン・オリーブオイルがベストです」
卵巣がんの治療を通じて、円藤さんは今ではすっかり元気を取り戻した。円藤さんの回復は、西洋医学と東洋医学との間で絶妙な間合いをとる賢明さによってもたらされたといえる。
巷では代替療法にのめり込むあまり、西洋医学を否定して治療の時機を逸する人が跡を絶たない。自然治癒力を高めるための代替療法を実践しつつも、その効果に対する冷静な目を失わない円藤さんの姿――そこには真に知性的な患者像がある、といっても過言ではない。
「私は『医者選びも寿命のうち』とよく言うんです。患者はテレビの情報など鵜呑みにせず、インターネットやがんの専門誌を読んで正しい情報を集めるべき。そして野菜や果物をたっぷり摂り、トータルバランスのいい食生活を心がける。それに尽きるのではないかと思います」
そう語る円藤さんの言葉は、がんと主体的に向き合ってきた人だけが持つ自信に満ちていた。円藤さんの探求が、いつの日か大きな実りにつながることを期待したい。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


