病気になっても、病人にならない 保健師であり、“老舗”患者会会長の長女・椚時子さんのがんとの対峙の仕方
予定を超えた「手術規模」と「入院数」
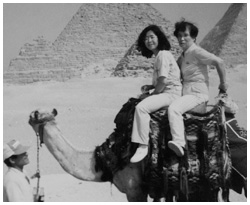
總さんが入院していた病院に、しかもその命日に入院した時子さんは、この5日後に大腸がんの摘出手術を受けた。
患部は筋腫がある子宮部分と癒着を起こしており、大腸の他にも、子宮と左の卵巣を摘出したため出血も多く、予定していたよりも大掛かりな手術になってしまった。
術後の経過は順調だった。けれども、退院を間近に控えた術後2週間目から原因不明の発熱に襲われてしまった。 時子「オペの後、普通は2週間くらいで退院するのですが、その時期に熱が出てしまったんです。発熱は10日間くらい続きました。がんで死ぬとは思わなかったのですが、なにかよくない状況に体が陥ってしまったのだという不安感がありました」
計子「娘は高熱でうなされている状態で、どうしてもよくならなかったんです。先生が『今日は最後の種類の抗生剤を使います。これが効かなかったら、無菌室に入るようになります』という説明をしたときの抗生剤が効いて、少しずつよくなっていった状態でした」
そして、入院から約1カ月後、時子さんは、ようやく退院することができたのであった。
悩まされ続けた排便のコントロール

退院から2週間ほどで、時子さんは職場に復帰した。自宅があるJR日野からJR新宿まで、電車に揺られること約1時間。まだ便のコントロールがままならない時子さんは、途中駅のトイレを使用するなどしながら、排便を処理していった。
時子「退院したときは大人用の紙おむつを使っていました。それまでは、少し水を飲んだだけで反応を起こしてしまい、多い日は20回くらいトイレに駆け込んでいるような状況でした。家で療養していたときは排便がコントロールできなかったのですが、職場に復帰すると決めた日の前日くらいから、不思議と少しずつ自分で調節ができるようになってきて、それほど頻繁にトイレに行かなくてもよくなってきました。日常生活に戻ったんです」
父親と共に登った富士山

時子さんが手術を受けた翌年、がん患者による「ガン克服日米合同富士登山2000」が行われた。その実行委員の1人であった計子さんは、入院中の時子さんに参加を勧め、申し込みをした。ただし、相当量の練習も必要で、個人的に近くの高尾山に登ったり、集団で山小屋に1泊する合同練習に参加したりもした。
たとえ練習の山行といえども、集団で山に登るということは、容易なことではなかった。とりわけ、一般参加に必要な練習日に出席できず、急遽、医療スタッフとしての参加を決めた時子さんは、登っては後続の人たちを待ち、また登り始めることを繰り返した。これでは自分のペースが掴めなかった。
富士登山の当日、時子さんは体調を万全に整え、山頂を目指した。時子さんたち医療スタッフは、500人以上の参加者が形成する長蛇の列に気を配り、体調を把握しながら頂上を目指した。
この富士登山は、集団で山に登ることの素晴らしさを教えてくれた。
時子「同じ病気をした人たちが、同じ目標に向かって励まし合いながら1歩ずつ進んでいく姿は、大きな病気を克服する患者さんのイメージに近いものがあるんです。それで、目標に到達して喜びを分かち合うことで、免疫力が湧き上がってきて、次の目標に繋がっていくんです」
時子さんは、この富士登山に、總さんがモンブランに挑んだ際に使用した登山服を身に付けていた。そして、共に登っているという気持ちで富士の山頂に登りつめたのであった。
がん体験は、保健師としての自身に生かされている

時子さんは、がん患者としての視座で「どんぐりの会」を見つめると、自分の拠り所になってくれていることに気付く。ときおり、“会長”から見せてもらう会報に目を通せば、会員たちの体験談や近況報告に自身を投影させ、勇気をもらう。病気を潜り抜けてきた人の話は、現在進行形でがんと向き合っている人にとり、計り知れない大切なものだと実感するようになった。このような会員たちの、がんになっても、いやがんになったからこそ、素晴らしい人生を送ろうとしている生き方は、もちろん時子さんのそれと共振する。
時子「それまでも毎日を楽しんでいたのですが、今は1日1日の大切さをより強く意識しています」
計子「夫のときと異なり、娘の場合は淡々とした闘病生活でした。退院してからも、驚かされるような再発・転移もありませんでしたが、がんというものを背負っています。(どんぐりの会の)会員のなかでいろいろなケースを間近に見てきましたので、不安がないわけではありません。でも、今のように前向きに生きていれば、大丈夫だと確信しています」
時子さんは、いずれはがんになるだろうと思っていた。しかし、30代で、しかも大腸がんになるとは予想だにしていなかった。がんと真正面から向き合うことになった当時は、それなりのショックを受けたのも事実である。それでも、がんになってからの日々を振り返ると、得たものも大きいと言う。
時子「私は保健師ですから、難病・不治の病を抱えた方、病気の告知を受けたばかりの方などのところにうかがうことがあるのです。そんなとき、自分の経験が生かせるんですよ。患者さんの気持ちを察することができますからね」
「父の言葉」を多くの人へ
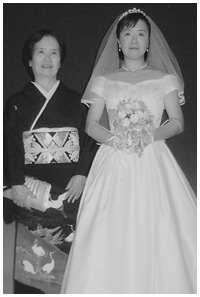
がん体験を振り返り、時子さんの胸に今、去来するのは、元気なうちにできることは、やっておこうということだ。というのは、たとえがんによる入院が決まっても、落ち込んでいるだけでなく、貪欲に興味を持ったこと、好きなことに挑戦しておこうということである。時子さんの場合、それは手術前に行った沖縄旅行である。
時子「病気になることは、たしかに不幸なことですが、それで得られることもたくさんあります。精神的に落ち込んで、暗くなっていると、余計に免疫力が下がってしまいます。だったら、できるだけ楽しいことを考えたり、笑ったりすることを心がけるようにすると、がんと闘う免疫力が出てきます。よく父が『病気になっても、病人にならない』と言っていました。その言葉は、自分が病気になって、よくわかってきました。体調が悪くなってきて再発するのかなとか、嫌なことがあってストレスがたまってきたときは、父の言葉を思い出し、こんなネガティブなことを考えていると、体の中でがん細胞が増えてきてしまうぞと思い直して、楽しいことを考えたりしています」
『病気になっても、病人にならない』――この總さんが遺していった言葉は、「どんぐりの会」の機軸となる考えの一つとなり、会員たちに通底する思いである。
「どんぐりの会」の設立に携わってきた時子さんが、計子さんとは別な形で、篤い病と対峙している人に伝えていく言葉でもある――。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


