がん体験、うつ体験から学んだ「無理をせず、休む」というゆとり 社会言語学者・佐藤優里(仮名)さん
どんどん深みに落ち込んでいくうつの恐怖
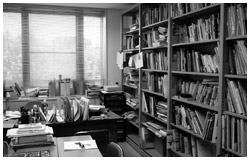

閑静な中にある佐藤さんの研究室
うつの症状が表れたのは、8月中旬に母が脳梗塞で倒れたことがきっかけだった。
「自分もがんの治療を受けながら、半身麻痺で車椅子の母の介護もしなければならない。糖尿病と白内障の持病がある父も、交代で母の世話をしているうちに、だんだんまいってきた。それでどうにも行き場がなくなり、八方ふさがりになってしまったんですね」
夫や小学6年生の息子と別居していたこともあって、佐藤さんはたった1人での闘病生活を強いられていた。それに加えて、1人っ子の佐藤さんの両肩に、両親に対する責任が重くのしかかる。実家の近くのマンションから通って介護を続けるうちに、知らず知らずのうちにプレッシャーがたまり、うつ症状となって表れてきたのだった。
人1倍前向きな佐藤さんは、それまで、うつとは無縁の人生を送ってきた。「うつで大学に来られない」という学生がいれば、「やる気がないからうつになるのよ」と叱咤するのが常だった。
「ところが、ある日突然、体が起き上がらなくなった。手を動かすのも、顔を傾けるのもいやなんですよ。すぐそばにあるテレビのリモコンに手を伸ばすことすら面倒で、食べる気もしなければ電話に出る気もしない、寝ようとしても寝られない。(どうしよう)と思っているうちに、どんどん深いところに落ちていくんです」
主治医と相談して精神科のドクターにカウンセリングを受け、抗うつ剤や軽い睡眠薬を処方してもらった。
「ドクターから言われたのは、『とにかく薬を飲んでコンコンと眠りなさい』ということ。寝ることによって、体が『ああ、私は大丈夫なんだ』と思うところまで持っていきなさい、と」
幸い18カ月の休職期間中だったこともあり、すべての仕事を休んで家にひきこもった。マンションで1人で寝ていると、天井が下がってきたり、壁が左右から迫ってくるような幻覚に襲われる。その恐怖にいたたまれず、実家に戻って休養することを決めた。
こうして2週間半ぐらい休んでいるうちに、回復のきざしが見えてきた。「不思議なもので、『ああ、私は大丈夫』と感じる瞬間が来るんですね」
05年4月、大学に復職。またバリバリ働くぞ、と意気込んだものの、いったん取りついたうつは、佐藤さんを簡単には解放してくれなかったようだ。
大学に戻った翌週の月曜1時限目の授業中、突然寒気を感じ、頭痛やめまいに襲われた。終業までの25分間はなんとか乗り切ったものの、その後、研究室までどうやってたどり着いたか全く覚えていない。 信頼できる同僚に助けを求め、そのまま帰宅。ゴールデンウィークまで休講にし、3週間を丸々寝て過ごした。大学からは休職も勧められたが、「ここで休���したら私は一生ダメになる」と思い直し、ゴールデンウィーク明けに復職。具合が悪いときは授業を代行してもらう体制を整え、現在は週6コマの授業を担当している。
誰にも病気のことをいえないのが一番つらい
こうして大学に復職した佐藤さんだが、がんであることは学長と事務局長にしか話していないという。 「『がんは死病、うつは気違いである。がん患者に重要な仕事を任せるのはやめよう』と日本人の多くは思うわけですよ。大学というところは非常にポリティカルで、人を出し抜いて出世しようと考えている人が多い。だから、がんだということを公表しないほうがいい、と諸先輩方に忠告を受けました。仮に若い研究者ががんになったとしても、それを公表する人はほとんどいない。誰にも病気のことを言えない、というのが一番つらいですね」
知性の殿堂であるはずの学界でさえ、がんに対する認識がかくも遅れているのが実態である。佐藤さんはがんの治療にあたり、ときにはアメリカの論文を調べ、ときには海外の有名な乳腺外科医にメールで相談するなどして、納得のいく治療を受けるためにあらゆる手を尽くしてきた。がん患者は自らの責任において情報を収集・吟味し、自分の病気と対峙するべき――そんな信条を持つ佐藤さんにさえ、がんの公表をためらわせてしまう。そこにこの国の病理の深さがある、といっていい。
だが、問題は当のがん患者の側にもある、と佐藤さんは指摘する。たとえば、患者同士が支えあう目的で結成された患者会にも、マイナス面が忍び込む危うさは常について回るという。
「患者会も人間の集まりだから、ときには人間関係がこじれてメーリングリスト上に中傷メールが飛び交うこともないわけではない。病院の待合室では、裏づけのない情報をもとに患者同士が盛り上がり、いつしか『この治療にはこれなのよね』という“結論”ができあがっていく。それが患者会のメーリングリストに書き込まれ、いつのまにか既定の事実として流布されていく。これはかなり危険です」
「人生において本当に大切なもの」の再発見
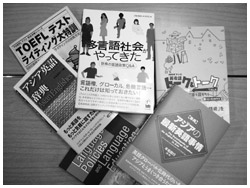
一方で、病気は佐藤さんの人生観を大きく変えたのも事実である。
「私は仕事が大好きなワーカホリックで、以前は『自分がいないと世の中はうまく動かない』と思いこんでいました。でも今回、病気で学期途中から休んだにもかかわらず、世の中すべてが丸く収まって動いている。『なあんだ、何も肩肘はってがんばる必要はなかったんだなあ』と思ったら、何か気が楽になりましたね」
また、がんになったことは、自分と周囲との関係を見直すよい機会ともなった。
「私ががんだとわかったとたんに、離れていった人たちもいた。逆に、それまで自分がけんもホロロにしていたような人たちがご飯を作ってきてくれたり、息子の面倒をみてくれたりしたんです。自分は世の中の見方を間違っていた、と大いに反省させられました」
佐藤さんにとって病気は、「人生において本当に大切なものは何か」を再発見する契機ともなったようだ。
大学で教鞭をとるかたわら、国連や外務省の同時通訳や政策提言の仕事もこなすなど、パワー全開で走り続けてきた佐藤さん。だが今は、「健康を第1のプライオリティとし、自分のペースで生きていきたい」と語る。
「今は両親とも体が弱くなり、まさに八方ふさがり状態。でも八方ふさがりだと思うと、またうつになってしまう。父は白内障の手術をすればいいし、母はリハビリをがんばればいい。私も無理なときは仕事を休めばいい、と自分に言い聞かせています。その意味では『こういうときもあるのよね』、とやっと思えるようになりましたね。それが、次のステップに進めた、ということだと思います」
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


