ブログを通じて日本版リレーフォーライフの実現をめざす 「がん患者支援プロジェクト」代表・三浦秀昭さん
リレーフォーライフとの出会い
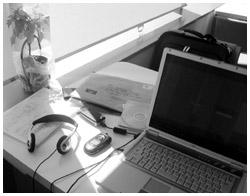
病室にパソコンを持ち込み、ブログを書き続けた
生きがいだった仕事を辞めてがんと直面する決意をした今、自分に何ができるのか――思いめぐらす三浦さんの脳裏に、がん告知直後にネット闘病記を読み漁った記憶がよみがえった。ネットで自分の闘病体験を公開すれば、同じ病に苦しむ仲間を勇気づけることができるかもしれない。三浦さんは2年間書きためた闘病記を公開することを決意。退職した翌月の2005年4月にブログを立ち上げた。
そんな三浦さんの背中を、さらに後押しするような出来事が起こる。5月に大阪で行われた『第1回がん患者大集会』に聴衆の1人として参加した三浦さんは、「3つの問題」に強い衝撃を受けた。
未承認薬、がん医療の地域格差、正しいがん情報の入手が困難であること。なかでも地域格差の問題は、さしたる自覚もないまま、首都圏で高水準の医療を享受してきた三浦さんの心を、鋭く刺した。NHKのテレビ番組でアメリカの「リレーフォーライフ」を知ったのは、そんな折のことである。日本でもリレーフォーライフが実現できないものか――それは、まさに天啓といってもいい閃きだった。
「がん患者大集会で議論されたのは、患者の力を結集して、行政や医療機関に3つの問題への対応を“お願い”するということ。それに対してリレーフォーライフは『自分たちに何ができるか』という発想なんです。我々が草の根でがんに対する意識を変えていこう、それが大きな力となれば、最終的には行政や医療を変えていける。リレーフォーライフこそまさにそのステージだ、と考えたわけです」
三浦さんはさっそくブログで日本版リレーフォーライフ実現を呼びかけた。35人が同志となり、「がん患者支援プロジェクト」を結成。集まったメンバーたちはアイデアを持ち寄り、ネット上で真剣に意見を交わした。
「ブログを拠点に、リレーフォーライフを実現しようとしている人たちがいる」
三浦さんたちの活動に注目するマスコミも出始めた。ブログやプロジェクトのことがNHKや読売新聞で紹介されると、ブログのアクセス数も1日500~600件から2000~3000件に増えた。三浦さんがたった1人で始めた活動は、次第に大きなうねりとなって広がり始める。
三浦さんにとって何より大きかったのは、心を1つにして目的を共有できるチームが、ブログ上で誕生したことだった。
「仲間と一緒にリレーフォーライフの活動をすることが、自分の残された人生には必要だと実感できる。おかげで免疫力も活性化したんじゃないかと思っているんですよ」
チームワークこそが三浦さんにとって、汲めども尽きぬ生きがいの源泉なのだ。「がん患者支援プロジェクト」の活動が、ビジネスマン時代の情熱をよみがえらせたであろうことは、想像に難くない。
脳転移が発覚

レジャーボートで妻、娘と休日を楽しむ
だが――三浦さんの病魔は、��っして追撃の手をゆるめたわけではなかった。
実はブログを立ち上げた6月、三浦さんは脳転移の告知を受けている。MRIで前頭頂葉に2センチのがんが発見されたのだ。
まさにこれから、というときに受けた、脳転移の告知。ステージも4に上がり、このときばかりは「もうだめかもと思った」と三浦さんはブログに書いている。前年に肺がんの脳転移で亡くなった叔母の記憶が脳裏に浮かんだ。死を覚悟した三浦さんに、ある脳神経外科の医師がこう語りかけた。
「今は放射線治療の技術も進歩しているので、早期がんであれば十分に治るんです。長く生きていれば、その間に新しい治療法や薬もできる。そうやって70歳になれば、三浦さんも普通の人と一緒じゃないですか。モグラ叩きかもしれないけど、一緒にがんばっていきましょうよ」
医師の言葉が、深く静かに沁みとおっていく。希望を捨てずに勇気を持って、粘って粘って生きていこう――三浦さんは、新たに浮かび上がってきた思いを、幾度もかみしめた。
7月、脳神経外科と放射線科の医師のタッグのもと、SRT放射線治療を受けた。これは、肺がん原発の脳腫瘍は中心部が壊死しているケースが多いことから、患部を16カ所に分け、SRTでがんの活性化の度合いを見ながらガンマ線を照射する治療法である。
この方法によりがんは再び寛解したが、9月からはシスプラチンとTS-1による抗がん剤治療をスタート。さらに、新横浜メディカルクリニックで免疫細胞療法も受けることにした。
実はこのとき、三浦さんは大きなブレイクスルーを経験している。いまだエビデンスが十分とはいえない免疫細胞療法を受けることについて、主治医は当然、難色を示した。だが、三浦さんは入院中の夜や朝の時間を利用して粘り強く主治医を説得。「患者中心に考え、メディカルクリニックと連携しながら治療をして欲しい」と訴え続けた。
そのかいあって、最後は主治医が教授を説得し、晴れて治療にゴーサインが出た。エビデンスを重視する大学病院としては異例のことだった。
納得のいく医療を受けるために、根気よく科や病院の異なる医師たちに働きかけ、自ら患者主体の“チーム医療”を実現してしまう三浦さん。その姿は、ブログの仲間たちにも影響を与えずにはおかなかったようだ。
「よく“2時間待ち3分診療”といいますが、先生たちは時間さえあれば話をしてくれます。医師は神様ではなく共に闘う仲間なんだと、リレーフォーライフの中でも伝えていきたい。ブログとリレーフォーライフの両輪で人々の意識を変えていけば、医療改革は進んでいくのではないかと思うんですよ。その意味では、リレーフォーライフは、患者の側から医療を変えていくための舞台装置なんです」
だが、脳転移を克服した今も、ステージは依然として4のままだ。「5年生存率13パーセント」。この数字を、三浦さんはどう感じているのだろうか。
「私は生存率を全く信じていません」と、三浦さんは断言する。
「年齢や環境、進行状況、がんの種類など、がんは患者によって全部違う。細かいレベルでエビデンスが出ていれば別ですが、今の生存率は単なる“確率”でしかない。仕事でデータ分析をしていた経験からいっても、『生存率は意味がない』というのが、私の持論なんです」
皆で一緒に歩いていこう
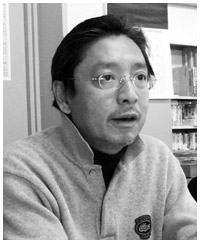
2006年2月現在、ブログの累計アクセスは23万7000件に上る。「がん患者支援プロジェクト」のメンバーも今では60名を超えた。
9月に予定される日本初のリレーフォーライフ実現に向けて、多忙な時期を過ごす三浦さん。彼がこれほどまでにリレーフォーライフに惹かれた理由は、何だったのだろうか。
「グラウンドを夜通し歩きながら、命をつないでいく、というところでしょうか。何よりチームでやる、というところがいい。その意味では駅伝と似たようなところがありましてね。『命のリレー』という名のタスキをつないでいくわけです」
大人から子供まで、サバイバーも現在戦っている人たちも健常者も、皆で一緒にがんと闘っていく。絶対あきらめない、絶対負けない。
「じゃあ、なぜ夜なのか。がんは24時間活動しているんだから、我々も24時間立ち向かって行こうじゃないかと。それが『夜通し歩く』というリレーフォーライフの精神なんです」
大人も子供も手を携え、夜明けが来ることを信じて歩き続けよう――そう呼びかける三浦さんにとって何よりも大切なものとは、共に生きる仲間たちなのだ。ビジネスマン時代に培った戦略立案のノウハウと実行力、そして仲間たちを結びつけるチームスピリット。その熱い思いは形を変えて、リレーフォーライフという新たな“プロジェクト”に注がれている。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


