悪性リンパ腫を乗り越えた「記者魂」 読売新聞西部本社法務室長・広兼英生さん
8剤併用の抗がん剤治療。強烈な副作用
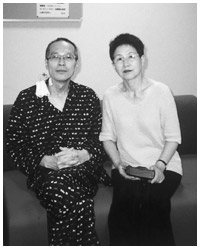
広兼さんの悪性リンパ腫は、「非ホジキンリンパ腫のMALTタイプ」で、標準治療は4種類の抗がん剤を使う「CHOP療法」という治療だ。
しかし神尾さんは、アメリカで開発された8剤を使う「多剤併用療法」で治療成績を上げており、広兼さんもこちらを選択した。
「抗がん剤の治療は、突き詰めれば、がん細胞が死滅するか、本体が死滅するかの二者択一。完治の可能性があるケースでは、全滅のために効果の異なる、強烈な薬を入れたほうがいいという確信めいたものがありました」
8月30日から始めた多剤併用療法を前半の治療とすると、後半には「大量療法」が待っていた。腹腔内に広く転移した広兼さんの悪性リンパ腫は簡単には殺せない。
抗がん剤治療は越年。2002年1月29日から、通常の10倍の抗がん剤を投入する大量療法が始まった。
抗がん剤は普通、腕の静脈から点滴するが、輸液の量が多いため首の大静脈からの直接投与になる。しかも通常の量なら体内から脊髄に通じる“関門”で、毒物・抗がん剤がシャットアウトされるが、その許容量を超えていた。抗がん剤が堰を超えて脊髄経由で脳にまで達し、「猛烈に頭が痛く、苦しいんです」。
それまでの吐き気や全身脱毛、口内炎などの副作用は序の口だった。40度前後の高熱が出て、体が震え出し、歯がガタガタ鳴った。舌をかみそうになり、あわてて食いしばった。大量の汗が出て、吐いた。白血球や血小板も激減したため、やむなく血小板を輸血した。
つらい治療を「ゲリラ掃討作戦」と名づけるユーモアで克服

しかし、生死を彷徨う危機的状況の中で、不思議なことを体験した。それは「記者魂」とでも言うものだろうか。
「体力が落ちてベッドの上で苦しんでいる自分を、もう1人のほうから取材メモを取りながら冷静に観察しているんです。不思議な体験でした」
人間のもつ生命力とでも表現すべきか、死に近い状態の中、この冷静な目で「希望」を見た。
「最初にたとえば白血球が5000あるとすると、それが500~100くらいに激減します。1番底に行くと、普通はそこが最悪の状態ですよね。でも、実際は違う。ボトム(最低部)に到達した瞬間、ガバッと意欲が湧く。パッと場面が変わり、それまで無気力だったのに、とたんに医学論文が読める状態になるんです」
どん底に落ちるや否や、すでに回復基調に入っているわけだ。生死、明暗、表裏……どれも紙一重のものなのかもしれない。
そして再発防止のための最後の治療が「メソトレキセート(一般名メトトレキサート)大量療法」だ。しつこく生き残るがん細胞を、極めて高濃度の薬でたたく作戦で、地固め療法と呼ばれる。広兼さんは、独自にこう命名した。「ゲリラ掃討作戦」
このユーモアこそ、免疫力アップの原動力。広兼さんは、がん細胞というゲリラたちの一掃に成功した。
神尾さんは最後の点滴を終えた後、ぽつりと漏らした。「私の技術と知識を全部出し切った」
2月27日。すべての治療を終えた広兼さんも、家路に着く途中の街路樹をひと際まぶしく感じながら、「やるべきことは、すべてやった」と、達成感に包まれていた。
書くことが生存意義という新聞記者魂
広兼さんは確かに幸運にも恵まれたが、その言葉だけで片付けるわけにはいかない。
広兼さんの受けた多剤併用・大量療法は「信頼できる科学的根拠がない」と否定する専門家も少なくなく、国内では完全に異端の治療。しかし、広兼さんはベッドの上で医師向けの専門書や論文を読み漁って神尾さんの治療に納得し、信頼して治療に挑んだ。だからこそ、医師も生死ぎりぎりまで大量療法を行うことができたのだ。
また、つらい治療を乗り越えられたのは、家族の存在を抜きにして語れない。抗がん剤による吐き気なども、「家族と話すだけで不思議と無くなるんです」と、広兼さんはしみじみ言う。
気分がいいと「治る」と感じ、きついと一転「だめかも」と天と地を行き来。実際、「自殺」の2文字が脳裏を過ったこともある。そんなある日、見舞いに来た長男が、父にこう不満を漏らした。
「お父さんに元気がないと、お母さんが家でふさぎ込む」
闘病中の父への言葉としては少々手厳しいが、もしかすると、男同士だけに分かるエールだったのかもしれない。
「愉快にやってたほうが免疫力が高まるし、良いことはわかりきっていますが、病気になるとそれがなかなかできない。長男の一言がズシンと響いたんです。次の日から、自分でも不思議なくらい明るく振舞いました」
この精神力の強さは、抗がん剤治療の最中に家族へ「リビング・ウィル(治療方針などに対する生前の意思表示)」をしたためたことにも現れている。文面には家族に対する感謝の言葉が綴られ、自らの人生を「そこそこ納得」と表現している。
「満足とまでは行かなくても、精一杯生きてきたんだから死んでも仕方ないと自分に言い聞かせ、一生懸命、生に対する執着を振り払おうとしていたんだと今になって思うんです」
書くことで頭を整理し、書くことで自分を鼓舞していたのだ。
「苦しみの中にも何か意義を見出したい、社会の役に立ちたいというのは誰しも同じでしょう。それが僕にとっては原稿を書くという営みだったんです」
退院直後、「耐えた 生きた がん体験記者ルポ」を読売新聞紙上に連載。全10回の期間中、日増しに反響が大きくなっていった。北海道やハワイなどからも同じ病気の読者からの苦悩や激励の手紙などが届き、それが広兼さんの励みになった。
「おもしろく」生きる
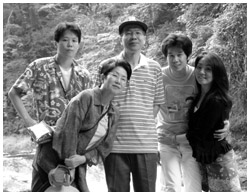
2005年夏、家族と阿蘇国立公園にある菊池渓谷へ
がんが寛解してから、もうすぐ4年。退院後にはさすがに深夜2時過ぎまでの夜勤は難しく、法務室長に転属になったが、今も毎日元気に働いている。手術前に51キロまで落ちた体重も、61キロまで戻った。
再発の危険はあるものの、くよくよ思い悩む時間は広兼さんにはない。新入社員研修のために自らの体験を語ったり、手術前には毎朝5時に起きて本を読んでいた「読書狂」にも拍車がかかった。
小説やルポはもちろん、宇宙理論や遺伝子、株の波動理論なるものまで興味は広がっている。
「株価は景気の善し悪しだけでなく人間心理の反映ですが、山口県出身の細田悟一(一目山人)という人が編み出した一目均衡表というのも興味深くて……」
ここから一気に男と女の話に話が飛んだりもする。
「なぜ男女は最初にキスをすると思いますか。遺伝子が子孫を残すため、相手に病気はないか、DNAの相性はどうかなどを判断するためでもあるんですよ」
そんな広兼さんが闘病中、いつも頭に思い浮かべていたというのが、郷土の志士・高杉晋作の辞世の句だ。
おもしろき こともなき世をおもしろく
この上の句に対し、付き添いの野村望東尼がこう続けた。
すみなすものは心なりけり
人間は気持ちの持ち方ひとつ。広兼さんの場合も、前向きに生きようとする意欲が免疫力を高め、病気の克服に役立ったのに違いない。
「生存率3割」というような過酷な現実を突きつけられたときにこそ、己の“面白き道”を進みたい。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


