氷壁に挑み続ける山男の「がん」をものともせぬ生き方 登山家・磯部道生さん
5分おきにトイレ休憩
退院した日の夜から、磯部さんは本格的なトレーニングを再開した。自宅から有馬温泉の南に位置する愛宕山山頂までの、片道40分のコースを行く。
しかし術後は下痢がひどく、5分おきにトイレに入らなければならなかった。まずコンビニや居酒屋に事情を説明して、トイレを確保することから始めた、という。片道40分といっても、ふつうの山歩きではない。実際の登山を想定した装備で歩く。約20キロのおもりで負荷をかけたリュックを背負い、重めの登山靴を履く。手袋をした両手にピッケルを持ち、手首を動かしながら歩く。氷壁を登るための訓練だ。石垣や壁を上りながら進んでいく。
トイレ休憩をする居酒屋では、トイレを借りたお礼に、焼酎を1杯頼む。それを飲み干して、また歩き始める。
「飲み屋さん5軒でトイレ借りたら、5杯飲まなあかん。ふらふらや(笑)」
そのうちに、下痢をする間隔が、5分から10分、20分と次第に開いていった。
手術の3カ月後には、磯部さんは例年通り、スキーのマスターズで、ジャイアンツスラロームという回転競技に出場した。また、同じ時期にガイド業も再開した。登山客が不安がらないよう、病気のことは内緒だ。
ただ、胃を全摘した後遺症は、あまりにも大きい。週に1度、丸1日えずく。苦い消化液が逆流してくる感じがする。調子のいい日でも、少ししか食べられない。寿司ならわずか3カンだ。宴会で料理を残すのが、申し訳なくていちばんつらい、という。情けなさを感じることも、しょっちゅうある。それでも、言ってどうなるものでもない、と割り切る。
「がん保険300万もらったら、少々しんどくても仕方がないな、という感覚や」と、笑い飛ばす。
単独登頂に成功


2004年8月、磯部さんは、ついにマッターホルンのふもとに到着した。山頂がピンと尖った美しい山は、“アルプスの女王”と呼ばれている。北壁はうっすらと雪化粧をしている。
磯部さんはまず3日間、トレーニングをかねた偵察を続けた。マッターホルンの北壁は、夏でも雪と氷に覆われている。防寒具を着る地点、アイゼンを靴につける場所など、登山のシミュレーションを繰り返した。術後は、かつての計画を変更し、北壁の前までは難易度の低いコースから登る。ペースも落とす。そして最後に、難しい北壁から山頂をめざす。
マッターホルンでも、他の登山者に気を遣われるのを恐れ、病気をひた隠した。常に登山者をリードする「山案内人」として登ってきた。その自分が、病後とはいえ、特別扱いされるのは耐えられない。また、ガイド付きで簡単に登ることなど、そもそも考えられなかった、という。万一の場合に備えて、上着のポケットに���、主治医に英語で書いてもらった病歴を潜ませた。
8月16日、ついに頂上をめざして、出発した。2日間の行程だ。体調はよくなかった。登りながらえずく。
食料は、自分でビタミン類を混ぜて団子状にしたビスケット、姫リンゴ、小さく切ったフランスパン、板チョコだ。それらをポケットに詰め込み、歩きながら少量ずつ食べる。ふつうの人ならわずか1食分ほどの量を2日間かけて食べる。満足に食べられないのに、過酷な登山をするのだ。体力は急激に消耗し、あとは気力勝負になる。
山小屋で1泊し、2日目は午前4時に出発した。マッターホルンは、日本にはない4000メートル級の山だ。しかも北海道ほどの緯度にある。ふもとでは雨が降っていたのに、山頂が近づくにつれて吹雪に変わった。磯部さんは巨大な岩壁に張りつき、わずかなとっかかりに指をかけ、上へ、上へと黙々と登っていく。この岩場で滑落し、命を落とした登山家も多い。
岩場の真ん中で、フランスのパーティ6人と一緒になった。人数が多いと登るのに時間がかかるから、「お先にどうぞ」と言ってくれる。
だが、体力の落ちた磯部さんにとって、それはありがた迷惑だ。みんなが後につづくと思うと、自分のペースを無視して一気に登らなくてはいけない。かといって、胃がないと言えば、下山を勧められるだろう。
そこで、磯部さんは覚悟を決めた。
「『俺は40歳や。君らより体力があるんや。ジャパニーズ・スピリットや!』。そう言うて、ばーっと先に登ってん(笑)」
午前10時ごろ、辺り一面真っ白に吹雪く中、ゴーグル越しに山頂の女神像の足だけが見えた。
磯部さんはそれをぎゅっと握ると、すぐに今登ってきた岩場を下り始める。ヨーロッパでは、スピードを競う、スポーツ感覚の登山が主流だ。腰を下ろして休んでいると、“遭難”と見なされ、すぐに救助用のヘリコプターが飛んでくる。ロープを投げられたらおしまいだ。
無事に下山すると、フランスのパーティから祝賀会に誘われた。難しい山を踏破したと、家族らも駆けつけて大騒ぎしている。
しかし磯部さんは誘いを断った。胃がないから、シャンパンも料理も口にできない。だからといって、胃がないことは打ち明けたくない。がん患者がひとりで登れる山だとなると、彼らの成功の値打ちを下げるような気がしたからだ。自分の部屋で焼酎をひっかけて寝てしまった、という。感慨に浸るでもなく、淡々としたものだった。
「それより、帰りの飛行機代を経費で落としたら、今年、税務署に指摘されたのが痛かった。『社長さん、これ、趣味でしょう。そんな汚いことせんとってください』て。そのほうがこたえた(笑)」
SOBE展の反響にびっくり

山を描いた自作のスケッチ画の前で語る
(有)ライチョウシステムズで
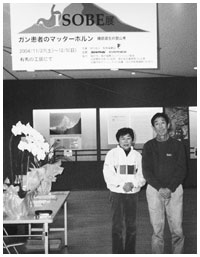
SOBE展の会場で妻・浩子さんと(2004年)
帰国後、磯部さんの成功を祝って、仲間たちが集まった。そのときに、磯部さんの登頂を写真やスケッチ画などで紹介する展覧会の企画が持ち上がる。「胃がないから、俺はそべや」という磯部さんの言葉から、「SOBE展」と名づけられた。
展覧会をきっかけに、磯部さんの快挙を知った人たちから、メッセージが届いた。
【病気と仲良くしながら、これからもがんばります。元気をありがとう】
【日々、つらいこと、しんどいことを避けているくせに、人並みの充実感を味わいたいと思っている甘さ。本当に刺激を与えていただいてありがとう】
磯部さんは反響に驚いた、という。
「がんの人には、目標や夢をしっかり持ち続けていたら、生きているうちは実現できる可能性がある、と伝えたい。どんな抗がん剤よりも、目的があるほうが上やと思う。ただ単に摂生したり、静養したりしとる人ほど、がんで死ぬで。あれ、気でいかれてまうんちゃうか」
磯部さんは、マッターホルンに登った翌年の9月には、アイガーに挑戦した。残念ながら、天候が悪くて失敗に終わった。2006年初夏には、仲間をガイドしながら、再度挑戦する予定だ。そして、同じ2006年の8月には、単独で中国のボゴダ峰(標高5445メートル)に挑む。ホテルを出てすぐに登れるヨーロッパの山と違い、ベースキャンプまで10日間かかる。その間に、食べられない磯部さんは、体力を消耗する恐れもある。かなり思い切った挑戦のようだが、彼にとっては十分到達可能な目標だ。
「来年になったら、もっと体力がつくはず。それに、次の目標を持っとかんとあかん。目標があるからこそ、トレーニングができる。次々と目標があるから、がんで悩む間がない。たとえ、みんなが10年生きるところを1年しか生きられへんとしても、中身を濃くすればええんやから」
磯部さんにとって、氷壁に挑むことこそが、「生きること」そのものなのだ。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


