大手広告会社営業部長、死の淵を潜り抜けた472日間の白血病闘病
もっとジタバタせなあかん

472日間にわたる壮絶な闘病を終えて
満面に喜びを表す吉田さん
そんな喜びも長くは続かなかった。一度は寛解した病気が、再び勢いを盛り返しつつあった。
翌年3月末、白血病が再発。2回目の寛解導入療法が始まった。1度再発してしまった以上、抗がん剤治療で寛解に持ち込んでも、また必ず再発する。したがって有効な選択肢は骨髄移植以外にない――主治医の言葉が重く胸に響いた。
(これまでの5カ月のつらい治療は一体何だったのか。自分は結局どうなってしまうのか。)
悶々とする吉田さんに喝を入れたのは、知人に紹介してもらった骨髄バンクの設立者、大谷貴子さんだった。
「あんた、自分の命がかかっているのやろ。もっともっとジタバタせなあかん」
電話口でパワフルにまくしたてる大谷さんの大阪弁に、目が覚めた。これがきっかけとなり、吉田さんは骨髄移植で実績のある病院に移ることを決意。5月下旬、本郷の東大医学部付属病院に転院した。
だが、ここでも死は追跡の手をゆるめない。
当初7名の適合者がいたはずのドナー(骨髄提供者)が、条件不適合により次々と除外され、最後に残ったひとりもDNAレベルで2タイプちがうことが判明したのだ。もしミスマッチ移植に望みを託すとしても、3年生存率は30パーセントという厳しさである。
血縁者で唯一のドナー候補者である従弟とも、血清レベルでタイプがちがうことがわかった。第3の選択肢である臍帯血移植も、発展途上の治療法ということもあって3年生存率はせいぜい2、3割程度。選択肢はひとつまたひとつと狭められ、追いつめられていく。目前に迫る死を思わずにはいられなかった。
“生命連鎖”という自然の摂理
そんな袋小路を打開してくれたのは、インターネットだった。東大病院では幸い患者のインターネット使用が許可されていた。ある日、骨髄バンクのホームページにアクセスすると、「臍帯血移植ができる病院」の名前と治療実績が掲載されていた。その中に、港区白金にある「東大医科学研究所」の名があった。
セカンドオピニオンを求めて医科研を訪ねた吉田さんは、再び転院を決める。東大病院に移ってから1カ月しか経っていないにもかかわらず――決め手は「治療成績」だった。
臍帯血移植の3年生存率が20~30パーセントといわれる中、医科研での生存率は18名中14名。この数字は驚異的だった。6月17日、医科研で臍帯血移植を受けることを決意。吉田さんはこの日を、「人生でもっとも重要な意思決定をした日」として長く記憶することになる。
もう、これでだめなら後はない――とことん追いつめられての最終選択だったが、不思議と吉田さんの心は晴れやかだった。
「それまでは毎日、迷いと不安でいっぱいでした。でも医科研への転院を決めたら、なんだかスッキリしてしまって。このときを境に、精神的な苦痛からはほとんど解放されましたね」
実を言えば、臍帯血移植を望んだ理由はもうひとつあった。
生まれたての赤ん坊の臍の緒には、無限の生命力が宿っているはず。臍帯血移植は“生命連鎖”という自然の摂理の象徴であるかに見えた。生命の神秘というものがあるならば、それに懸けてみたい――
吉田さんはそう考えたのだった。
死ぬほどの頭痛や嘔吐に耐え抜いた1カ月半

退院後、会社内で徐々に
仕事を再開し始めた吉田さん
臍帯血移植を行う前に、通常の何10倍もの抗がん剤投与と放射線治療が行われた。がん細胞を生産する自前の造血幹細胞を破壊しつくさないかぎり、移植をしても意味がないからだ。
8月12日、北海道の名も知らぬ赤ん坊から贈られた注射器2本分の臍帯血を注入し、15分ほどで移植は終了。だが、ここからが、闘病生活における最大の苦難の始まりだった。
間断なく押し寄せる頭痛、嘔吐、下痢、そして虚脱感。激しい頭痛に見舞われて失神した翌日、CTを撮ると、脳に硬膜下血腫が認められた。2度の緊急手術により最悪の事態は逃れたものの、タイミングが少しでもずれたら確実に死んでいたはずだ。まさに薄氷を踏むような状況が続いた。
嘔吐の苦しみもまた尋常ではなかった。外泊中に出かけたラーメン屋で、食事中に突然吐き気に襲われ、満員の店内で器の中に吐いてしまったこともある。
「今思えば、移植前後の1カ月半が本当につらかったですね。無菌室で死ぬほどの頭痛や嘔吐に耐えていると、精神的にも孤独で追いつめられていく。つらいときは娘や妻の顔を思い出し、自分自身を鼓舞しましたね。家族を父親なしで生活させるわけにはいかない、と」
これまでさんざん、自分のためだけに生きてきた。これからは家族のために生きよう――その一念がつらい闘病生活を支えた、といっても過言ではない。
そのかいあって、今年5月に職場復帰。今もドライマウスやドライアイ、GVHD(移植片対宿主病)による発疹は残るものの、以前に比べれば「夢のような毎日」と吉田さんは言う。「来週は1週間、ロスに海外出張に行くんですよ」と、わずかに声を弾ませた。
生かされている自分に気づいて
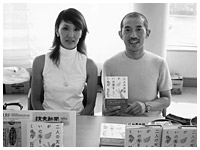
9月に横浜パシフィコで開催された
日本血液学会、日本臨床血液学会会場内で
自著の販売をする吉田さん夫妻
それにしても、吉田さんが自ら道を切り開いていく不屈のパワーには、深く感じさせられるものがあった。何度も何度も行く手をさえぎる袋小路。そのたびに、少しでも可能性のありそうな病院や治療法を調べてはセカンドオピニオンを求め、自ら突破口を開いてきた。それが“奇跡の生還”へと吉田さんを導いたといえる。
「奇跡は待っていても起こらない。奇跡を起こすためには自分の努力も必要だと思うんです。幸い今は、インターネットなどで情報が簡単に手に入る。自分の病気を客観的に知り、よい医師を探してセカンドオピニオンを求め、あらゆる手段を使って自分の病気を治す最善の治療法を選択したほうがいい。その代わり、選択の結果は自己責任。最後までジタバタして、生き残るために最善の策を自分で探すこと――それにつきますね」
もちろん、家族の支えが闘病の原動力になったことはいうまでもない。(もし独身だったら、ここまで生き伸びられただろうか)と吉田さんは、時おり自問することがある。
だが、吉田さんを支えたのは家族だけではない。入院直後は4日間で100名の知人・友人が見舞いに訪れ、「吉田さん、見舞い客数、病院新記録です」とナースにからかわれるというオマケまで付いた。社会から隔離された孤独な闘病生活のさなかに、メールで寄せられる友人たちのエールも心に沁みた。
死に至る病気を克服した今、吉田さんは大きな心境の変化を迎えている。
「僕は元々、人生にはスピリチュアルな面があると思っていたのですが、今回の闘病でそれを確信させられました。何か理由があって生かされている、という気がするんです。今度は自分が血液疾患の患者さんを励ましたり、助けてみたり。社会に貢献する生き方をするために、生かしてくれているのかなあと。それまで無茶な生活をしていた自分に、病気が気づきを与えてくれた。『残りの人生、ちがった生き方をしないとだめだよ』と教えられたような気がするんです」
これからは公私共に、血液疾患を持つ人々を助けるネットワークを作っていきたい、と吉田さん。すでに社内の有志を募り、ある構想を実現させようと動き始めたところだ。
ビジネスマンとして築いてきたキャリアや人脈と、白血病を経てつかんだ人生の目的。人智を超えた大いなるケミストリーの力が、もうすぐ大輪の花を咲かせようとしている。
「『二人の天使』がいのちをくれた」(吉田寿哉著、小学館刊、1,470円)

大手広告会社のバリバリの営業部長が、ある日突然「急性骨髄性白血病」と告げられ、頭が真っ白になったところから社会復帰するまでの472日間にわたる壮絶な闘病記。その闘病の真っ只中に生まれた子供と、臍帯血をもらった名も知らぬ赤ちゃん。その「二人の天使」が命の支えとなり、それが彼の生き方に大きな影響をもたらす。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


