がんと難病の二重苦にも負けない生き方の秘訣 ジャーナリスト・柴野徹夫さん
「書かせ屋テツ」が新聞記者に

1968年、琵琶湖にて(後ろ右から4人目が柴野さん)
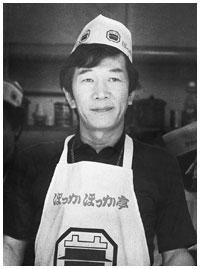
(1980年)

(1983年)
1960年当時、柴野さんは京都教職員組合で働いていた。その頃、21歳。仲間とともに季刊雑誌『ぼくらを見てくれ』を創刊した。これは、働く仲間や中卒で都会に集団就職してきた“金の卵”たちが、自分の正直な思いを文章や詩、俳句、イラスト、写真、楽譜などで表現した作品集だ。
きっかけは“金の卵”たちとの出会いだった。雑誌『週刊わかもの』の読者会で、中卒の子たちと話した。彼らが田舎で抱いていた夢、都会の工場で直面している苦労や孤独、劣等感やつらさなど、どの子の話にも涙なしには聞けないドラマがあった。
「きみの話、すごく感動した。それ、そのまま書いてみないか?」
「文章なんか、書いたことないもん……」
「いま話してくれたそのまま、その調子でいいんだ。書いてみてくれ」
彼らは表現することで、目に見えて成長していった。優れた詩人も現れた。それが楽しくて、柴野さんも編集に夢中になる。その頃ついたあだ名が「書かせ屋テツ」だ。
ある日、大先輩の詩人が、彼に言った。
「きみ自身が自分を書かなきゃ! それでも書けなきゃ、恥をかけ!」
編集にやりがいを感じつつも、内心、悔しかった。1973年、35歳で「しんぶん赤旗」の入社試験を受け、ジャーナリストになった。「政治的な理由で原稿をボツにしたりしないだろう新聞社を選んだ」という。
記者時代、一貫して力を入れたのが弱者の実情描写と原発の取材だった。“原発ジプシー”と呼ばれる危険な仕事に従事する日雇い労働者の存在や、敦賀原発の事故隠し、原発に巣くうヤクザの実態、札束攻勢に心を荒廃させる住民の姿などをスクープした。尾行されたり、ヤクザに脅されたりしながらの取材だ。
心を許しあえる仲間になると、電力会社の下請け労働者たちは危険をおかしてまでも内部資料を提供してくれた、という。
それに対し、柴野さんは彼らを守る報道を貫いた。また原発下請労組の結成を説き、知恵と力を注いで奔走した。この一連の取材と報道で、1981年度日本ジャーナリスト会議奨励���を受賞した。ルポ『原発のある風景』(上下巻、未来社)が、その仕事だ。
1987年、50歳を機に、フリージャーナリストになった。収入面で不安があったが、妻で看護師の宮内美沙子さんが快く応援してくれた。エッセイストでもある宮内さんには、『看護病棟日記』『ナースキャップは「ききみみずきん」』(未来社)『患者に学ぶ』(岩波書店)など、多数の著書がある。
幼い子どもを抱え過酷な夜勤にあえいでいた妻に、当事者の立場から看護の実態を書くことを勧めたのは、じつは新聞記者時代の「書かせ屋テツ」だ。その日暮らしではなく、看護婦や医療がどうあるべきか、自問自答する姿勢を妻に求めたのだ。
胃がんで再び「書かせ屋テツ」に
1995年8月、59歳。軽い気持ちで受けた人間ドックで、胃がんが発見された。
(うっそォ……。突然すぎる。困ったな……)
うろたえた。長男はまだ大学1年生。学資も必要だ。組織検査の結果が出るまでの数日、病状がつかめないことが辛かった。「もし残り時間が、数カ月だったら……」。どうしても最悪の場合を考えてしまう。家族に何をしてやれるか。友人・知人のためにやっておくべきことは。何を優先するか。
だが、どうにも思考がまとまらない。頭の中に靄がかかって、いつものように整理できない。自分が何10年もかけてやってきたことのまとめ、やり残している仕事、ぜひやりたかったことなどの優先順位がつけられないのだ。そんなイライラ感が、寝ても覚めても続く……。
「時間というものと生命の意味を、あのとき初めて真剣に考えました」
数日後、精密検査の結果が出た。
「進行性胃がんです。転移の有無は切開しないとわからない。できれば即刻、遅くとも1カ月以内に手術を」と言われた。
科学的に病状をつかめたら、もううろたえなかった。
「手術死という最悪の場合も考え、自室と書斎を整理しました。病状と治癒の可能性をできるだけ正確に掌握したくて、やたらと医学書を読み、医師にも率直に聞きました。すると、対処方法が見えてきます」
入院中の患者の多くが、がん宣告だけで打ちひしがれていた。
「俺はがんだ。もう駄目だ」と思いこみ、なんとか「健康な自分」に戻ろうと、もがき苦しんでいる姿を見た。
だが柴野さんはそうは考えない。なぜか。
「“完璧な健康状態”なんてあり得ないですよ。人はみな大なり小なり、心や体を病みながら生きている。がんになっても、寝たきりになっても、やれることはある」
病床で、自分の残り時間をどう使うべきか、考えをめぐらせた。真っ先にやりたいと思ったのは、「書かせ屋テツ」の仕事だった。ちょうどその頃、才能がありながらも、出版社に門前払いを喰わされる詩人やルポライターの作品を活字にし、世に送り出す作業を始めていたところだった。なぜ“物書き”の仕事を最優先しなかったのか?
「残り時間を自分のためだけに使うのは、もったいないですよ。自分の生きている喜びとか、存在理由とかを考えた結果です」
退院後、ジャーナリストの仕事も続けながら、「非営利・自力出版支援工房」と名づけた「山猫軒書房」を立ち上げた。これまでに12冊の書物を編集・出版している。
生きている限りはやれる
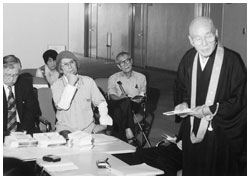
2004年7月、難病の「多発性筋炎」だと診断された。「障害者手帳第3級」を手にした。「効果的な治療法なし。2~3年後に筋萎縮で車イス生活になる」との説明を受けた。パソコンさえ打てなくなる日が、来るかもしれない。それでも、胃がんのときと同様、落ち込むことはなかった。
「自分のやりたいことさえあれば、どのような状態でも、生きてる限りはやれる」
そんな思いが彼を支えている。
精密検査のために、入院して右の太ももの筋肉を数センチ切り取った。鎮痛剤をのんでも、強い痛みは消えない。
ところが、入院中も、寝るとき以外はパジャマを着ない。車イスに座って、口笛を吹きながらノートパソコンに向かう。同室の患者たちが不思議そうに聞く。
「柴野さん、ほんとに病気なの?」
「深刻なんです(笑)」
「ニコニコしてるじゃないですか!」
じつはこのとき、柴野さんにはどうしてもやらないではおれないことがあった。
入院前、大江健三郎や加藤周一、梅原猛ら日本を代表する知識人9氏が「いま憲法が危ない」と「九条の会」を立ち上げた。第9条は、【戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認】をうたっている。それを改定しようとする動きに危機感を募らせたのだ。
その多くは記者時代にインタビューした人たちだった。政治的にも思想的にも立場の異なる人たちが「人間、文化、この国、命、世界の平和。それだけは守ろう」と結集したことに、感じるものがあった。
ところがマスコミは、この動きを黙殺して、報道しない。多くの庶民は、軍国体制に向かう現状に無関心だ。柴野さんのイライラが募る。その頃、庭の木が彼にささやいた。
(ジャーナリストだろ。あんたがやれば? 権力を正すのがジャーナリストの仕事なんだろ?)
これはどうやら、「もう1人の自分との、やむにやまれぬ対話」らしい。そこで、自分の「訴え」を書くことにした。単なる「訴え」ではない。読んだ人には、戦争や憲法、命への思いを、文章や詩、イラスト、音楽など、好きな方法で「メッセージ作品」として表現し、寄せてもらう。そんな文化的で創造的な草の根からの運動に発展させたい。作品を展示し、書物としても出版する構想だ。「現代の万葉集づくり」と名づけた。
消灯時間の過ぎた病室で、布団をかぶってパソコンのキーボードをそっと叩く。文章表現と格闘していると、筋肉を切り取った痛みも忘れることができた、という。
退院後、車イスと杖で歩けるようになると、「訴え」のたたき台を持って京都の学者や宗教者に声をかけて回った。そして9月下旬、プロジェクトが発足した。
「僕にとって戦争は、身体を張ってでも止めなきゃならない“最大の悪”です。真剣勝負」
だからと言って、彼には、必死の形相で演説し、突っ走っている感じはない。仲間たちと楽しくジョギングしている風なのだ。
「生きている間に自分の信ずることをしっかりとやること。もしぼくがその努力をしないなら、たとえ生きていても、もう死んでいるのと同じじゃないですか。それに気づかせてくれたのが、がんや難病でした。がんになって初めて『生きている意味』がはっきり見えたんだから幸せです。自分に残された時間を、誰のために、何のために使うのか? むしろ健康な人たちのほうが、それが見えないために、生きながらに死んでいるケースも多いのではないですか」
最近、庭の木がこう問いかけてきた。
(笑って死ねるかな?)
一瞬、驚きながらも、心の中でつぶやく。
(たぶんね。日本の将来は本当に心配だけど、僕としては精一杯やった。とっても楽しゅうございました、さいならーって、ね)
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


