押し寄せる苦しみの大波にも、「前進、前進」の心 看護師・鈴木厚子さん
治療の選択は生き方の選択

左横は肺がんの患者会を主宰する沖原幸江さん
2月初旬、分子標的薬イレッサの治療が始まった。1カ月入院して様子をみたところ、肺と脳の腫瘍がそれぞれ半分に縮小。イレッサが一定の効果をあげたため、退院して自宅療養に切り替えることになった。
常に明るく前向きな鈴木さんも、不安に苛まれることがなかったわけではない。薬の副作用で、ひどいニキビにも悩まされた。外出するのが億劫になった鈴木さんは、次第にパソコンの前に座ることが多くなってゆく。
そんな折、肺がん患者が主宰するインターネットのホームページに悩みを書き込んだのが縁で、鈴木さんはがんの患者会とメーリングリストに参加することになった。
「書くことや話すことって、自分の気持ちを整理するうえでとても重要なことだと思うんです。私自身、がんばろうという気持ちもあるけれど、死んじゃいたいと思う気持ちも波のようにやって来る。
でも、その気持ちを吐き出せば、少し心が整理されて、波が穏やかになってくるような気がします」
多くの患者と出会ったことは、がんとの付き合い方についての考えを深めるきっかけにもなった。
患者の中には、抗がん剤治療を続けてあきらめずに最後まで闘う人もいれば、QOLを重視して代替療法に切り替える人や、ホスピスに入る人もいる。だが、一人ひとりがどんな治療法を選ぶかは、その人の生き方に関わる問題であって、他人が口出しするべきではない、と鈴木さんは言う。
「治療の選択は生き方の選択であり、同時に死に方の選択でもあると思うんです。だから、悩んで悩んで一人ひとりが結論を出したのなら、それがベストなんだと私は思います」
死について語り合える仲
もう一つ、患者会に出てよかったと思えることがある。それは「死について語り合えること」だと、鈴木さんは言う。
がんと向き合うとき、患者はいやおうなく死と対峙することを要求される。だが今のところ、医療側のサポートが患者の精神面のケアにまで及ぶことは稀だ。のみならず、死そのものをタブー視する現代社会の風潮が、がん患者の孤独感を強めることにもつながっている。
「親しい友達にホスピスの話などをすると、『どうしてそんなことを考えるのよ』と、逆に励まされてしまうんですね。死に関する話というのは負のイメージが強いようで、周囲の人の拒絶反応が強いんです。でも、私にとって死を考えるのはとても大切なこと。だから家族にしても友人にしても、その話をしてはいけないと言われるのがすごくつらかったんです」
がんという病を患った以上、迫り来る死の問題から��をそらすことはできない。だが、伝統的な宗教や死生観を失った今の日本では、その不安を受け止めてくれる場を見つけるのは難しい。
その点、患者会なら死についてもフランクに語り合える。そういう場を得たことは、鈴木さんにとって大きな救いとなった。
以前、鈴木さんは春の新宿御苑で花見をしながら、亡くなった患者の友人と語り合ったことがある。
「死ぬときは、やっぱり苦しみたくないよねえ」
「私は眠るように死にたいなあ」
「死んでも、またどこかで会えるかなあ」
「私も次に行くから、待っててね」
まるでどこかに遊びに行く相談でもするかのように、二人は静かに語り合った。死についての思いを共有し、死を迎える予習をする。そのことで、お互いの心が癒されていくのを感じたという。
鈴木さんが死について考え始めたのは、実は発病がきっかけではない。看護師の仕事を始めた20代前半の頃、多くの人々の生死に立ち会う中で、命というものの不思議さに打たれることが多かった。
キューブラー・ロスの著書『死ぬ瞬間』や立花隆の『臨死体験』などを読んだことも、死についての関心を深めるきっかけとなった。死は生とどうちがうのか、死後の世界は果たしてあるのか。そうした興味は常に鈴木さんの心の中にあったという。
「私は、死に対する恐怖というのは孤独感から来ていると思うんです。たった1人で死んでいかなくてはいけない、その孤独感が、人間にとって一番つらいのではないでしょうか。
シェイクスピアの『ハムレット』の中にこういう台詞があるんです。『死ぬことは眠ること、眠ることは夢を見ること。どんな夢を見るのかわからないから、人は死を恐れるのだ』。
まさに死の後に何があるかわからないから、私たちは死を恐れるんですよね。それをシェイクスピアは数百年も前に言っていた。素晴らしいなあと思いますね」
シェイクスピアやチェーホフに救われた

2月にイレッサの治療が始まってから半年が経過した。8月に検査を受けたところ、一度は縮小した腫瘍が再び大きくなっていることがわかった。そこで、脳の腫瘍に対してはエックスナイフによる放射線治療を行う一方、肺の上葉を手術で切除。さらにリンパ節の郭清も行った。
その後、自宅での療養生活に入って1年が経過。昨年9月の検査では、肺の異常こそ認められなかったものの、脳の腫瘍は依然として残り、浮腫も強くなっていることがわかった。再発もしくは放射性壊死の可能性が考えられたが、その後のPET検査で、「再発とみなされる」との結果が出た。
一度エックスナイフを当てた箇所に再発したため、再び放射線治療を行うことはできない。そこで、鈴木さんは05年1月、大阪の専門病院で開頭手術を受けることを決意した。
今、鈴木さんは年明けの手術に向けて準備を整えながら、心ゆくまで年の瀬を楽しんでいる。
「手術をしたら後遺症で自由が利かなくなるだろうし、もしかすると目が見えなくなるかもしれない。だから、それまではのんびりして、したいことをしていたい。私はお芝居が大好きなので、12月は市村正親さん主演の『クリスマス・キャロル』を3回見に行く予定なんです。それから蜷川幸雄演出の『ロミオとジュリエット』も絶対はずせない、と思って」
そう語る鈴木さんの声は、少女のように弾んでいた。鈴木さんが心中どんな不安を抱えているのか、それをうかがい知ることはできない。とはいうものの、鈴木さんの言葉には一種の清々しさのようなものが感じられたのも事実である。

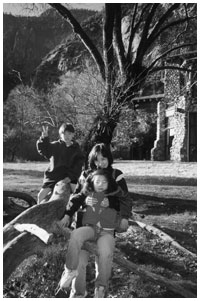
それがどこから来るものなのか。鈴木さんが悩みに悩んだ末、最終的に納得して開頭手術という選択肢を選び取ったからではないか、と私は思った。そして、これまでに築いてきた温かい人間関係が彼女の心を鎮めていることも、言葉の端々から感じられた。
たしかに家族や周囲の人たちのサポートがなければ、ここまで来ることはできなかった。なかでも医師である夫は、終始一貫して自分を支え続けてくれた。
そう言いつつも、自分を支えてくれているのはそれだけではない、と鈴木さんは言う。
「私、お芝居にもずいぶん救われている気がするんですよ」
がんの告知を受ける前に、たまたまチェーホフの『桜の園』の公演を観に行った。そのとき、劇中に登場する家庭教師トロフィーモフという人物に、鈴木さんは強い感銘を受けた。
「ロシアの貴族制度が崩壊していく荒廃した時代の中で、貧しいトロフィーモフだけが希望を捨てずに生きている。そして『前進、前進』と言って、舞台から客席に下りて走り回るシーンがあるんです。それに私はすごく感動して、同じ公演を3回見に行ったんですね。
その後、自分ががんだと知ったとき、『前進、前進』という声が頭の中で鳴り響いた。だから私、お芝居にもずいぶん助けられているんです」
この話を聞いたとき、私は鈴木さんの中で発光しているものの正体がつかめたような気がした。
それは、苦の局面にあっても人生に美を見出すことのできる、採れたての果実のようにみずみずしい心。その豊かな感受性が光源となって、彼女自身を内側から照らしている。
そして、その光が陽だまりのように自分の心までも温めていくのを、私は静かに見守っていた。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


