「いい加減な医者」はぶっつぶすつもりで活動しています 「癌と共に生きる会」会長・佐藤 均さん
策略をめぐらせる

4月中旬、5泊6日の治療を終えると、翌日からカメラマンの仕事を再開した。
仕事の合間を縫って、佐藤さんはA医師と約束した「活動」を進めていく。
4月下旬、島根医大の病院長室にカメラを持ち込んでインタビューし、「抗がん剤治療の専門医育成」の約束の言葉を引き出した。地元の大病院の院長たちに直接、「島根には抗がん剤治療の専門医がいない」ことを確認して回った。
5月下旬には、「*癌と共に生きる会」のメンバーとして、坂口力厚生労働大臣らに署名簿を添えて「抗がん剤の未承認問題の早期解決」を訴えた。これを伝える地元紙の記事は、とても奇妙なものだった。東京発の全国版記事でありながら、「出雲・佐藤さん所属の患者会12万人署名簿提出」の見出しで、その場の写真の約半分が佐藤さんで占められていた。強力に地元島根にアピールするものとして、意図されたものだったのだ。
「僕のために、写真を撮って記事にしてもらったんですよ(笑)。知り合いの記者に頼んで。ずっとこの問題はマスコミと議会にうまく働きかけないと、解決しないと思っていました。
どのように持っていったら、日本のがん治療の現状を県民に抵抗なく理解してもらえるのか。策略を練るのは嫌いなほうですが、あのときの僕は何でもやろうと思った。人の命がかかっていますから」
佐藤さんは早速、この4段抜きの記事をコピーし、島根の議会関係者らに配った。さらに有力議員に「一生に1回だけ、頼みに来ました」と協力を求めた。報道カメラマンの姿勢として、議員らと距離を置いてきた、それまでの佐藤さんらしからぬ行動だった。
議員のアドバイスで、佐藤さんは自分の思いを「抗がん剤治療専門医(腫瘍内科医)の早期育成を求める請願書」にまとめた。それを議会に提出するには、住民の署名が必要だ。佐藤さんは地元の患者仲間二人と手分けして、署名を集めることにした。
*「癌と共に生きる会」=A医師の患者・家族で作る患者会。ただしA医師とは直接関係していない独立した会である
地元のタブーを打ち破る
ところがその活動を始める寸前、仲間のうちの一人が亡くなる。彼女は佐藤さんにA医師の治療を受けるきっかけをくれた“命の恩人”で、夫と幼い子どもが遺されていた。
「弔い合戦だと思って、活動に臨みました」
請願書を読み、署名した人の多くが、その内容を「自分や家族のこと」として切実に受け止めた。署名活動があちこちに広がり、職場や飲み屋ごとに集めたものが佐藤さんの自宅に次々と届けられた。わずか3週間で2万6000人分の署名が集まった。これは出雲市の全所帯数に匹敵する数だ。
一方で、医療関係者たちは「立場があるから」と署名を断った。
「大事な命と隣合わせで闘っているはずの人たちが、協力してくれなかった。信じられません。人の命を何だと思っているのか」
佐藤さんの許せない、という思いは今も強い。
署名を添えて請願書を県議会議長らに手渡した。同時に、県には専門医養成などを国に働きかけるよう、要望した。活動を後押しする“幸運”もあった。厚労省の生活習慣病担当者が県職員に着任し、「日本のがん医療は遅れている。佐藤さんの言うことは本当です」と議員に説明してくれたのだ。A医師は週刊誌に「わざわざ島根から大金をかけ、簡単な治療を受けにくる人がいる。何で田舎でできないんだ」と書いた。
9月の定例議会で、請願書が採択された。12月には、島根医科大学が外科・内科・放射線科などを一本化した「腫瘍学教室」を開講し、付属病院に「腫瘍科」を作ることを発表した。医師の専門性と患者の利便性を高める、全国初の試みだ。 そのころ、以前の主治医に東京での治療を再度説明すると、今度は反応が違った。
「佐藤さんが受けている抗がん剤治療は、抗がん剤治療の専門医がいないとできない治療だからね」
「地元に抗がん剤治療の専門医がいない」ことは、もはやタブーではなくなっていた。
活動が実るまで死ねない
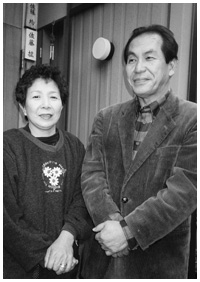
署名活動を展開していたころ、A医師が笑顔で言った。
「佐藤さん、がんばってるらしいね」
佐藤さんはそこでやっと、安心できたという。引き続きA医師による治療が受けられるのだ。
「4カ月間は針のむしろでしたから、嬉しかった。命が助かったと思った(笑)」
A医師の元でこれまでに5-FUを51.25グラム使った。島根での約4倍の量だ。8カ月間、がんの成長がストップしている。肺に多発性の転移を抱えながらも、腫瘍マーカーの値は下がったままだ。
妻の愛子さんも、安心して病気をしなくなった。夫婦で旅行を楽しむ余裕も生まれた。
治療の“条件”としての「活動」が、いつしか“生きる意味”に変わっていた。
「今は国のがん医療を変えたい一心です。実は、僕をがんにしたのも、活動させたのも、母親じゃないかと思っているんですよ」
喘息で亡くなった母は、積極的な性格だった。気性の似た佐藤さんは、「閉鎖的な島根県で活動できるのは、お前しかいない」と仕向けられたような気がしてならない、という。
「だって僕が活動しなかったら、県民はこんな実態があることを知らなかったでしょ? で、医師たちはこの事実を知っていたわけでしょう? 許せないんですよ。だから僕、活動が実るまで死ねません」
この数カ月で講演を7~8回こなした。人前で話すのが苦手だったはずが、今、人前で堂々と熱弁をふるう。「がん医療は国全体の問題」という意識から、国レベルでも活動する。
地元では患者会を主宰し、活動計画を練る。加えて、次々と舞い込むがん患者からの相談を一緒になって考える。身も心もへとへとになりながら。毎月抗がん剤治療を受けている身でありながら、なぜそこまでできるのか。
単に「うまい」治療との出合いだけではなかったろう。患者のための医療を実践する専門医の情熱に、魂を揺さぶられたからに違いない。佐藤さんの心は、ソフトな外見からは想像できないほど激しく燃えている。
「多くの医師は、自分の知識の範囲内の抗がん剤治療しかやらない。その結果、再発・再々発して亡くなっていく人がいる。ある意味では“犯罪”ですよ。そんな医療がまかり通っている。いい加減な医者はぶっつぶすつもりで僕は活動していますからね。
島根のやり方を真似て全国各地の県が動き出せば、国だって動かざるを得ない。ほかの県でもどんどんやってほしいんです」
患者が中心になって活動する、それでこそ日本のがん医療は今後、どんどん患者本位のものになっていくのではないか。
佐藤さんの情熱に接すると、そんな希望がわいてくる。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


