「ぶざまな乳がん体験」から、何かを得てほしい 漫画家・大山和栄さん
医師にクレームをつける
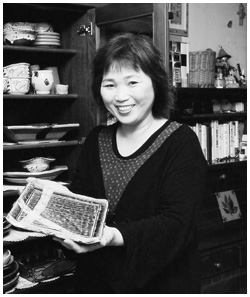
大好きな陶器に囲まれて
大山さんは「追加手術をするかどうか」という究極の選択を強いられた。
悩んだ末に、大山さんは再手術を決めた。いちばん親身になってくれているのはA医師だ、と思えたからだという。
ただ、医師たちの意見が統一されていないのは納得がいかない。そこで、A医師に「私への説明を1本化してほしい」と迫った、という。
「先生たちの間で『外来』や『入院』や『病理』など役割分担を勝手にして、別々の見解を出すとはどういうことですか? と怒りました。
それが大学病院のシステムと言われても、私たち患者には関係のないことで、『私』という患者にとっては、信頼できる『先生』はたった1人やねん。先生の言葉を頼りに私はがんばる。だからすべてA先生から説明してほしい。そして、治療の流れがわかるように、情報はすべて患者の私にもください、と言いました」
医師にクレームをつけたくても、多くの場合、患者は黙って泣き寝入りしてしまう。逆に言えば、正面切って怒りをぶつけられたA医師は、内心ビビッたに違いない。
だが、A医師は逃げなかった。これまで場数を踏んできたのだろうか。黙って大山さんの訴えに耳を傾けると、こう言った。
「すいませんでした。言ってもらって気がつくこともあります。改善するよう努力しますよ」
この言葉に、大山さんは「しょうがないなあ」と、肩の力を抜いた。心が和むのを感じていた。
追加手術の結果は、「陰性」だった。その後の抗がん剤治療は、2003年7月まで続いた。
「医師ほど信用できない人はいない」?
大山さんは乳がんのつらさを「少しずつ乳がん患者になっていき、決して『完治』しないこと」という言葉で表現する。
「実は、手術後に”本格的な治療”が始まります。乳がんであることを自覚せざるを得ない状況に持っていかれてしまう。たとえば、放射線治療の副作用はきついし、皮膚の色も変わる。ホルモン治療で生理を止めると、更年期障害が引き起こされる。抗がん剤で髪が抜けてから人に会いたくなくなったと、ウツを抱え込む患者さんがいます。患者会だけでなく、病院の中にもカウンセリングの機能がほしい。退院後も、主治医と定期的に話せれば、患者の気持ちはずいぶん楽になると思う」
大山さんのがん体験は、予備知識ゼロから出発し、いったん加速度がつくと、怒涛のように膨れ上がっていった。その濁流を全力で泳ぎ抜いてきた経験から、こうアドバイスする。
「お医者さんに頼りきるのはよくない。お医者さんほど信用できない人はいないからね(笑)。医師の間で見解が分かれることもあるから、セカンドオピニオンは必要です。私も最初は、別の医師に意見を求めたことを主治医に内緒にしていたから、えらそうなことは言えないけど(笑)。
でも自分の情報だから、自分で管理する義務も責任も権利もあると思う。情報選びは自分でやっていかなくてはいけないんですね。たとえ経験豊富な医師でも、『私のパターン』は初めてかもしれないから。
がんには不確実なことも多いから、『わからない』と言ってくれる先生のほうが正直で、信頼できますね」
大山さんは、「私のぶざまな体験から、何かを得てほしい」と、闘病記『今日と明日のはざまで』(星湖舎)を上梓している。
子どもたちに傷跡も見せた
大山さんには、3人の子どもがいる。長女の睦美さんは成人して家庭を持っているが、長男・謙太郎さんと次女・綾乃さんは、発病当時、高校生だった。
家族とは本当のことを言い合える関係でいたい。だから、大山さんは子どもたちに病気のことは包み隠さず話し、治療をめぐる悩みや身体のしんどさを打ち明けてきた。手術後の傷跡さえ、見せた。
とくに、謙太郎さんには、将来付き合う女性が同じ病気になったとしてもいたわれるようになってほしい、という願いがあった。
綾乃さんは傷跡を見て、「痛そう! かわいそう!」と顔をゆがめて、大山さんの背中をさすった。
謙太郎さんは厳しい顔でこう言った。
「痛々しいけど、これで済んでよかったよ! この傷はがんばった砦の跡や!」
「ありがとう!」
謙太郎さんの言葉に、大山さんは思わず涙ぐんだ。
実は、謙太郎さんと綾乃さんは、大山さんの病名がはっきりする前から、インターネットでがんのことを調べていた、という。入院中は兄妹で家事を分担して乗り切った。それまで家のことは大山さん任せだったことを思うと、子どもなりに母親を支えようと必死だったのだろう。
「あぁ、背中が痛い」
と大山さんがつぶやくと、
「あんだけ傷してたら、痛いやろな」
と謙太郎さんが背中をさすってくれる。
駅から家まで歩くのがつらいときには、「自転車もっていったろか?」と駅に届けてくれた。
「過去にとらわれて自分を責めたらあかん!」
と、綾乃さんが励ましてもくれたこともあった。
悲しみのお裾分け
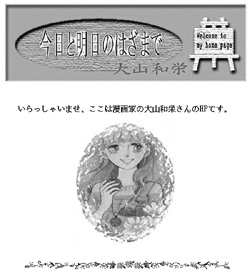
大山さんのホームページ(2003年)
がんになるまで、大山さんは子どたちと「死」について話すことなどなかった。しかしがんになったことで、人生の先を見たような気がした。
(自分がいなくなったら、この子たちは生きていけるのだろうか)
そんな切実さで、親戚の連絡先から学校のことまで、「もしも」の場合を話し合った。子どもたちに、生きていく「覚悟」と「知恵」を持たせたい、という一心だった。
ただ、思春期の子どもたちにとって、母親のがんは、やはりあまりに重すぎる現実でもあった。
放射線治療のために胸に描かれたバツ印のことを、「フランケンシュタインみたい」と冗談めかして話したときのことだ。綾乃さんのホームページの日記にはこう書かれていた。
〈なんで私に話すの? 私は何もしてやれない。私にどうしろというの!!〉
自分の病気が子どもに負担になっていると知り、悲しかった。それでも、大山さんは子どもたちを「かわいそう」だとは考えない。
「病気になるということは、分けてあげなくてもいい”悲しみのお裾分け”をまわりの人にすること。でもそれによって、うちの子は成長したと思う。自分たちの置かれた状況から逃げ出したいこともあるかもしれないけど、将来、『あのときはしんどかったけど、そのしんどさが今、こうやって活きているな』と思えることがきっとあるはず」
親子がもっとも大きな苦境に立たされたのは、追加手術における決断を迫られていた時だった。
混乱の最中、頼りにしていた夫が「離婚してくれ」と告げて、家を出て行った。大山さんと子どもたちを置いて、夫は新しい生活を選んだという。がんが影響したのかどうか、大山さんには分からない。子どもたちは自分の将来に不安を感じながらも、「生活を支えなくちゃ」と必死にアルバイトを始めた。その時、謙太郎さんは大学進学を目指す受験生だった。
嵐のような日々が過ぎてゆき、謙太郎さんは今春、大学に入学した。
一家ががんを抱えていることに変わりはない。大山さんにしても、がんのことを考えていると、心配でたまらなくなる。だからできるだけ考えないように、工夫する毎日だ。
それでも、大山さん親子の表情は明るい。「夫」との関係に区切りをつけ、「がんという病気」を丸ごと受け入れたからなのだろう。
* 大山さんは乳がんの体験をコミック誌『フォアミセス』(秋田書店)に発表している(「明日への贈り物」2003年7月号)。今後も掲載の予定。
* 大山和栄さんの公式ホームページ
夢ごもり
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


