患者と医療者が互いに興味を持てば医療現場は変わるはず 諦めずに患者の声を医療の側にフィードバックし続けたい・内田スミスあゆみさん
くも膜下出血で1カ月間昏睡
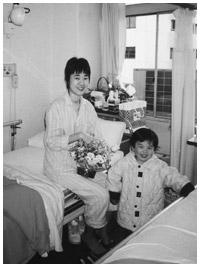
退院の日、甥っ子と一緒に
手術は成功し、その後の回復も順調だった。術後1週間目には朝食を残さずに食べ、初めて歩行訓練で病棟の廊下を1往復した。だが10月16日の午後、事態は急転する。突然激しい痛みが襲い、たちまち内田さんは呼吸困難になり、意識を失ったのである。くも膜下出血であった。
くも膜下出血から生還するには早急な手術が必要になる。けれどもこのとき内田さんは小脳血管芽腫摘出の大手術を受けてから日が浅く、とても再度の大手術に耐えられる状態ではなかった。しかし今度また動脈瘤が破裂したら死を免れることはできない。医師団はやむなくしばらく様子を見ることにしたが、動脈瘤の大きさが1センチくらいに達したところで、緊急手術を行うことにした。小脳血管芽腫の手術が終わってからまだ3週間ほどしかたっていない時期のことだ。
11月3日、手術は行われた。内田さんの意識が戻ったのはそれから約2週間後のことだ。くも膜下出血を起こしてからおよそ1カ月間、内田さんは昏々と眠り続けたのである。もちろんその間の記憶はない。手術によって聴覚神経を切断したため、内田さんは左耳の聴覚を失っていた。顔面マヒも残っていた。しかし、一命はとりとめることができたのである。
結局、内田さんが退院したのは1995年の春であった。S大学病院で水頭症の手術を受けてから約7カ月間も入院していたことになる。その間に内田さんは心身ともに深く傷ついていた。体の傷は時間とともに癒されていく。だが心の傷が癒されるまでには、それよりずっと多くの時間が必要だった。
神様がくれた鈍感さ

NPO法人「楽患ネット」主催の講演会で体験を語る
内田さんは今年の春から特定非営利活動法人(NPO法人)楽患ネットの活動に参加し、「いのちの授業」と名づけられた講演会で自らの闘病体験を人々に話している。
「やり場のない怒りを医療者に向けることは間違っていると気がついたこ���が、経験を語るきっかけになりました。医療現場でみんなが抱えている苦しみをみんながいい形で共有すれば、それぞれがもっと楽になれるのに、実際はお互いが相手のことに興味を持っていなかったり、ときには反感さえ持ったりして心を閉ざし合っているのが現状です。私のときも、私と家族と先生たちはあんなに近くにいたのに、まったくお互いの心が分かっていなかった。それがすごく寂しいのです。だから患者、家族、医療者のお互いの理解、コミュニケーションがもっと進めばいい。そのためにはまず医療者が人間としての患者に興味を持ち、その言葉に耳を傾けるようにすることが必要です。そして患者の側も、諦めずに自分たちの言いたいことや声をフィードバックしたほうがいいと思います」
入院中、医師や看護師はとても難しい症例の手術がうまくいったと言って喜んでいた。けれども内田さんはその喜びを共有する気にはなれなかった。
入院する前はひどい頭痛がしたが、自分の耳で聞き、自分の足で歩くことができた。それが手術後は頭痛はしなくなったが、左耳は聞こえず、歩くこともできなかった。治るとは、病気をする前の状態に戻ることなのではないか。これで治ったと言えるのか。そういう内田さんの思いは、医師たちの喜びとははるか遠いところにあった。
「あゆみちゃんも大変ね、あんなことになって。お嫁入り前なのにこれからどうするのかしら」
そんな身内の言葉にも内田さんの心は傷ついた。
しかし不思議なことにそうしたことをつらいとか悲しいとは感じなかった。
「そのころはいちいち悲しんでいたら、きっとリハビリなんてできなかったでしょうね。だから一種の防御反応だったのかもしれません。多分、神様が鈍感さをくれたのでしょう。でも体が元気になってきたら、あとからつらくなってきたし、今でもつらくなることがあります」
内田さんの母親は、内田さんが入院している間のことを日記につぶさに記録していた。退院後、しばらくして内田さんはその日記を読み、自分の体に何が起こったのか、どういう経緯をたどったのかをできるだけ理解しようと努めた。そしてある程度理解がまとまったとき、「急に文字にしたくなった」という。それを本の形にしたのが、『東京タワーに灯がともる』である。
分かってほしいから拒絶した
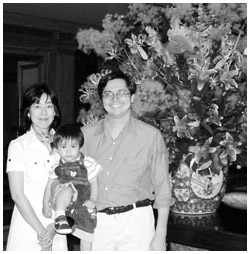
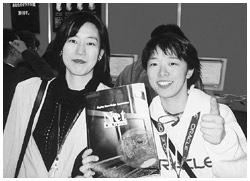
自分の闘病の記録をまとめているとき、内田さんは親しい人に対して心を閉ざしていた時期がある。神経がぴりぴりとして、刺々しい雰囲気だった。実際、この頃何人もの友人が離れていったという。
「いろいろなことで傷ついてきましたから、人が怖くなっていたのです。私の気持ちは誰にも分かってもらえないという諦めにも似た気持ちでした。でも人を拒絶していたのは、分かってほしいという気持ちの裏返しだったんですよ」
きっと著書をJ医大のA教授に送ったのも、分かってほしいという心のサインだったのだろう。そして教授が「初めて患者さんの声を聞きました」と言ったとき、きちんと伝えれば分かってもらえるということに内田さんは気がついたのではないだろうか。
その間に内田さんは、患者の家族の立場も体験している。父親を末期の肝臓がんで亡くしたのだ。このとき病院側は、抗がん剤治療をするかどうか家族に判断を求めてきた。けれども内田さんは、「家族であっても本人の痛みとか辛さを決める権利はない」と考え、医師から父親に告知してもらう道を選んだ。
「権利がないということだけでなく、私たちが父の気持ちを知らなかったから決められなかったという面もあったと思います。だから家族同士も普段からきちんと話し合っておくべきなのです。日本は病気とか死の話題を避けようとしがちですが、もうそろそろその習慣は変えたほうがいいのではないでしょうか。家族や友人との関係を豊かにするものとして、死や病についてもっと話してほしいですね」
その後、内田さんは99年にデイビッド・スミスさんと結婚し、昨年の11月には長男のマックス聴寛君を出産した。今は夫婦で会社をつくり、コンピュータ・ソフトウエアの仕事をしている。
「今は患者主体という言葉だけが一人歩きしています。でも実際は患者がすごく隅に追いやられている気がします。だから患者は自分たちこそチームの一員という意識を持って、分からないことがあれば積極的に聞き、医療側にフィードバックしてほしい。ソーシャルワーカーとか医療コーディネーターとか、最近は患者と病院の間に入ってくれる専門職も出てきています。NPOとか患者会、あるいはメディアにいうだけでも、それが医療者の目に留まるかもしれない。だからとにかく諦めずにボールを返し続けることです」
いのちの授業で自分の体験を話したあとは「いつもとても落ち込む」と内田さんは言う。話すことは、つらさや悲しさ、痛みを再現することになるからだ。そんな内田さんを見て、夫のデイビッドさんは「もうやめたら」と声をかけることがある。でも、内田さんはいのちの授業への参加を続ける。返したボールがいつかきっと医療の側から返ってくると信じて。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


