患者の心に寄り添うボランティアを医療現場に がん体験が患者を置き去りにしない医療の大切さを教えてくれた・今井俊子さん
置き去りにされる患者の辛さを実感

看護師はこんなときこそ患者を支えなくてはならないはずである。だが実際に自分が患者になってみて今井さんが感じたのは、“置き去り”にされる患者の辛さだった。
たとえばトイレにいくとき。体内に溜まっている血液や浸出液を排出するためのドレーン(誘導管)のバッグを抱えながら用を足すのは並大抵の苦労ではない。手術後間もないときは痛みが激しいので、今井さんはベッドから降りて立ち上がるだけでも5分くらいかかった。そのうえ右手はほとんど力が入らないので、狭いトイレのなかでも悪戦苦闘しなければならなかった。
だがそんなときも大半の看護師は、「痛みますか」「お薬出しましょうか」と“機械的”に声をかけるだけ。こちらがいろいろいいたいことや聞きたいことがあっても、「熱を測りましょう」「便は出ていますか」と看護師のほうで聞きたいことを優先させる。それでいて病室にきてシーツを交換するときなどは黙々と作業をすませ、終わったらさっさと出ていってしまう。なかには挨拶の言葉さえかけない看護師もいた。
一方で今井さんには病棟の看護師長をしていたときの忘れられない思い出がある。夜になるといつも廊下で一人たたずんでいた患者のことだ。以前からときどき短い言葉を交わしていたその患者を、あるとき今井さんは看護師長室に招じ入れた。けれども自分からは何もいわず、そのまま机に向かって仕事をし、患者のほうもただ黙ってそれをニコニコしながら見ているだけだった。そんなことを何度か繰り返したその患者が、「私の心のなかにずっといる」と、今井さんはいう。
「だから患者さんと話をするときは、ずかずかと相手の心のなかに入っていくまいと思っています。こちらから話しかけるより、患者さんのいうことを聞くのが基本です。それが私のやり方で、そのスタンスは今も変わっていません。でも、患者さんの立場から見ると、医療者に対してもっと近寄ってほしいという思いも抱えているんです。その思いに気がつかないと、患者さんを置き���りにしてしまいます。自分が病気を体験してからは、どうしたら患者さんの気持ちを邪魔せずに近寄れるのかということを考えるようになりました。そこががんになって一番変わったところです」
体験を生かして始めたボランティア活動
患者になってみて初めて見えてきた医療に対する不満もあった。
「一番大きかったのは、看護師などの職員が私から逃げていたことです。私は自分が教材になろうと思っていましたから、看護師に対して嫌みなこともいろいろいいました。そのせいもあったかもしれませんし、忙しすぎて雑談をしている余裕がないということもあったのでしょう。でも、検温とか配膳とか、自分たちの仕事上の必要があるときしか病室にこないし、きたときも一言も私に話しかけてこない職員が多かった。なんで部屋にきてくれないのだろう、何で声をかけてくれないのだろうと本当に思いました。そして、置き去りにされる患者さんの気持ちがよく分かりました」
手術から約3カ月後、今井さんは職場に復帰した。このときは右手を挙げることにもチョークを握って黒板に字を書くことにも、大変な努力を必要とした。ボールペンのキャップをはずすことさえできなかったのだ。それでも今井さんは教壇に立ち、看護師になるために勉強している学生たちに、自分が患者として体験したことや感じた思いを伝え続けた。黒板にきちんと字が書けるようになるまでには、約1年かかったという。
その一方で今井さんは、入院していたときの体験を何とか生かしたいと思うようになっていた。そしてそのことを相談した医師から1年後に勧められたのが、ボランティアだった。乳がん患者の病室を訪れて、同じがんの体験者として話を聞いたり相談にのったりしてほしいというのであった。
「自分ががんになったときは、叔母がいい見本になってくれました。だから今度は私が見本になろうという思いもありました。患者さんのなかには、がんだからもう死んでしまうのではないかとお先真っ暗な気持ちになっている方もいます。そういう方に対して、元気になっている私を見てもらい、あとについてきてという思いを伝えること。それに患者さんの悩みごとが自分で解決できるものであればそれを伝えることや、医師や看護師に対して聞きたいことやいいたいことがあればその仲立ちをするのが私の役割でした」
医療現場にはボランティアが必要と確信

最初は一人で活動していた。けれどもそのうち今井さんだけでは対応しきれなくなってきた。そこで立ち上げたのが乳がんの患者会「新樹の会」である。今井さんは現在もこの会の会長を務めている。
新樹の会は現在会員約110人。年2回、勉強会を兼ねた講演会を行ったり会員同士で温泉旅行にいったりしているほか、乳がん患者やその家族からの電話相談にも応じている。
そうした活動を続けるうちに、医療現場でボランティアが必要だという今井さんの思いはどんどん大きくふくらんでいった。そのため日本病院ボランティア協会の賛助会員にもなった。「終末期患者の看護」を専門とする教員として学生に教えながら、約1年間、東京・清瀬市にある救世軍清瀬病院のホスピスで毎週土曜日、研修を兼ねてボランティアをしたこともある。そして日の出ヶ丘病院と出合い、ボランティア・コーディネーターとしての道を歩むことになったのである。
「患者さんが一番気を許せるのがボランティアです。家族にもいえないことをボランティアになら話せるということもよくあります。だからホスピスに限らず医療現場にはボランティアが必要です。ボランティアは職員のすき間を埋め、職員にできないこともできます。難しいことではありません。患者さんを大事にし、暇をもてあましている患者さんや孤独や不安を抱えている患者さんに寄り添って、今日は楽しかった、ひとりぼっちではなかったと思っていただくことができればそれでいいのです。患者さんに喜んでいただけることがボランティアの喜びであり、ボランティアの喜びが私の喜びになります。患者さんのことを知らなければ注意事項などをボランティアに伝えることはできないので、私も患者さんに接することはありますが、私自身はあくまでも黒子です。それでも今は楽しくてしようがないですよ」
コーディネーターの育成とレベルアップが重要
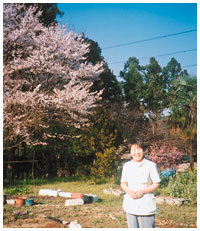

1995年の阪神・淡路大震災以来、日本でもボランティア活動をする人は確実に増えてきた。病院ボランティアも最近は珍しくなくなった。しかし今井さんは「日本の病院ボランティアの実情はまだまだ」と指摘する。
「ボランティアは職員の代わりではないというのが大前提です。しかし残念ながら日本では、ボランティアを職員がわりに使っている病院も多いですね。日の出ヶ丘病院でも最初のうちは自分たちの手足となって動いてくれるのがボランティアだと考えている職員がいて、ぎくしゃくしたことがありました。今は職員がボランティアと一緒に病院をよくしていこうという意識を持つようになったので、とてもうまくいっています。ただここの病院に限らずボランティアの人数はまだまだ不足しています。もっとボランティアを増やしていくためには、まずボランティア・コーディネーターを育成し、そのレベルアップを図っていく必要があります。そのため昨年は地域の高齢者施設などと連携してボランティア担当者会議を立ち上げました。将来、コーディネーターの養成機関ができたら、ここの病院で実習できるようにしたいですね」
がんの手術をしてから20年。今でも右腕はむくみやすい。だから疲れたときには右手を高くあげるリハビリをする。がん細胞が体のどこかにまだあるかもしれないという気持ちもずっとある。しかし今井さんは、検査で見つかったらもうけものという考え方をしている。がん細胞があるのに見つからなかったら検査した意味がないし、見つかればそれだけ早く治療できるからである。
「もともと何でもいいほうに考える性格なんです」
そういって今井さんは笑う。看護師として患者に向き合っていたときも、患者として自分のがんに向き合っていたときも、教師として学生に向き合っていたときも、この前向きの性格と明るさが今井さんを支えてきた。もちろんそれはコーディネーターとして病院ボランティアの新しい道を切り開こうとしている今も、変わらない。今井さんのようなコーディネーターが増えていけば、日本の医療現場ももっと変わっていくはずだ。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


