「尊厳ある生」こそ大切なもの 無念な思いを抱いて死んでいく人をなくしたいから、私は書き続ける・中島みちさん
「看護の日」の制定を発案し行政を動かす

ノンフィクション作家の中島さんは、本を書くだけではなく、さまざまな社会活動に直接関わることも多い。「看護の日」の制定に動いたときもそうだ。自ら「看護の日の制定を願う会」の発案・発起人となり、各方面に働きかけたのである。その結果、厚生省(現・厚生労働省)は90年、毎年5月12日を「看護の日」と制定した。
「主人は入院中に気管を切開していましたが、その切開口から痰のようなものが噴き出てくるときにはもだえ苦しみます。急いで看護師さんを呼ぶのですが、患者さんたちが不安になる深夜には他の病室でも同じように看護師さんを呼ぶ人が多く、誰もいないナースセンターでナースコールのランプは点灯しっぱなしの状態です。隣室の患者さんが、看護師も家族もいなかったほんの数分の間に血の海の中で亡くなっていたことがありました。あのバブルの時代、多くの人々が、元気なときには必要以上の便利さや贅沢を享受しているのに、死んでいくときにはこんな惨めなケアしか受けられない。看護の現場では予算がなくて、とにかく人が足りない。それなのに医師と看護師の団体が小さなパイを少しでも多く取ろうと争っているのを見て、これはいったい何なのだろうと思いました。そして看護に一般の人の目を向けてもらうにはどうすればいいかと考え、看護の日の制定を思いついたのです」
と、中島さんはいう。つまり照明さんのときの体験がきっかけになり、看護の日の制定を求める運動を始めたのである。
中島さんは医療に3度も煮え湯を飲まされている。それによってかけがえのない2人の人を失っている。自分のときも危うく手遅れになるところだった。普通ならそんな体験をすれば、医療に対し絶望的な気持ちになるのではないだろうか。少なくとも強い不信感は持つだろう。
しかし、中島さんは違った。絶望するどころか、医療現場をなんとか少しでもよくしようと看護の日の制定運動に自ら身を投じさえした。
“見えない死”を少しでも見えるように

今、中島さんはノンフィクション作家として、四つのテーマを追っている。看護問題、脳死問題、病理検査の問題、そして戦犯問題だ。
看護問題は、看護の日の制定で一定の成果をあげることができた。しかし、QOL(生活の質)を少しでもいいものにして、患者の尊厳ある生を最後の一瞬まで支えるために、そして人がその手で人の世話をするということが一番尊いのだという価値観を世の中に根づかせていくために、中島さんはこれからも看護問題を追っていくつもりだという。
脳死問題については『脳死と臓器移植法』(文春新書)などの著書でも積極的に発言してきた。病院のICU(集中治療室)に入って脳死の現場も取材した。それは照明さんが亡くなって半年ほどたったときのことだ。
「夫の死後、半年くらいは仕事に戻る気が起きませんでした。けれども誤診のこともありましたし、生前の夫に励まされたこともあったので、やはり人間の生と死に関わることを書いていかなければいけないと思ったのです。ちょうど夫の死の年に脳死移植が見切り発車したこともあり、東京と大阪の病院に頼み、脳死状態に陥った方がおられるという連絡が入るとすぐに飛んでいったりしていました」
照明さんが亡くなったとき、中島さんは号泣しながらすがりつき、遺体がだんだん冷たくなっていくのを感じていた。そしてすっかり冷たくなったとき初めて、「もうだめだ」という諦めの気持ちがわいてきたという。ICUを取材していたときには3歳児の脳死も目撃した。ピンク色をした頬を見て、「本当にここから臓器が取れるのか」と素朴な疑念を抱いた。そこを出発点として、海外取材もし、考え続けた結果、中島さんは法律で押しなべて脳死を人の死とすることには反対している。脳死は死に向かう不可逆的なプロセスではあるが、死そのものではないという考え方だ。
しかし97年に臓器移植法が制定されるときには、情報が開示され、本人の意思がはっきりしているなど一定の条件を満たした場合に限って、脳死者からの臓器提供を認めるという立場をとった。医療という密室の中での“見えない死”を、少しでも見えるようにする道筋をつけるためだった。
病理検査をしなければ確定診断はできない
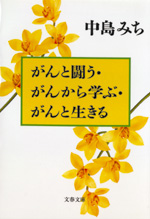
がんとがん医療をめぐる諸問題に貴重な体験から迫り、人の尊厳を追及した愛と感動の書
文春文庫 876円(税別)
3番目の病理検査についても、自分や姉のときの体験に触発されて考えるようになった問題だ。
「腫瘍を切除する前に病理検査をしていれば、姉は助かったかもしれませんし、少なくともあんな死に方はしなくてすんだはずです。がんという病気は病理検査をしなければ確定診断がつかないということを、私たちも知らなければいけないし、医師も患者にそういってほしい。もちろん病理検査をしても確定診断がつかない場合もあります。そのときは患者にはっきり、今の段階では明確には分からなかったといってほしい。そうすれば患者だって、またしばらくしたら検査を受けようという気になるでしょう。そうすることで救われる命があるのです」
この問題については、システムとして変えない限り解決できないと中島さんはいう。たとえば一定規模以上の病院は必ず病理医をおくようにするとか、病理検査なしには確定診断はつかないと医師が患者に説明するシステムをつくるというようにだ。そのために中島さんは厚生労働省にも働きかけてきたし、今は日本病理学会や病院機能評価などの活動にも加わっている。
最後の戦犯問題というのは、太平洋戦争中の行為が戦争犯罪に問われ、戦後、現地での形ばかりの一方的な裁判で処刑された、若い日本兵たちの問題だ。事実を調べれば調べるほど、なぜ彼らだけが、その一身に責任を負わされねばならなかったのか、その不条理が身に迫る。そういう状況のなかで無念の思いを抱いて死んでいった人たちがいることを、著書『日中戦争いまだ終らず――マレー虐殺の謎』のなかで中島さんは訴えている。
看護、脳死、病理検査という医療に関わる問題と戦犯問題が並んでいるのは奇異に思えるかもしれない。しかしこれら四つの問題に取り組むようになった背景には、共通の原点があると中島さんはいう。
「不条理な死をなくしたいという思いが私の原点です。もちろんそれは姉や夫、そして私自身のがん体験から抱くようになった思いです。その意味で四つのテーマはみんな同じところから始まったのです」
今日、生きている。その幸せをかみしめて

放射線障害がもとで右の鎖骨を失っただけでなく、中島さんは頸腕神経損傷、リンパ浮腫の影響で右手が不自由になっている。それでも、
「不自由で不運なところはあるかもしれませんが、不幸だと思ったことはありません。思うように動かない右手の指に念力を込めて、なんとか動くようにとリハビリもしています。今日はこれが片手でできるようになったと70歳を過ぎたのに日々目標を達成する張りがあるし、喜びがある。それはとても幸せなことですよ。それにがんをしたことであくまでもマイペース、今日も元気でお日様に会えたというだけでも嬉しい。ドン底で苦しんでいる人の気持ちも少しは理解できるようになってきたかも」
がんの病名告知に中島さんは賛成している。けれども余命告知にはケースバイケースだが慎重だ。人間というのは一片の希望さえ失ってしまったら生きていくことができない。どんなに厳しい状況でも、明日があるということが信じられれば、懸命に生きていくことができる。それが「尊厳ある生ではないか」と考えているからだ。
そういう中島さんは散々煮え湯を飲まされた医療に対して絶望せず、まだまだ希望を持っている。だから不自由な手を自分で叱咤激励しながら今日も書く。不条理な死を少しでも減らしていくために。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


