医をめぐる勉強ががんをめぐる環境を変えるかもしれない 医師と患者の架け橋として・中島陽子さん
ボランティアとして患者の話を聞く
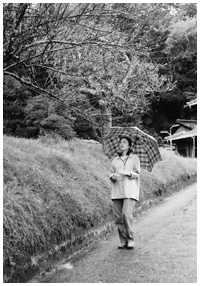
緑あふれる自宅近辺を
散策するのも日課のひとつ
「病院で心理職として何かするには認定心理士の資格が必要で、認定心理士の資格を取るには心理学実験の単位修得が必要なのです。滋賀大学での履修は半年で、放送大学は2年ちょっとで修了しました」
と、こともなげにいうが、中島さんは退院の1カ月後には病気する前に勤めていた食品会社の研究室に職場復帰している。しかも主婦業もしていたし母親でもあったのだから、この間の忙しさは並大抵ではなかったはずだ。
「その頃は土日はほとんど家にいませんでしたね。講演会だけでなく心理学学会とか乳がん学会などにも飛び回っていましたから。夫の実家に住んでいたので家事は義母が手助けしてくれましたが、夫は呆れ返っていたでしょう。ただ、私がそうしなくては生きていけないような状態で必死だったことは家族も分かっていてくれたと思います」
その間に中島さんは週1回、京都国際社会福祉センターに通い、カウンセリングの勉強もしている。この頃になると、病院で医療側と患者側の橋渡し役になりたいと、はっきり考えるようになっていたからだ。そして99年の6月から手術を受けた病院で始めたのが、乳がん患者の話を聞くボランティアである。
「乳腺外来の診察がある日に時間を決めて、『ひだまりサロン』という名で、自由にきて自由に話ができるようにしています。だいたいどの方もいうことは同じ。術後の不安と再発の不安です。私は半分心理職で半分がん体験者というスタンスで話を聞きます。とにかくまず聞くこと。本当に聞いてもらったとその方が思えるように聞くことです。術後には重いものを持たないようにといわれたけど、何キロまでなら大丈夫なのかというような、具体的な疑問には分かる範囲で答えます。でも、不安とかそういうことに対する答えは、自分のなかにしか見つけられません。だから話を聞くことが大切なのです」
医療者側の想いも知る必要がある

「医をめぐる勉強会」1周年記念講演会の様子。
勉強会には医師や看護婦など、
いろいろな立場の人が参加する。
再発の不安は中島さん自身も抱えている。時間の経過とともに切羽詰まったような不安は薄れてきたが、再発や転移がいつ見つかるか分からないという不安は常にある。病気を知ることで対応してきたが、それですっかり不安が解消できるわけはないのだ。
「完全な非浸潤がんでなければ、完治はあり得ないと思っていたほうがいいのではないですか。だから私は完治したという意識は全くありません。再発や転移の可能性は1000分の1くらいだから心配しなくてもいいという人がいますが、そういう人には、私がその1だったらどうしてくれるんだ、といいたいですね」
病院でのボランティアを続ける一方で、4年前には「風の吹く場所」という名のホームページを開設した。また、2000年の6月には、「医をめぐる勉強会」を立ち上げた。その会誌の第1号に中島さんはこう書いている。
「患者の立場でお話しする機会が増えてくると、今度は医療者の『医療、患者への想い』もまた、患者側に伝わっていないと気付かされました。お互いに『知ること』で、手を取り合い、暖かい医療を作ることはできないでしょうか。この勉強会は医療現場での双方向の理解を目指した、ささやかな取り組みです」
大津市の生涯学習センターで3カ月に1回開かれる勉強会では毎回ゲストが話をしたあと、参加者が自由に話し合う。第1回の参加者は10人ほどだったが、最近は毎回40人くらいが参加している。入会金1000円を払えば会員になることができ、会員は1回500円、非会員でも1000円払えば誰でも勉強会に参加できる(次回の開催は2004年3月の予定)。いろいろな立場の人が同じ目線で話し合える場をつくりたい、という中島さんの狙い通り、勉強会には医師や看護師なども参加している。この勉強会を始めてさすがに忙しくなりすぎ、中島さんは患者会を退会し、2年前には仕事もやめた。今はボランティアと勉強会が活動の中心だ。
気持ちの持ち方で変わることもある

自らハンドルを握り、
買い物へ、講演会へとでかける
「医療側と患者側の架け橋という役割は、勉強会でちょっとはできていると思います。これからは宗教をバックボーンにしないで、チャプレン(病院付きの牧師)のようなこともしてみたいと思っています」
という中島さんは7年前に退院したあと、副作用がひどかったので2年間の予定だった抗がん剤の服用は1年半でやめた。ホルモン剤は当初の計画通り5年間服用したが、それ以後は民間療法も含めてがん予防に関わることは何もしていない。食生活も和食中心にした程度で、とくに大きくは変えていない。薬の副作用で浮腫が出たりしたことはあったが、この7年間、健康状態は良好だ。
「変わったのは、気持ちです。病気をする前と比べると今の私は別人のようですよ。以前はまわりの人や社会がどう思うかということを優先していましたが、今はできる限り自分がしたいことをしようと思っています。もともと、人に積極的に関わろうというタイプではありませんでしたから、勉強会なんて昔の自分だったら絶対やらなかったでしょうね。気持ちの持ち方を変えたことが再発を防いだかどうかは何ともいえませんが、でも、気持ちは大事だと思います。後ろばかり見ている人は、病気に埋没してしまうところがありますからね」
がんをめぐる環境を7年前と比べると、今は患者側からの情報発信がとても多くなった。そしてそうした情報発信は医療者の側にも確実に届くようになってきた。がん患者や体験者の地道な活動が少しずつ医療のあり方を変え始めている。そんな手応えを感じているのはきっと中島さんだけではないだろう。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


