私はがんとともに生きる道を選んだ 発病から23年、病気は自分の影のようなもの・高出昌洋さん
カルテをのぞき見て知った本当の病名
高出さんが本当の病名を知ったのは、この頃であった。ある日、河野医師による診察を受けていたときのこと。何かの用があって河野医師がほんの短い間、席を外した。ふと見るとカルテが机の上に置いてある。何気なく手にとって病名の欄を見ると、「胃癌」の二文字が目に飛び込んできたのだ。
もっとも高出さんはがんだったことを知ってもたいして驚かなかったという。「ああ、やっぱり」と思った程度だったそうだ。自分でも何となくそうではないかと思っていたし、手術からすでに2年がすぎていたからだろう。
「あとで聞いたら家内は手術のときに河野先生から病名を教えられていたそうです。当時はまだ私が39歳で、二人の子供も小学校の低学年でしたから、家内はずいぶん驚いたでしょう。手術後にはどんどんやせていきましたから、不安にも思っていたでしょうね。でも、私に知られてはいけないと気を遣っていたようです。今思うと、食事などにもいろいろ気を配ってくれていましたね。私自身はがんと知ったことで不安になったとかそういうことはありませんでした。ちょっと胃が痛んだり体調が悪かったりすると、もしかしたら再発か、と思うこともありましたが、幸いそういうことが長く続くことはありませんでしたからね」
いずみの会は、例会を中心にした活動を行っている。河野医師が出席したときは、腹式呼吸やイメージ療法などについての話を聞き、河野医師が出席できないときは会員同士がお互いに病気の体験を話し合う。初めの10年間は月2回例会を開いていたが、その後は月1回になった。以前は患者や家族からの相談を電話で受ける「がん110番」や講演会などを行ったこともあるが、今は例会以外の活動を行うことはあまりない。現在の会員は約70名。例会の出席者は多いときで17、8人、少ないときは10人を切ることもある。
「もともと患者同士で励まし合うことを目的にした会ですし、河野先生はお忙しいので出席できないことも多いですから、先生なしでも動く形で20年以上続けてきました。苦労なんてとくにありませんが、毎月例会の期日を決め、会員の皆さんに案内の葉書を出さないといけません。名簿の整理などもしなくてはいけませんが、本来そういうことは苦手なほうです。でも、会の活動はもう生活の一つのリズムのようになっていますね」
患者を支えているほうも救われる

「いずみの会」で8月に淡路に日帰りで行ったときの記念写真
スタートして21年もたつと当然、この間に亡くなった会員も少なからずいる。ともに歩んできた戦友が欠けていくようで辛いが、そういうときは亡くなった会員の家族を支えないといけないし、葬式などを手伝うこともある。がんに限らず会員が病気になったときは見舞いにも行く。
「がんという辛い病気を経験した人間が、がん患者の気持ちを一番わかりますし、支えているこっちのほうがそれで救われる面もありますよ」
毎年8月は例会を行わないことになっている。しかし今年の8月は希望者を募って淡路島で温泉と食事を楽しむ日帰り旅行を実施した。がんが再発し元気をなくしている会員がいるので、その人を励ますために企画した旅行だ。
「その方は最初、いこうかどうか迷っていたようですが、参加したあとは思いきっていってよかったと、とても喜んでいました。なんだか体も元気になったみたいといっていましたよ。おかげで私たちもとても嬉しくなりました。深刻になって1人で考え込んでいたりすると余計に状態が悪くなってしまいます。逆に楽しいことをしたり考えていたりすれば体も活性化してきます。病気とは気の病と書くように、そういうことが大事なんだと思います。だから病気になっても自分だけで苦しまず、みんなで分かち合えばいいのです。私にとってはそれをできるのが、いずみの会なのです」
阪神大震災のとき、高出さんの自宅は一部損壊程度で大きな被害は免れた。だから地震が収まると、高出さんはまず担任しているクラスの生徒や卒業生の家を訪れ、被害状況や安否を確認した。大工道具を持って被災した人の家の修理をするなど、ボランティアもした。
「震災の経験のあとで神戸の人たちは本当に優しくなりました」
と、高出さんはいう。では、病気の体験は高出さんをどう変えたのか。
「無茶はできないと思うようになりました。遅くまで飲んで帰るというようなことは、全然しなくなったとはいいませんが、少なくなりました。それと家庭のこともちょっと振り返らないといけないなと思うようになりました。病気するまでは家のことは全部、妻に任せきりでしたから。子供が小さいとき放っておいてすまなかったという気持ちもありますし、家のこともせなあかんと今は思っています」
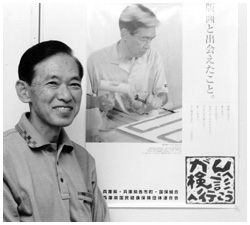
自らポスターのモデルになった高出さん。
兵庫県などががん検診の啓蒙用に作成した
アルコールは退院後、じきに再開した。ただ以前は日本酒やウイスキーを飲んでいたが、病気をしてからは焼酎のお湯割りに代えた。お湯で割ればアルコール分は薄くなるし、温かいから胃腸にもいいと考えてのことだ。今はほとんど毎日飲んでいるが、せいぜい1、2杯程度ですますようにしている。民間療法などは一切していない。
食事はもともと好き嫌いがなく何でも食べるほうだったが、病気をしてからは、体のほうが自然に受けつけるものと受けつけないものを分けるようになった。脂っこいものはあまり口にしなくなったし、肉と魚ならたいてい魚に箸がいく。以前は電車で通勤していたが、病気後は自動車通勤に代えた。そのほうが体が楽だし、おかげで帰りに一杯ということもなくなった。しばらく離れていたバスケット部の顧問には手術3年後に復帰したが、以前のように休みなしで没頭するような無茶はしなくなった。
がんの存在は自分の影のようなもの
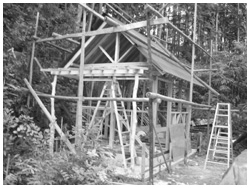
高出さんがアトリエの敷地内に自力で建設中の水車小屋
もう一つ、死や生に関する考え方も大きく変わったと高出さんは語る。
「盲腸になったこともなく、健康には自信がありましたから、それまでは死について考えること自体ほとんどありませんでした。でも病気をしたことで、人間の生や死についていろいろ考えるようになりました。人間というのは、生まれてきたらもう死に向かって歩み始めているんです。そういうことはみんなわかっているはずなのに、死に対する恐怖感を抱く。でもたかだか70年から90年も生きたら終わりなんですよ。だからその期間をどう生きるか考え、思い残すことのない充実した歩みができるように努力したほうがいいのです。単に長く生きるのではなく、毎日毎日どう喜びを見いだし感謝して生きていくかが大事なのです」
今年の春、高出さんは定年まであと数年を残して37年勤めた学校を退職した。辞めることに迷いはなかったという。病気をし、版画と出会ったことで、仕事だけではない人生、クラブ活動に打ち込むだけではない人生もあることを知ったと高出さんはいう。
「今振り返ると、病気をしなかったら経験できなかったような人生を得ることができました。版画と出会ったことでいろいろな人と知り合えたし、庭造りとかパソコンとか興味の範囲も広がりました。病気をしたから版画と出会ったのですから、病気したことはありがたいと本当にそう思います。病気も身の内とよくいいますが、がんも身の内です。私は、病気は自分の影のようなものだと思っています。光が当たると自分の影ができる。それを、この野郎と思って追いかけても逃げていくし、自分が逃げようとしてもついてくる。逃げても対決しても、生きることからかえって遠ざかってしまうのではないでしょうか。私はいずみの会を引き受けたときから、病気とともに生きる道を選んだのです」
発病からすでに23年が経過し、その間、転移も再発もしていないのだから、高出さんのがんはもはや完治したといっていいだろう。しかし高出さんは今もなおがんとともに歩み、がん体験を大切にしながら版画家として充実した人生を生きているのである。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


