「絶対泣かない」と心に誓い、膵がんと闘った1年(1)
病院を換えて検査を受ける
11月9日次女の付き添いでK医師の診察を受ける。K医師はまじめそうで温厚な感じがした。経過を説明したあとまずエコーを撮った。CT、MRIそして12月25日に胆膵EUS検査をした。これは内視鏡を使って胃の中から膵臓のエコーをとる検査だ。胃カメラと同じようにはじめに喉に麻酔薬を含む。
検査室に入るとK医師を含め3人の若い医師がいた。点滴用の針を刺す人、喉にもう1度麻酔薬を吹きかける人、体を横向きにして片手をあげる体勢をとらせる人。「寄ってたかってごめんなさい」と言いながらK医師が口にマウスをくわえさせてテープで固定する。「気分を楽にする薬をいれますからね」という声が聞こえてすぐ意識がなくなったようだ。
「小川さん、終わりましたよ」という声がして体を起こされた。気がつくと休憩室のベッドの中。心配そうな顔で次女が立っていた。自分で靴を履いたらしいがまったく覚えていない。30分以上も眠っていたとか。でもまだフラフラする。もっと簡単な検査かと思っていたが結構大変だったらしい。でも意識がないだけ胃カメラよりも楽だ。1人で大丈夫なんて言ったが、次女に付いてきてもらってよかった。
| ●単純性嚢胞 | ||
| ●仮性嚢胞 | ||
| ●腫瘍性嚢胞 | 膵管内乳頭腫瘍(分岐型) | 過形成 |
| 腺腫 | ||
| 腺がん | ||
| 粘液生産性膵腫瘍 | ||
3日後の検査説明には主人が同行してくれた。K医師は温和な顔で、図を書きながら詳しく説明してくださった。「今までの検査の結果では単なる膵嚢胞だと思われる。各種画像診断で明らかな悪性所見はないが、ただ分岐型粘液産生性膵腫瘍も完全には否定できないので、ERCPをしたほうがより確実です」ということだった。そして膵嚢胞の種類について右図のような説明をしてくださった。
ERCPについての説明はR病院と同じだったが、R病院が日帰りに対してT病院では入院して検査を行い、何事もないことを確認してから帰すということだった。それを聞き主人も納得したので検査を受けることにし、年明けの平成11年1月19日検査入院した。単なる検査だからと1人で。北病棟の内科、6人部屋だった。婦長から一通りの説明を受けた後、担当医が紹介された。研修医、担当医、主治医の3人である。しかし1万人に1人の死亡率という明日の検査もK医師がしてくださるということで不安はなかった。
検査の当日、点滴をしてストレッチャーに乗せられて検査室に向かった。「歩けるのに」と言ったら看護婦さんが「大変な検査なんだから」と言ったので急に不安になった。検査室に入るとそこはよくテレビでみる手術室のようだった。医師も6~7人いるようだ。その中にK医師の姿があった。検査だというのにまるで手術を受けるみたい。「小川さん大丈夫ですからね」と言ってくださった言葉にふっと緊張が解けた。前の検査と全く同じに「寄ってたかってごめんなさい」と言いながらK医師がマウスを固定する。「今から点滴のなかに気分を楽にする薬をいれます」と言われ、前回は知らないうちに眠ってしまったので、今度はしっかり数をかぞえた。い~ち、に~い、さ~ん、5つぐらいで意識がなくなった。
ERCP検査とは口から内視鏡を入れ、胃、十二指腸を経て総胆管の入り口から膵管内に挿入して膵液を採取し、造影剤を注入して画像を撮るらしい。どのくらい経ったのだろう、人声が聞こえ、喉からスルスルと管の抜ける感じがして思わず「げっ」となった。 「小川さん、終わりましたよ。お疲れさま」とK医師。
検査で膵炎になる
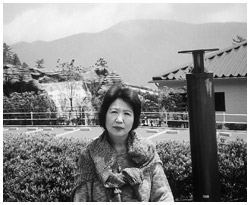
2000年4月箱根にて
その日の夕食を全部たいらげたが、翌日の朝食は途中でなんとなく食べたくなくなって残した。その後主人と電話中にお腹に軽い違和感を感じ、途中で切ってしまった。夕べと今朝の採血の結果はどうかと思いながらベッドでおとなしくしていたら「お昼休みだから」と次女が来た。「もうお昼?」カタカタと音がして食事が運ばれてきた。「あまり食欲ないの」と言ったとき、バタバタと足音がして主治医のT医師が入ってきた。
「小川さん、食事ストップ! 朝の血液検査でアミラーゼの数値が上がっています。膵炎の疑いがあるので……」
「やっぱり何かあったんだ。ママ朝からちょっとおかしかったの」と娘に話す。入れ違いにK医師が入ってきた。
「小川さん軽い膵炎おこしたみたい。5パーセントぐらいの割合なんだけど。検査しているときちょっと嫌な予感がしたんですよ。起こしやすい人って何となく分かるのでね」
食事は下げられてしまい、テーブルの上に「食事ストップ」の札が置かれ、研修医のY医師が点滴を付けていった。
「先生、膵炎ということは今日帰れないんですか?」
「そうですね、2~3日様子を見ますのでこのまま入院していただくことになります」
俄に私は病人扱いになってしまった。昼休みが過ぎた。このまま残ろうかと言う娘を大学に帰す。
夕方主人と次女が来てくれた。後日談だが、「ママの顔色すごく悪いよ。パパ今日すぐ来ないと後悔するかも」と娘が電話したらしい。そのくらい私の顔色は土気色をしていたそうだ。自分では少しだるいぐらいで、いたって元気だと思っていたのだが。
翌日主治医のT医師から膵炎は慎重に経過をみないといけないので、1週間ぐらいの入院になると告げられた。そしてERCPの話になったとき急に、「小川さんの家は何新聞とっていますか?」と聞かれ、「読売新聞です」と答えると「18日の新聞にERCPの取材された記事が載っているんですが、あれ小川さんのことなんですよ」
18日といえば入院の前日である。読んでいなかった私は恐縮した。次女が来たのでその話をすると「知っていたわよ。でもママが気にするといけないと思って黙っていた」と言う。
なんのこと? 翌日切り抜きを持ってきてくれた。「膵臓がん新診断法 遺伝子異常1日で判定」というタイトルで「3月に簡便キット登場 早期診断・治療に展望」とサブタイトルがついていた。
要約すると膵がん患者の膵液に認められるK-rasという遺伝子の変異した量を一定の枠内で示すことで、膵がんを早い段階で発見する簡便な遺伝子学的診断法が開発された。一般の医療機関で採取した微量の膵液を、各種の試薬を使って1日で判定できる。膵がんは早期発見が難しく、T大学消化器内科のO教授によれば、手術した症例の5年生存率は20パーセント以下で、治療成績はよくない。膵がんの血液検査で指標に使われる腫瘍マーカーCA-19-9はがん細胞が作るタンパクであるため、検出されたときはすでにがんが進行していることが多い。これに対しK-ras遺伝子は変異すると発がんの引き金となるとされており、膵臓で分泌される膵液から採取し調べれば、危険水域かどうか判定できる。T大消化器内科のT助手らはこの方法を使い膵臓疾患の疑いがある患者を対象に、ERCPと呼ばれる検査で採取した膵液を分析した。この検査結果についてT助手は「変異K-rasが多量に検出された場合は、確実にがんが存在すると考えられ膵がん治療が必要だ」と語る。
『これまで膵がんとは関係ないとされてきた膵嚢胞は、粘液産生性膵腫瘍あるいは通常型膵がんに進行する可能性があると指摘、「注意深く観察する必要がある」と話している。K-ras診断法の問題点として、膵液採取のため、経口挿入するERCPの必要があることだ。膵炎などの合併症をまれに起こす心配がある』という箇所を私が読んだら気にするだろうと次女は思ったとのこと。そのまれに起こすという膵炎に私はなったのだ。なるほど、膵炎は別として膵嚢胞に関することは私のことねと納得。
毎朝採血。研修医が何回も刺す。看護婦さんに「私は研修医さんの練習台みたいね」と言ったら「小川さんってニコニコしながらきついこと言うのね」と笑われた。
『白い巨塔』の大名行列

T大学付属病院
アミラーゼの数値が安定したのは5日目だった。4日間いわゆる飲まず食わず、点滴だけで栄養を補給しながら、抗生物質を投与していた。
「今日からお食事がでますからね」やっと食べられる!
しかしトレイに載っていたのは、実のないお澄ましとサラサラの重湯、そしてジュースらしきものがちょっぴりずつ入った器だった。重湯は味がなかった。うゎーこんなもの食べられないと思ったが,目をつぶって流し込んだ。その後だんだんわがままになった私にお塩や梅干しを持って次女が毎日きてくれた。
5日目にO教授の回診があった。大勢の医師がゾロゾロ付いてくる。テレビドラマの『白い巨塔』を思い出した。看護婦さんが起こそうとする素振りをしたので、ベッドに起き上がろうとする。
と、「そのままで」と顔に似合わず?優しい声で私を制した。カルテを見ながら主治医のT医師やK医師に質問したり、他の若い医師たちに膵嚢胞やERCPの説明をしていた。
これが別名「大名行列」といわれる教授回診なんだと思いながら、周りの医師、とくに担当医がすごく緊張していたので私まで緊張してしまった。
その後順調に回復した私は入院9日目の1月27日に退院した。
「迷惑かけてごめんなさい」
「いや、大変だったね。娘に脅かされてどうなるかと思ったよ」
「ねえ、R病院で検査しても膵炎おこしたかなあ」
「多分ね。そうしたらお前は我慢強いから、大変なことになっていたかもね」
「パパが同意書にサインするの気が進まなかったのは、きっと守護霊さんが守ってくれたのね」
迎えに来てくれた主人と車中で会話がはずんだ。
結果を待つ間「大丈夫」と自分に言い聞かせながらも不安がつきまとっていた。2月15日の結果報告で、私の膵液からK-rasは全く検出されなかった。
「よかった。パートナーが消えるかと思った」
主人がめずらしく感情を込めてつぶやいた。そのとき主人がこんなに心配してくれていたんだと初めて実感した。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


