がんと一緒に生きていく身内と思うことにしました
術後8年目に骨転移が判明
 ゾメタ投与中の石田さん
ゾメタ投与中の石田さん病状に変化が現れたのは、術後5年が経過したころのことだ。PSA検査の数値がじわじわと上昇し始め、次の段階の治療を考えなければならない時期にきていた。
主治医は放射線治療をするか、抗がん薬治療をするかで迷っていたが、PSA値の上昇速度が極めて遅いこともあって、男性ホルモンを遮断するLH-RHアゴニスト製剤を追加。
骨転移が判明したのは、それから3年後の2012年9月のことだ。骨シンチグラフィの検査後、主治医に呼ばれて診察室に入ると、2枚の画像を見せられた。前回の検査画像と比べてみると、今回の画像には、骨の一部に明らかに影が映っていた。
「これは、骨に転移したとみなさなくてはなりません」
医師の宣告に、石田さんは大きなショックを受けた。
「骨転移があるとなると、いずれ、肺や他の臓器に遠隔転移してしまうかもしれない。これは大ごとだぞ、と思いました」
骨転移が判明すると、ただちに、骨を丈夫にする薬剤であるゾメタ*の投与が開始された。ゾメタとは、骨粗鬆症で使われるドロネート系の飲み薬を強力にした注射薬で、痛みや骨折、高カルシウム血症などに効果がある。一方で、ゾメタの投与中に歯の治療を受けると、顎骨壊死*や骨髄炎を起こす危険があるともいわれている。
「ゾメタの治療を始めるとき、『抜歯は禁止』といわれました。歯を抜いたところから、顎の骨の壊死が始まる恐れがあるというんです。治療中に歯の詰め物がとれたんですが、口腔外科と相談して、『骨を削ったりしなきゃ大丈夫だ』ということになりました。ただ、ゾメタにはそれ以外の副作用はほとんどないので、楽といえば楽ですね」
現在は、ゾメタを4週間に1回投与するほか、エストラサイトと前立腺肥大症の薬であるアボルブ*の服用を続けている。
*ゾメタ=一般名ゾレドロン酸 *顎骨壊死=顎の骨の組織や細胞が局所的に死滅し、骨が腐った状態になること *アボルブ=一般名デュタステリド
誰にも言えなかった排尿障害の悩み
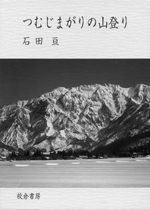 自ら執筆・出版した『つむじまがりの山登り』(校倉書房)
自ら執筆・出版した『つむじまがりの山登り』(校倉書房)「治療は割合、楽なほう」と語る石田さんだが、悩みがなかったわけではない。実は石田さんは、手術以来ずっと、頻尿や尿失禁などの排尿障害に苦しめられてきた。その悩みを誰にも打ち明けられないまま、今日まで暮らしてきたという。
「尿意を感じたら、5分から10分以内にトイレに駆け込まないといけない。全然尿意を感じないのに、失禁してしまうこともあるんです。とにかく、いつ、どこでどうなるかわからない。本当に困っています」
つきあいの多い���田さんにとって、とくに心配の種がお酒の席だという。ビールを飲めば、電車の中で尿意を催して大変なことになる。さりとて、日本酒やウイスキーにすると、今度は酔いで尿意の感覚が鈍くなり、失敗しかねない。しかも、この排尿障害は年々ひどくなってくるという。
「先日も、電車で席を譲られたんですが、『運動不足だから、少し揺られていたいんだ』といって、断りました。座っていると、尿意を感じにくいので危ないんです。トイレに行く間隔をうまく調節できるといいんですが、トイレに早めに行けば尿が出るともかぎらない。ニオイも気になります。とにかく、自分でコントロールできないのが困ります。尿失禁の予防体操もしているんですが……。このまま排尿障害が悪化したら、外に出られなくなっちゃうんじゃないか。これはもう、薬の副作用どころの悩みじゃないですね」
前立腺がんの手術に、排尿障害の後遺症はつきものである。今思えば、発症したときには70歳を過ぎていたのだから、手術をせず薬で治療したほうがよかったのではないか。
「手術をしなければ、尿失禁の心配はないわけですからね」
石田さんの言葉には、後悔がにじんでいた。
毎年の山登りが体力のバロメーター
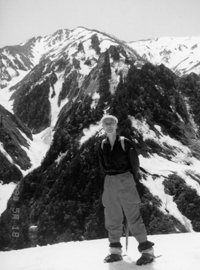 奥只見・荒沢岳(新潟県)にて
奥只見・荒沢岳(新潟県)にて現在も、男性ホルモンを抑える薬と骨転移治療の薬による治療を続けながらも、さまざまな活動で多忙な日々を過ごす石田さん。自らの病歴を語るその語り口は淡々として、病気とほどよい距離を保っているように見える。
「たぶん、やることがありすぎるからでしょうね。会社やジャズ・バンドのことで年中用事がつまっているので、気が抜けない。本当はもう少しのんびりしたいんですが……」
とはいうものの、傘寿を迎えた今、寿命を意識するようになったのも事実だという。石田さんが今、一番不安に感じているのが、遠隔転移の可能性だ。2012年暮れ、エッセイストの小沢昭一さんが前立腺がんで死去したことにも衝撃を受けた。
「昨年あたりから、同世代の人がバタバタ死んでいくんです。自分も、がんがどこかに転移すれば、余命いくばくもないかもしれない。そう思うと、がんの治療は延命措置にしか過ぎないのではないか、という気がしてきたんです。最近は薬も少しずつ強くなっていますし、『薬の力で生かされている』状況になりつつあるのではないか。薬でがんが制圧できるのならそれもいいけど、死ぬときは薬で苦しみたくない。どうせ死ぬなら苦しまないほうがいい、と思っちゃいますね。結局は、がんと一緒に生きていくしかない。がんも身内と思うしかないんです」
そう語りつつ、80歳を迎えた今も、さまざまな企画を練るのに余念がない。毎年、仲間と一緒に越後の浅草岳に登っては、「体力を測るバロメーターにしている」という。バンド活動もライブをすることで精力的に続けている。
「本場のニューオーリンズでは、ジャズもロックみたいになってきて、僕らがやっているようなジャズは、そのうち消滅するんじゃないかといわれています。むしろヨーロッパのほうが、僕らのようなニューオーリンズ・ジャズを歓迎してくれるんじゃないか。もっといろんなところに行って、ジャズを演奏してみたいですね」
病気と闘う原動力は、持ち前の好奇心と行動力。その尽きることのないパワーに脱帽する思いで、校倉書房を後にした。
同じカテゴリーの最新記事
- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)
- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん
- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って


