治療する側とされる側の懸け橋の役割を果たしたい 下行結腸がんⅢA期、上部直腸、肝転移を乗り越え走るオストメイト口腔外科医・山本悦秀さん
走ることで体力を増強させる
山本さんがランニングに打ち込むようになったのは1987年、山本さん、39歳のときである。その少し前に実兄が膵がんで倒れ、他界していた。
その死を目の当たりにした山本さんは、「がんに負けない健康と体力」を身につけるべく、ランニングを開始、全国で行われるロードレースやハーフマラソンを転戦するようになる。そうしているうちに「ランナーズハイ」と呼ばれる心地よさに魅せられ、2年後には初めてフルマラソンも完走する。
その頃には山本さんは、年間30回以上のレースに出場するようになっていた。そうしてランニングは山本さんの生活のベースになっていく。
「私にとっては、ランニングは単なる楽しみではありません。自らの健康を測るバロメーターであると同時に、健康や体力強化を実現するための方法論でもあるのです」と、山本さんは語る。
実際、この言葉は比喩でもなんでもない。驚くことに、山本さんは治療中で体力が必要なときにも、ロードレースやハーフマラソンの大会に出場しているのだ。
例えば、最初の手術の後では、化学療法を行っている最中の05年10月に金沢市の市民マラソン大会に参加、また、2度目の直腸がんの切除手術時には、何と手術の2日前にハーフマラソンを完走しているのだ。こうしたランニングへの取り組みの背景にあるのが、山本さんならではの健康観だ。
「手術前というと、誰もが体力を温存するために大人しくしています。でもね、私は違っている。走ることで、体力をより強化するのです。もちろん、自分にはまだこれだけの体力がある、と自信を持てることの効用もある。スポーツ選手が大切な試合の前に強化合宿をするのと同じ原理かもしれません」
絶体絶命の危機だった肝転移の後でも、もちろん、山本さんはいち早くランニングに復帰している。驚くべきことに肝臓留置カテーテルがまだ取れない08年5月に福井県鯖江市で行われた10kmのロードレースに出場しているのである。
「走ることで体力を回復し、免疫力を強化する。そうしてがん再発を予防してやろうと考えた。もちろん、走っているときは再発不安の恐怖から、解放されるということもありました」
さらに抗がん薬治療中にも同じ10kmのロードレースに参加する。
もちろん、記録など望むべくもない。しかし、山本さんはまったくめげることなく、その後も月2回のペースでロードレースやハーフマラソンに出場し続けた。そして肝転移後、4戦目の「健民トリム」大会からは成績もどんどん上向きになっていくのである。それは山本さんが、最悪の状態を脱し、がんを克服しえたことの証しといえるの���もしれない。
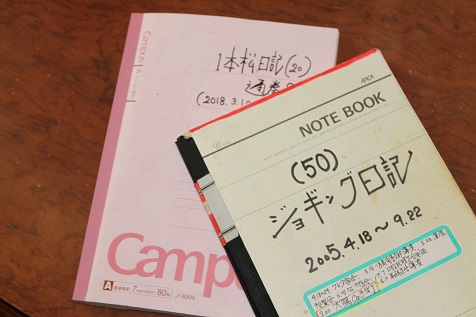

ストーマなんて気にしない
それから10年――。
山本さんは金沢大学を定年により退官し、現在は東京・洗足で、奥さんが開業する歯科医院を口腔外科診療という側面からサポートしている。もちろん、レース出場800回を目前にしたランニング生活も順調そのものだ。ただ、これまでの治療を振り返ると、一点だけ誤算もあった。
「2回目の手術の時に仮設のつもりでつけたストーマが仮設ではなくなってしまっているのです。何だか騙されたような話だけど、肝転移の後、5年たったときに、まあ、そんなに不便でもないし、ランニングに支障があるわけでもないからまあいいか、と、そのままストーマ生活を続けることにしたのです」
そう決めた後は、いかにも山本さんらしく、自ら「オストメイトの広告塔」を名乗ることにしたという。ちなみにオストメイトとは、ストーマ保有者のことを指している。
「オストメイトの人たちはごく普通に暮らしています。ただ一部には偏見も残っているし、トイレ使用などでクレームが寄せられることもある。私はことさらオストメイトの立場を主張しようとは思わない。ただ世の中には、こんな人もいるということを理解してもらいたいのです」
山本さんの視点はきわめて普遍的だ。山本さんが訴えているのは、結局のところ、誰もが自他の差異を認めて共存できる社会を実現したいということだろう。翻ってみると、そんなおおらかさ、自由さが山本さんの生き方のベースにあるようにも思われる。そして、そんな生き方こそが、山本さんのがん克服の最大の要因だったのかもしれない。
そのがんからの生還者、山本さんが今後の抱負を語る。
「怖い思い、つらい治療を重ねて患者さんの気持ちがわかるようになった。そのことで患者さんに寄り添うこともできるようになった。この経験を活かして、治療する側とされる側の懸け橋になれればと考えているのです」
医師としてオストメイトがんサバイバーとして、そして1人のランナーとしてこれからも新たな〝走り〟が続く。
同じカテゴリーの最新記事
- 人生、悩み過ぎるには短すぎてもったいない 〝違いがわかる男〟宮本亞門が前立腺がんになって
- がん患者や家族に「マギーズ東京」のような施設を神奈川・藤沢に 乳がん発覚の恩人は健康バラエティTV番組 歌手・麻倉未希さん
- がん告知や余命を伝える運動をやってきたが、余命告知にいまは反対です がん教育の先頭に立ってきたがん専門医が膀胱がんになったとき 東京大学医学部附属病院放射線治療部門長・中川恵一さん
- 誰の命でもない自分の命だから、納得いく治療を受けたい 私はこうして中咽頭がんステージⅣから生還した 俳優・村野武範さん
- 死からの生還に感謝感謝の毎日です。 オプジーボと樹状細胞ワクチン併用で前立腺PSA値が劇的に下がる・富田秀夫さん(元・宮城リコー/山形リコー社長)
- がんと闘っていくには何かアクションを起こすこと 35歳で胆管がんステージⅣ、5年生存率3%の現実を突きつけられた男の逆転の発想・西口洋平さん
- 治療する側とされる側の懸け橋の役割を果たしたい 下行結腸がんⅢA期、上部直腸、肝転移を乗り越え走るオストメイト口腔外科医・山本悦秀さん
- 胃がんになったことで世界にチャレンジしたいと思うようになった 妻からのプレゼントでスキルス性胃がんが発見されたプロダーツプレイヤー・山田勇樹さん
- 大腸がんを患って、酒と恋愛を止めました 多彩な才能の持ち主の異色漫画家・内田春菊さんが大腸がんで人工肛門(ストーマ)になってわかったこと


