肺がんが教えてくれた生きるヒント 放射線治療専門医が34歳でがんに。アフラックのCMで有名になった加藤大基さん
医師の医療用麻薬の偏見を患者として体験
手術の翌日、加藤さんは体を動かすたびに手術跡に激痛が走るようになり七転八倒の苦しみを味わうようになった。たかだかベッドで小さな寝返りを打っただけで、示現流の使い手にばっさり袈裟がけに斬られたような激痛が走るのだから、堪ったものではない。
夜になっても眠ることができず、ベッドの上で彫刻のように静止したまま朝を迎えた。外が明るくなったからといって痛みが和らぐわけではない。激痛に耐えながら加藤さんは脊椎カリエスによって28歳の若さで寝たきり生活を余儀なくされた正岡子規に思いを馳せていた。
日頃歴史に接している人間にとって、現在は歴史の1ページでしかない。いつの時代の人物であろうと、共感する人物や学ぶことの多い人物は常に精神的に近い距離にいて、困難直面したときにはそれらの人物から生きるヒントを得ようとするものだ。
激痛に耐えている間、歴史家でもある加藤さんが夜通し子規のことに思いをめぐらせ、自分と重ね合わせながら、脊椎カリエスで子規が味わった激痛は如何ばかりのものだったのだろうと考え続けたのも自然な成り行きといっていい。
加藤さんが激痛から解放されたのは朝になってからだ。担当の医師が往診に来た際、加藤さんがベッドの上で微動だにできないまま痛みをこらえているのを見て、すぐに医療用麻薬の量を増量してくれたのだ。 このときの経験で加藤さんは医療用麻薬が偏見と誤ったイメージによって何の根拠もなく必要量の数分の1しか処方されてないことの不条理を、身をもって経験した。
医療用麻薬は適切な使い方をすれば、むしろ体力や気力が回復してQOL(生活の質)の向上にも繋がることが多い。とくに疼痛に苦しむ人間にとって、それは不可欠であり、それがQOLを維持できる唯一の命綱のなっているケースが多い。
病床で正岡子規に思いを馳せた
それを思うと加藤さんの脳裏にはまた正岡子規が去来する。
子規が28歳で脊椎カリエスと診断され、ほとんど寝たきりの生活を余儀なくされながら、激しい痛みから解放されて俳句、短歌、随筆に数々の傑作、秀作を残しているが、それを可能にしたのはモルヒネだった。
結局、子規は最後までそれを欠かせなかったが、アヘン中毒で廃人になるどころか、日本の文学史に大きな足跡を残す珠玉の作品を作り続けて34年の短い生涯を閉じている。
「手術後は倦怠感がひどくて本を読む気にならないので、ベッドから窓の外の景色をよく見ていました。���郷界隈は多くの文人が暮らし、作品の舞台にもなったところですから、印象にある小説の一コマを思い浮かべたり、そこに暮らした人物のことを考えたりしていました。
とくに正岡子規はいまの東大に学んだ人であり、布団から動けない境遇のなかで『病牀六尺』などを編み上げた根岸の家も、上野の山を挟んで向かい合っていますから、子規のことに、あれこれ思いを馳せることが多かったですね」
吉田松陰の生き方に生きるヒントを見いだす
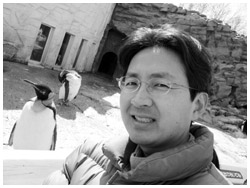
2008年3月、北海道旭山動物園のペンギンと
もう1人、入院中に加藤さんの脳裏にたびたび去来した人物は吉田松陰だった。加藤さんは恩師である中川恵一さんの勧めで、自らのがん体験をベースにした『東大のがん治療医が癌になって』(ロハスメディア刊)と銘打たれた著作を著しているが、その中には松陰について書かれた箇所がいくつかあり、至誠を貫く1点の濁りのない生き方や教育者としての優れた資質に強い共感を覚えていることが伝わってくる。本のなかで、彼がとくに多くのスペースを割いているのは松陰の死生観についてだ。
数えの30歳で刑場の露と消える前日、松陰は『留魂録』を書きあげている。これは冒頭に「身はたとひ 武蔵の野辺に朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂」という辞世の歌が記されているのを見てもわかるとおり、遺書として書かれたもので、自分の肉体は死んでも志は同志の士たちに受け継がれ、生き続けて欲しいという思いが率直に語られている。
そのように吉田松陰は死の前日まで精一杯生き、松下村塾に学んだ同志たちに真心のこもったメッセージを送り続けたが、加藤さんはその姿に強く惹かれ、生きるヒントを見出す。
「松陰を見ていると、いつ人生が完結しても構わないというくらいの覚悟と意気込みを持って日々を生きないといけない、ということを教えられます。このことは松陰だけでなく、脊椎カリエスで布団の上から動けない生活の中で、死の間際まで珠玉の作品を生み続けた正岡子規からも、教えられることです」
その結果、加藤さんは歴史上の人物の死を1つひとつ検証していけば、我々現代人の、生と死を考える上でも、多くの教訓を得られるのではないかと考えるようになった。
その思いは揺らぐことがなく、退院後、彼は昔と今では、生と死に対する考え方がどのように違い、それが社会や人間にどのような影響を及ぼしているか探る活動を始めた。
「順天堂大学に医史学という講座があって、そこの先生にご協力いただいているのですがいま、ぼくたちが勉強しているのは、現在のがん患者さんと、過去の人たちの死生観です。
昔は結核や天然痘が死の病でしたから若くして亡くなる人間がたくさんいました。しかも、大家族で暮らすのが普通で、大半が家で息を引き取ったので、死はありふれたものでした。
でも現在は核家族で、家で亡くなるケースは10パーセント程度しかない。身の回りでめったに人が死なないから死が身近なものではなくなっている。そのため病院で突然身内が予期しない形で死んだりすると、受け入れられないことが少なくない。
最近医療訴訟が急増している背景には、医療側のミスではなくても人は突然死ぬのだということを受け入れられない方が増えていることも1つの要因になっているように思います」
将来、歴史家としての活躍も

医療だけでなく、歴史にも博覧な加藤さん
手術から2年、現在加藤さんは免疫療法をメインに行うクリニックで診察に当たるかたわら、中川恵一さんの要請を受けて週1回ではあるが東大病院放射線科に復帰している。そのため、臨床医としての仕事とその勉強に追われ、歴史の勉強にはなかなか手が回らないようだ。
昨年結婚し、もうじき第1子が誕生する予定とおっしゃっているので、これからの生活基盤を固めるうえで、そうなることは仕方のないことだ。
しかし、1人の歴史ファンとして言わせてもらえば、加藤さんは歴史家としても大きな可能性を秘めているように思えてならない。
幕末から明治にかけての時代は魅力あふれるダイナミックな人物が次々に現れている。そのなかには高野長英、緒方洪庵、大村益次郎など、医者を生業としていた人物が少なくない。

2007年5月に発行。
中川恵一さんとの共著
司馬遼太郎や吉村昭は史実に沿った形で彼らを題材にした傑作を残し、読むものを感動させてくれるが、惜しむらくは、医学や自然科学の深い知識に欠けるため、高野長英がどんな医者で、シーボルトからどんなことを学び、どんな医療活動をしていたのか見えてこない。
大村益次郎にしても彼が長州の村医者時代どの程度の医療活動を行い、自然科学の知識がどの程度だったか知ることができれば、もっと完成系に近い大村益次郎像が描けるのではないかと思ったりもする。
老婆心ながら、加藤さんなら、それができるのではないか、とふと思った。
同じカテゴリーの最新記事
- 人生、悩み過ぎるには短すぎてもったいない 〝違いがわかる男〟宮本亞門が前立腺がんになって
- がん患者や家族に「マギーズ東京」のような施設を神奈川・藤沢に 乳がん発覚の恩人は健康バラエティTV番組 歌手・麻倉未希さん
- がん告知や余命を伝える運動をやってきたが、余命告知にいまは反対です がん教育の先頭に立ってきたがん専門医が膀胱がんになったとき 東京大学医学部附属病院放射線治療部門長・中川恵一さん
- 誰の命でもない自分の命だから、納得いく治療を受けたい 私はこうして中咽頭がんステージⅣから生還した 俳優・村野武範さん
- 死からの生還に感謝感謝の毎日です。 オプジーボと樹状細胞ワクチン併用で前立腺PSA値が劇的に下がる・富田秀夫さん(元・宮城リコー/山形リコー社長)
- がんと闘っていくには何かアクションを起こすこと 35歳で胆管がんステージⅣ、5年生存率3%の現実を突きつけられた男の逆転の発想・西口洋平さん
- 治療する側とされる側の懸け橋の役割を果たしたい 下行結腸がんⅢA期、上部直腸、肝転移を乗り越え走るオストメイト口腔外科医・山本悦秀さん
- 胃がんになったことで世界にチャレンジしたいと思うようになった 妻からのプレゼントでスキルス性胃がんが発見されたプロダーツプレイヤー・山田勇樹さん
- 大腸がんを患って、酒と恋愛を止めました 多彩な才能の持ち主の異色漫画家・内田春菊さんが大腸がんで人工肛門(ストーマ)になってわかったこと


