佐々木一十郎名取市長が語る 「子どもたちに、きちんと引き継いでいける自立したまちを」 末期の上咽頭がんに打ち勝って地方行政に手腕を振るう
入院生活に備えネット環境を整えた
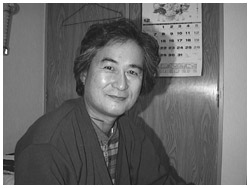
入院治療を開始した当時の佐々木さん
入院したのは放射線科の病棟だが、ここは驚くほど暗い印象の一角だった。建物が古くて実際に暗いということもあるのだが、患者のほとんどががん患者なので暗い雰囲気になってしまっているようだった。
佐々木さんは、入院するにあたり、真っ先にインターネット環境を整えておくことにした。病室は個室なのだが、風呂もシャワーもトイレもなく、快適な生活は望むべくもない。せめて外部とのつながりを断たないために、インターネット環境の整備が必要だと感じたのだ。 とりあえずPHSのカード電話をノートパソコンに接続して使う一方、病院にはISDN回線を引き込んでくれるように頼んでみた。ADSLや光ファイバーのなかった時代だ。
「最初はとんでもないことを言い出す患者だという目で見られましたが、いろいろな方が応援してくれたことで、なんとか実現できました。日本の医療ではQOL(生活の質)が大事、などといいながら、入院患者の社会生活維持のための配慮はまったくなされておりませんね。
患者が希望を持って闘病生活を送るためには、病が癒えて復帰したときに戻っていく社会と、つながりを持ち続けることがとても大切です。入院している間、患者は社会と切り離されることで絶望するのだから、つながる手段を考えることが絶対に必要だと思います」
当時、東北大学付属病院では新しい病棟を建設中だった。佐々木さんは、患者の声を集める提案箱に、新病棟ではベッドサイドにブロードバンドの端末を設置することを提案した。だが、そのアイディアは実現しなかったという。
「その時点での設置が無理なら、せめてダミーの配管だけでもしておくように提案しました。配管があれば、後でいかようにも使えますからね。ところが、これも不採用。病棟の設置基準にないというのがその理由。お役所の頭の固さもありますが、患者が社会とのつながりを持つということの重要性を、病院関係者が理解していないのです。」
長期入院し、病院で生活してみて、今まで気づかなかった多くのことが見えてきた。
治療の副作用がじわじわ襲ってきた

抗がん剤の副作用で体にダメージを受けていたころ
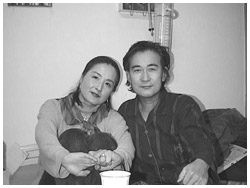
闘病生活を支えてくれた妻と病室で
放射線治療と化学療法の併用療法は、患者の佐々木さんにとって、これまでに経験のない未知の体験だった。シスプラチンと5-FUの併用は、現時点では一番効果があり実績もあるが、副作用もあると聞かされていた。
「副作用症状がひどいときには、自分がこれほどダメージを受けているんだから、がんはもっとダメージを受けているはずだと思っていました。抗がん剤治療は確かに大きな副作用がありましたが、不安はありませんでした。毎日、血液検査をやって、数値が悪ければすぐに止めるということだったので、どんなにひどくても、自分の体がもたないところまでいくことはないはず、という安心感がありました」
放射線による治療でダメージを受けたのは唾液腺だった。放射線をがんの病巣に集中させているのだが、どうしても唾液腺にもかかってしまうのだ。また、抗がん剤によって粘膜という粘膜がすべて炎症を起こし、それによって自分のつばが飲み込めないほどの痛みに出会った。
体にダメージはあったが、なんとか体力がもち、狙い撃ちされたがんは次第に消えていった。放射線と抗がん剤の同時併用療法が功を奏したのだった。
退院したのは99年の3月24日。抗がん剤の副作用で髪はかなり抜け落ちていたが、それはほどなく回復した。
自立できるまちづくりを目指して市長になる
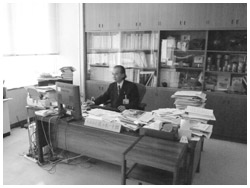
市長室で執務におわれる佐々木さん

名取市役所の建物
がんとの戦いに勝ち抜いた佐々木さんは、市議会議員を2期8年務めた後、00年の市長選挙に立候補した。がんの治療からちょうど5年が経過したところだった。
市長を目指したのは、「自分たちのまちを自分たちの思いで作っていきたい」との思いからで、そのためには市長になる必要があった。
「市議会議員にできることは非常に限られているんですよ。簡単に言ってしまうと、予算の編成権や執行権を持っているのは市長だけで、議員は議会で予算や条例について審議するだけ。
国政は議員内閣制ですから、国会議員が内閣を作り行政を担当することができますが、地方自治体の権限は首長に集中しています。政策を実現していくためには、市長になる必要がありました」
佐々木さんが目指したのは、仙台のベッドタウンになりつつあった名取市を、別の方向に舵取りすることだった。ベッドタウン化すれば、働き盛りの人たちを集めることができる。しかし、いずれその人たちは年をとる。そして、ついには、支える若者のいない老人のまちとなってしまうのだ。
「ここには海も山もありますし、気候温暖で災害も少ない。そのため、旧石器時代からずっと人々が暮らし続けてきた歴史があります。こんな自然環境に恵まれた場所ですから、子どもたち、孫たちに、きちんと引き継いでいけるまちを作っていきたいと思っているんですよ」
この名取市で生まれ育った子どもたちが、このまちで仕事に就けるような職住近接型のまち。そういう自立したまちが、佐々木さんの目指すところだという。
また、名取市では、がん治療のための陽子線治療施設を作る計画も進めている。東北大学医学部放射線科教授の山田章吾さんをはじめとする有志とともに、宮城県や経済界に働きかけているところだ。用地には名取市にある宮城県立がんセンターの敷地の一部を借りる約束もとりつけているという。
「重粒子や陽子線治療という技術が開発されているのですから、治すことができるがんはできるだけ治そうということです。救える生命は救いたい。陽子線は体の奥のがんでも、周囲にほとんど影響を与えずに治療することができます。私のがんも、陽子線で治療していたら、唾液腺を温存できたかもしれません。
名取市に作る施設では、治療もさることながら放射線の専門医や放射線技師などの人材育成や、新しい医療機器の開発にも力を注ぎたいと考えています。人材がいなければこの治療は広まりません。将来的には、各県が1台ずつ持つようにならないと、保険適用にはなりませんからね」
陽子線治療施設はまだ計画の段階だが、ぜひ実現させてほしいものだ。
生まれついてのオプティミスト

仲間と共にレスキュー挺に乗り
子どもたちの元旦セーリングを見守る
今年の元日、佐々木さんは名取市沖の海上で太平洋から昇る初日を拝した。その日は、松島・名取ジュニアヨットクラブの恒例となっている元旦セーリングがあり、佐々木さんは仲間と共にレスキュー艇「なとり」に乗り、操船しながら子どもたちのセーリングを見守っていたのだ。
新しく迎えた2008年だが、今年の秋には、がんの宣告から10年を迎えることになる。がんが再発する可能性は低そうだが、ゼロというわけではないだろう。しかし、それを恐れることはないという。
「がんの末期と言われたあの時も、今も、考えていることは同じですよ。人間はいつか必ず死を迎えるし、明日、玄関を出たところで車にはねられて死ぬかもしれない。大切なのは、生きている今、何をすべきかということです。」
佐々木さんはにこやかにそう言う。
元旦セーリングでは、ジュニアセーラーたちが小さなヨットで海に出た。子どもたちが乗っているのは、オプティミスト・ディンギーという小さな箱型のかわいらしい艇種だ。世界中の海で、この艇種は子ども用のヨットとして使われている。安定性がよく、操艇しやすいのが特徴だ。
オプティミストとは、楽天家、楽観主義者という意味を持つのだが、佐々木さんは、自分のことを「生来のオプティミスト」と言っている。
少々波に揺られても、風に吹かれても、安心して乗っていられるヨット。なるほど、と思った。佐々木さんは、がんの話をしながらも笑顔を絶やさない。オプティミストだからこそ、がんという荒海を飄々と乗り切れたのかもしれない。
同じカテゴリーの最新記事
- 人生、悩み過ぎるには短すぎてもったいない 〝違いがわかる男〟宮本亞門が前立腺がんになって
- がん患者や家族に「マギーズ東京」のような施設を神奈川・藤沢に 乳がん発覚の恩人は健康バラエティTV番組 歌手・麻倉未希さん
- がん告知や余命を伝える運動をやってきたが、余命告知にいまは反対です がん教育の先頭に立ってきたがん専門医が膀胱がんになったとき 東京大学医学部附属病院放射線治療部門長・中川恵一さん
- 誰の命でもない自分の命だから、納得いく治療を受けたい 私はこうして中咽頭がんステージⅣから生還した 俳優・村野武範さん
- 死からの生還に感謝感謝の毎日です。 オプジーボと樹状細胞ワクチン併用で前立腺PSA値が劇的に下がる・富田秀夫さん(元・宮城リコー/山形リコー社長)
- がんと闘っていくには何かアクションを起こすこと 35歳で胆管がんステージⅣ、5年生存率3%の現実を突きつけられた男の逆転の発想・西口洋平さん
- 治療する側とされる側の懸け橋の役割を果たしたい 下行結腸がんⅢA期、上部直腸、肝転移を乗り越え走るオストメイト口腔外科医・山本悦秀さん
- 胃がんになったことで世界にチャレンジしたいと思うようになった 妻からのプレゼントでスキルス性胃がんが発見されたプロダーツプレイヤー・山田勇樹さん
- 大腸がんを患って、酒と恋愛を止めました 多彩な才能の持ち主の異色漫画家・内田春菊さんが大腸がんで人工肛門(ストーマ)になってわかったこと


