大腸がんを克服し見事に評論家生活に復帰した豊田泰光さんの闘病秘話 まさかの再手術。あのときは、生きて還れるような気がしなかった
仕事のときはいつも便秘状態
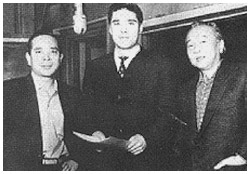
有名人のなかには退院後、体力が十分回復しないうちに現場に復帰する人が多いが、豊田さんは無理をせず、ナイター中継の解説や講演の仕事も体力の回復に合わせて徐々に増やしていった。しかも仕事に行くときは必ず下痢止めをしっかり飲んで「便秘状態」にしてから出かけた。まわりに迷惑を掛けたくなかったからだ。これは、仕事をするからにはまわりに甘えてはいけない、という豊田さん一流のダンディズムから来ている。それだけに西鉄時代同じ釜の飯を食った仲である仰木彬さんが、2005年に肺がんが再発した体でオリックスの監督に返り咲いたことには批判的で、仰木さん自身にも直接、引き受けるべきではないと忠告していたようだ。
「仰木チャンは僕の1年後輩で、西鉄時代2遊間コンビを組んだ仲だから、遠慮せずになんでもいえる仲なんです。だから監督就任の話を受けるかどうか迷っているときに、『あんたはグランドで死ねたら本望かもしれないけど、選手たちはどうするの』って忠告したんです。今はもう、監督がベンチにふんぞり返っていられる時代じゃない。3塁コーチスボックスに立って陣頭指揮するくらいじゃないとダメなんです。
でもいくら忠告しても聞いてもらえなかったですね。本人はグランドで死ぬのが美学だと思い込んじゃっていましたから。案の上、仰木ちゃんはそのシーズンの後半になると体力が続かなくなって、ベンチで居眠りする有様でした。終盤には球場の階段を昇るのもしんどそうだったと聞いています。
がん患者は、がんに甘えてはいけないんですが、仰木ちゃんは、そうなってしまいましたね。監督としては飛び切り優秀で、イチローをはじめ多くの才能にチャンスを与えた功績のある人だけに、残念でしたね」
十分な回復まで復帰すべきでない

フジテレビで辛口の野球解説をしていたころ
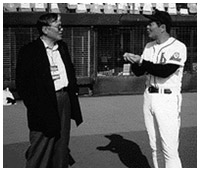
野球解説者として王監督を取材中
このように豊田さんはがん患者のあり方に対して野球解説同様、辛口の正論をストレートに述べる。王貞治監督が体力が十分回復しないうちに、やせ細った体で監督���帰したことに対しても、もっと体力が回復してからでもよかったのではないかという思いが強いようだ。
「僕は、何も、がんになったら監督をやるなと言っているわけではないんですよ。監督という仕事は激務だから十分こなせるだけの体力が回復するまでは、復帰すべきではないと言ってるだけです。監督のなかには、ヤンキースのジョー・トーレ監督のように、がんを克服して監督に復帰したあとも常勝将軍として見事な采配を振るい続けている例もあるんですから」
ヤンキースのトーレ監督は今や日本でもっとも知られた監督の1人になっているが、彼が前立腺がんを克服した経歴の持ち主であることは、ほとんど知られていない。あの眼光鋭く相手チームの動きを監察する表情には、病人っぽさが微塵も感じられないのでそれも無理からぬことだ。トーレ監督は昨年まで9シーズン連続でヤンキースを地区優勝に導いている。それが可能になったのも、1999年のキャンプ中に見つかった前立腺がんを早期発見と十分な休養で完治させることができたからだ。
興味深いのは、9年連続地区優勝の最大の協力者だったピッチングコーチのメル・ストットルマイヤー(2005年まで在任)も在任中に白血病を告知されながら見事に克服したがんサバイバーであることだ。
そのためヤンキースは、大リーグのなかでも、がんの撲滅キャンペーンや啓発活動にひときわ熱心に取り組んでおり、昨年の母の日にはデレク・ジーターやアレックス・ロドリゲスがピンクのバットを持って打席に立つ姿が見られた。これは乳がんの撲滅と早期発見を呼びかけるキャンペーンの一環として行われるものだが、ピンクのバットは試合後オークションにかけられ、売上げはすべて乳がんの患者団体に寄付されている。ヤンキースは今年も父の日に行われた、前立腺がんの撲滅と早期発見をアピールするキャンペーンに全面協力し、選手全員がキャンペーンのスローガンを記した腕章を腕に巻いて打席に立っていた。松井秀喜も左腕にその腕章を巻いて打席に立っていたのでご記憶の方も多いのではないかと思う。
がんの啓発活動とプロ野球

ちょうど豊田さんにお会いしたのがその翌日だったので、そのことを話題にすると、球界のご意見番らしい鋭い反応が返ってきた。
「アメリカと同じように、日本も、もうじき2人に1人ががんを経験する時代になるんだから、日本の球界もそれなりの役割を果たすべきですよ。必要なのは、真剣に取り組む姿勢と、気の利いたアイデアです。母の日のピンクバット・イベントみたいな、気の利いた企画を日本でも考えてどんどん実行すればいいんですよ。そうすれば女性ファンの裾野を広げることにも繋がるから、長い目で見れば自分たちのプラスにもなるんです」
それが実現すれば、日本のがん医療に大きく貢献することになるだろう。日本のがん患者の死亡率が高いのは、医療水準の不均衡という要因もあるが、それ以上に大きいのは早期発見の重要性がまだ十分認識されておらず、発見が遅れるケースが多いからだ。早期発見の重要性をなかなか国民の各層に浸透させることができないのは、それを効果的に伝える手段がないからだ。
それを考えると、日本最大の国民的娯楽であるプロ野球を啓発活動の場として活用できることは願ってもないことだ。
アメリカでは、大リーガーががん医療の発展に大きな貢献をしてきた。その1つの例が、世界屈指のがん医療専門病院であるシアトルのフレッド・ハッチンソン・がんセンターだ。日本でもよく知られたこの病院の名前の由来をご存知だろうか?
フレッド・ハッチンソンは実は野球選手なのだ。フレッド・ハッチンソンは現役時代、デトロイト・タイガースでエースとして活躍した投手で、引退後はタイガース、レッズの監督を歴任した。
1964年8月に肺がんの悪化でレッズの監督を辞任後、その年の11月に還らぬ人となっている(背番号1は今でもレッズの永久欠番)。
その1年後に、弟でがんの専門医であるウィリアムが、がんと戦い続けた兄の意思を受け継いでシアトルにその名を冠したがん研究機関を設立。フレッド・ハッチンソンの知名度もあって幅広い層からの財政支援があったため、このがんセンターは瞬く間に世界的ながん研究機関へと発展した。
こうした経緯があるため現在も大リーグとは密接な関係にあり、地元で絶大な人気を誇るジェイミー・モイヤー(元マリナーズのエース。現フィリーズ)は様々な基金設立の呼びかけ人になって毎年300万ドルを超す資金を同がんセンターに寄付している。
日本のプロ野球界ががんの問題に真剣に取り組むようになれば、そのうちモイヤーのような存在が現れるかもしれない。その必要性を声を大にして訴えられるのは球界のご意見番=豊田泰光さんしかいない。末永くご活躍いただき、日本のプロ野球が、がんの問題に前向きに取り組む必要性を声を大にして説いていただきたい。
同じカテゴリーの最新記事
- 人生、悩み過ぎるには短すぎてもったいない 〝違いがわかる男〟宮本亞門が前立腺がんになって
- がん患者や家族に「マギーズ東京」のような施設を神奈川・藤沢に 乳がん発覚の恩人は健康バラエティTV番組 歌手・麻倉未希さん
- がん告知や余命を伝える運動をやってきたが、余命告知にいまは反対です がん教育の先頭に立ってきたがん専門医が膀胱がんになったとき 東京大学医学部附属病院放射線治療部門長・中川恵一さん
- 誰の命でもない自分の命だから、納得いく治療を受けたい 私はこうして中咽頭がんステージⅣから生還した 俳優・村野武範さん
- 死からの生還に感謝感謝の毎日です。 オプジーボと樹状細胞ワクチン併用で前立腺PSA値が劇的に下がる・富田秀夫さん(元・宮城リコー/山形リコー社長)
- がんと闘っていくには何かアクションを起こすこと 35歳で胆管がんステージⅣ、5年生存率3%の現実を突きつけられた男の逆転の発想・西口洋平さん
- 治療する側とされる側の懸け橋の役割を果たしたい 下行結腸がんⅢA期、上部直腸、肝転移を乗り越え走るオストメイト口腔外科医・山本悦秀さん
- 胃がんになったことで世界にチャレンジしたいと思うようになった 妻からのプレゼントでスキルス性胃がんが発見されたプロダーツプレイヤー・山田勇樹さん
- 大腸がんを患って、酒と恋愛を止めました 多彩な才能の持ち主の異色漫画家・内田春菊さんが大腸がんで人工肛門(ストーマ)になってわかったこと


