- ホーム >
- 闘病記 >
- がんになった著名人 >
- 最期の生き方、最期の死に方
子どもたちのために、未来の土台づくりに奔走する婦人科医 末期がんに鞭打ちながら、南相馬復興に命を懸ける――。原町中央産婦人科病院・高橋亨平さん
地域復興のためにがん治療を
震災から2カ月。5月のある日、高橋さんは異常な腹痛と下血に見舞われる。それまでにも同じような症状はあったが、何とかしのぎ続けてきた。しかし、このときはあまりの症状の激烈さに、さしもの高橋さんも福島市の病院を訪れた。そこで下されたのが「末期の直腸がん」という診断だった。
がんは直腸から肝臓、肺にも転移しており、とくに肝臓の転移がんは野球のボールほどの大きさがあったという。
「診断画像を見て覚悟を決めた。何も治療をしなければ余命半年。きちんと治療をすれば1年持つかもしれない。がんになっても治療をしない人はいるし、そんな人の気持ちもわかる。しかし自分は少しでも長く生きて、何とか、南相馬の医療を守り、地域を復興させる土台をつくりたいと考えたんだ」
以後、厳しい治療が始まった。
外来化学療法中も診療を続ける
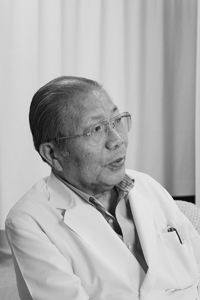
福島の今後について語る高橋さん
まず手始めに肝臓の転移がんを手術で取り除くことになった。そこで、がんを手術可能な範囲に縮小させるために抗がん剤治療が行われた。そうして半年あまり。12月初旬に手術のために入院すると、肝臓の予備能力が小さいために手術不能と判断される。再び厳しい抗がん剤治療が開始される。
そうして半年あまりが経過したころ、肛門が激烈な痛みに襲われた。原発がんである直腸のがんが進行し始めたのだ。症状を抑えるために抗がん剤治療を中断し、放射線による治療を受けることになる。そうして7月終わりから1カ月、高橋さんは治療のために週に5日、福島県立医大に通い続けた。
もっとも、その間も高橋さんは診療を中断しなかった。治療の予約を1時30分にとり、午前中の診療が終わると、車で病院へ駆けつける。そして治療を終えて帰院すると、すぐに3時から午後の診療に取り組む日々が続いた。
その放射線治療が終わり、現在は再び抗がん剤治療を始めるための経過観察の状態が続いている。もっとも血液検査で白血球の状態が悪く、なかなか抗がん剤治療の再開には踏み切ることができないという。当然ながら、体調も決して芳しいものではない。
「これまでの抗がん剤治療の影響もあるのかもしれない。2日に1度くらい、激しい脱水症状が起こり、全身が干物のように干からびてしまう。そうなると立ち上がることもできなくなるほど体力が減退してしまう。疲れもあるし、気力が萎えてしまいそうになることもあったね」
と、高橋さんは言う。
そのときには震災からすでに1年半が経過しており、同じ地域の他の医療施設も診療を再開した。そのことを考えると、診療を休むこともできたはずだ。しかし、それでも高橋さんは診療を止めようとはしない。
「他の病院もあるのだから診療をやめて治療に専念したほうがいいといってくれる人もいたよ。でも、患者さんの中には、俺でないとダメだという人もいる。俺だから安心して何でも話せるし、治療も受けられるという人もたくさんいる。そんな患者さんのことを考えると後継者が見つかるまでは、やっぱり診療を止められないな」
実際、診療再開後も高橋さんを訪ねる患者数は減少することなく、現在も多い日には100人を上回るほどだ。そうした多くの患者のために高橋さんは、病身を押して診療を続けている。
そうした診療活動とともに、高橋さんは地域の人々の暮らしを守るために、さまざまな活動に取り組んできた。
たとえば震災後、病院を再開すると被災地での医療を軌道に乗せるために、高橋さんは自治体などとも丁丁発止のやりとりを続けている。それはまず、診療に不可欠な薬剤の確保から始まった。
「薬がなければ患者を救えない。それで知り合いの薬局から回してもらおうと思ったら、県の許可が出ない。それで県に掛け合って、問屋から役所に薬を運んでもらい、それを自衛隊に病院まで運んでもらうことになった。早朝、ドアをノックする音で玄関を開けると、自衛隊員が待ち受けているのだから職員たちも驚いていたね」
72時間以上の入院を勝ち取る
また、病院での入院期間についても高橋さんは自治体とやりあった。自治体側は避難勧告が出された地域で医療活動が行われているのはおかしい、そのことを理由に72時間以上の入院を認めないと主張していたという。多くの患者さんが被災地に残っている現実を見ようとしない建前論だ。高橋さんはそんな自治体と根気よく交渉を続け、72時間以上の入院を認めさせる合意文書として、「医師の裁量による判断も可能」という1文を盛り込ませる。
「それで医師が必要だと判断すれば、以前と同じように、患者さんの長期入院が可能になった。実際、たった3日の入院じゃ救えない患者さんも沢山いるからね」
と、高橋さんはしてやったりの表情を見せる。
除染活動にも乗り出す

除染についての勉強会で、南相馬の現状を説明する高橋さん
原発事故が起こってからは、高橋さんの活動はさらに広がりを見せる。放射能汚染に脅える住民のために、高橋さんは昨年10月に「社団法人南相馬除染研究所」を設立。放射能の計測と除染に乗り出すのだ。
放射能被曝がとくに心配な妊婦たちには、被曝線量を測るフィルムバッジを持たせ、地域の人たちの自宅の放射能曝露の状況を計測し、放射能の不安のない暮らし方を指導する。また環境中に残存している放射能を遮断するために、業者に協力してもらって鉛を用いた特殊な素材のカーテンを開発、さらにボランティアを募って、住宅やその周辺の土壌の除染にも乗り出した。
「同じ地域でも、個々の住宅によって曝露の度合いはまったく違っている。コンクリート建ての住宅ならまず曝露の不安はない。木造住宅の場合は屋根の中に放射性物質が溶け出していることが多いので、2階は心配だが1階は大丈夫。そうした住宅では当分2階は使わず、1階で生活するように指導する。除染もそんなに難しいことじゃない。表層から5㎝程度、土を取り除いて、1カ所に集めて埋めればいい。こんな言い方をすると叱られるかもしれないが、放射能なんて虫のようなもの。汚れた部分をつまんで取り除けばいいんだよ」
と、高橋さんは屈託なく笑う。
私たちが取材に訪れた時点で、南相馬地区の放射能による汚染状況は、生活にまったく問題がないレベルにまで低下しているという。
「人間の体にホメオスタシスと呼ばれる恒常性機能がそなわっているように、自然環境にも自らを浄化する働きがあるんだなあ。やっぱり自然の力は偉大だよ」
また、こうした除染活動とともに、高橋さんは除染研究所を基盤として、野菜の水耕栽培を普及させる活動にも取り組んでいる。
これは非常事態に備えて、地域住民が自ら食料を確保するための試みだ。すでに町のある駐車場では、「鮮菜ちゃん」と名づけられたテーブル大の特殊なプランターがいくつも並べられ、レタスの栽培が行われている。
「初めて栽培したレタスの甘さといったらなかったね。この活動を始めたのは非常事態の有無にかかわらず、野菜作りを楽しんでもらいたいと考えたからなんだ。何かを育てるということには、人の心を癒やす力があるからね。
それが地域の人たちのコミュニケーション作りにも役立つのではないかとも考えたんだ」
こうして高橋さんは、震災後も、そして原発事故の後も、さまざまなアイデアをひねり出し、地域のために力を振り絞り続けてきた。
もちろんその当初から、高橋さんの身中では、がんが暴れていたに違いない。病にも屈しない生命力の強靭さは、同時に高橋さんの南相馬という地域への愛着の深さをも物語っているといえるだろう。
同じカテゴリーの最新記事
- 飽くなき好奇心を持ち続けたニュートリノ研究の第一人者 ノーベル賞最右翼だった物理学者の最後の研究は自らの闘病生活となった──。戸塚洋二さん(物理学者)享年66
- 没後30数年経ても今なお色あせぬ世界観 戦争を憎み、子どもたちに慈愛を注ぎながら旅立った――。いわさきちひろさん(絵本画家)享年55
- 死ぬまで競馬を愛し続けた勝負師 スキルス性胃がんに侵されながらも「馬一筋」を貫いた心優しき苦労人──。吉永正人さん(騎手・調教師)享年64
- 死を恐れず、生の限界まで仕事を続けた稀代の辛口人 世論を笑い飛ばした名コラムニストは最期までペンを握り続けた──。山本夏彦さん(コラムニスト・編集者)享年87
- 鬼の演出家の志は役者たちに引き継がれた 最期まで闘い続けた演劇人は後進に囲まれこの世を去った──。野沢那智さん(声優・パーソナリティー・演出家)享年72
- アメリカ帰りのブルース歌いは、静かに日本の大地に沈んだ 「兄貴」と慕われたその人は、何も言わずに1人で去った──。デイブ平尾さん(歌手)享年63
- 突き進んで生きるその源には、ユーモアと独自の哲学があった いくつもの才能を開花させて、風のように去って行った──。青島幸男さん(作家・タレント・政治家)享年74
- 「マンガの神様」が最期まで続けた挑戦 力尽きるときまで描き出したのは、命の輝きだった──。手塚治虫さん(マンガ家)享年60
- がんの病魔と果敢に向き合い、死のときまで作家であり続けた 稀代のストーリーテラー・マルチ才人はかくして死んだ──。中島梓・栗本薫さん(評論家・作家)享年56


