- ホーム >
- 闘病記 >
- がんになった著名人 >
- スペシャルインタビュー
がん細胞から世界平和まで縦横に語り合う白熱の3時間 「知の巨人」立花さんが自らのがん体験を踏まえ、樋野さんに鋭く迫る がん特別対論・立花 隆(評論家) × 樋野興夫(順天堂大学医学部教授)
宇宙の成り立ちの数字と、がん発生原因の数字はよく似ている
前半では昨年暮れ、膀胱がんの手術した立花隆さんが、順天堂大学医学部教授で病理・腫瘍学の樋野興夫さんに、「がんの素顔」について鋭く迫った。後半では、がん治療の現実、日本の医療改革のあり方、メディカル・タウン構想、がんに罹った場合のこころの持ち方、さらには人体と宇宙の関係性にと「知の巨人」と「病理・腫瘍学の重鎮」2人の対論は熱く縦横無尽に進んでいく――。
がんを小さくすれば普通の生活ができる

立花 僕の周囲に、抗がん剤治療の副作用に苦しみ亡くなっていった人や、現在苦しんでいる人が何人もいます。それで抗がん剤のことを少し調べましたが、抗がん剤は恐ろしいものだという印象を受けますね。
樋野 抗がん剤はがん細胞だけでなく、正常細胞もやっつけますから、副作用に苦しむ人が多いのです。ただ、薬の作用は副作用であり、副作用がない薬はありません。抗がん剤は正常細胞とがん細胞の両方をやっつけますが、がん細胞のほうが増殖の度合いが強いので、よりがん細胞に効くわけです。しかし、正常細胞にもリニュー(複製・再生)を支える増殖力の強い細胞があり、その細胞も同時に叩かれますから、さまざまな副作用に苦しむことになるわけです。最近は、がん細胞に特異的に効く分子標的治療薬という新しい抗がん剤が出てきており、普通の抗がん剤と分子標的薬のコンビネーション・セラピーが行われるようになっています。
立花 抗がん剤によってどれほどの延命効果があったかという統計資料を見ると、それほど大きな効果はないような感じを受けます。「ベネフィットとリスク」という観点に立つと、ベネフィットが意外にない。
樋野 中皮腫の薬に、昨年認可されたアリムタ(商品名)という薬があります。その薬が効く人は中皮腫の患者さんの一部ですが、効く人には良く効きます。胸の中皮腫の影が小さくなります。しかし、残念ながら1年後ぐらいしてまた大きくなるケースが多いです。だから延命効果はそれほどない。大事なことは、その薬を飲んだことによって一時的に中皮腫が小さくなり、入院先の病院から歩いて自宅に帰り、1年間、普通���生活ができることです。つまりQOL(生活の質)は完璧に上がるのです。そういう点を考えると、延命効果だけでは判断できません。
立花 そういう場合は、その薬を使用する前に、患者との間にきちんとインフォームド・コンセントをとるということですね。
樋野 そうです。抗がん剤はがんの大きさによって効き方が違います。いままで効かなかった薬でも、がんが小さくなると効いてくるケースがあります。そういう意味では、がんを小さくするというのは意味がある。
立花 僕の場合は、進行度がT1の膀胱がんですから、大したがんではなく、予後もそんなに悪くはないと思っていますが、「いずれ再発するから、そのときが問題だ」と言われています。いま3カ月おきに検査をしてもらっています。先日「これはちょっと怪しい」ということがあって、特別な断層撮影をやってもらいましたが、大丈夫でした。しかし、どこでどうなるかわからない。それでいろんな情報を仕入れて、抗がん剤についても読んでみたのですが、僕は抗がん剤は使いたくないという気持ちです。
樋野 私たちが大学に入った当時は、小児がんで多くの子供が亡くなりました。しかし、いま小児がんの多くが治ります。小児がんの特効薬が革命的に開発されたわけではありません。医者が薬の使い方を学んできた結果です。同じ薬でも、使い方によって治せるようになるのです。薬の使い方をよく知っている専門的なオンコロジスト(腫瘍内科医)が必要ですね。
縦割りの医療を改めてチーム医療の確立を
立花 日本ではオンコロジストがまだ少ないですね。これは何が原因ですか。
樋野 縦割りの弊害です。教授は一国一城の主です。外科なら外科で、手術から化学療法まで、全部やりたくなるでしょう。いまの日本の医療は相談医療で、チーム医療になっていない。1人の患者さんのために、いろんな分野の医師が多面的に議論をして治療方針を決めているわけではない。1人の主治医がいて、わからなくなったら別の医師に相談しているだけです。日本でもチーム医療をやる必要があります。がんはチーム医療で治すものですよ。
立花 ただ、チーム医療をやろうと思っても、ある部門については人材が少なすぎて難しい面もありますね。歯が抜けた櫛ではチーム医療はできない。
樋野 ですから、これからは横断的なチーム医療を推進するために、歯が抜けたようになっている部分を育てる努力が必要です。それをいまの教授クラスに求めるのは無理で、医学部の学生、大学院生ぐらいのときから横のつながりを良くする教育を行い、人材を育成すべきです。
立花 各医科大学がそういう教育システムに変えなければダメですね。
樋野 そうです。だから昨年、文部科学省は「がんプロフェッショナル養成プラン」を作成したわけです。全国の医学部では横断的ながん治療を実現するため、そのプランに基づいた教育を行っています。そのプランの大きな柱がチーム医療です。
立花 そうですか。すると何年か後には、日本でもアメリカのようなチーム医療が行われるようになるわけですね。
樋野 5年後です。5年間でチーム医療を確立することになっています。
立花 5年でできますか。
樋野 病院長の権限の強いところはできます。ただ教授の権限が強い大学病院ではなかなか難しい。そこに風穴を開けるためには、若い人たちを育てるしかないと思います。アメリカの医療は、1人ひとりの医師というより、全体はまとまります。しかし、日本は1人ひとりの医師は立派ですが、全体となるとわけがわからなくなる(笑)。
いずれがんで死なない時代がやって来る
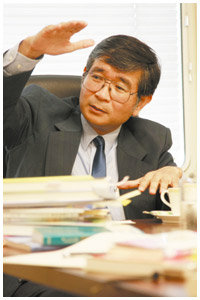
立花 医学界にだけ任せておいたのでは、チーム医療は一朝一夕にはできないような気もしますね。
樋野 第3者が積極的に関わったほうがいいかもしれません。最近は、大学完結型の病院ではなく、地域に密着した開放型の病院が求められていますから、市民、患者、医療従事者が同じ土俵に上がって議論しながら、チーム医療を推進していくべきでしょうね。
立花 具体的なイメージはありますか。
樋野 メディカル・タウンをつくるべきです。大学病院が閉鎖的な一国一城として存在するのではなく、地域と密着しながら医療共同体を目指すべきです。
立花 しかし、日本の医療の現状は、メディカル・タウンを形成する方向に進むというより、医療崩壊の流れの中で、地方の中枢病院が相次いで閉鎖に追い込まれているのが現状です。
樋野 いま医療崩壊の流れを食い止めるために医療改革が進められています。しかし、それは必ずしも患者視点の改革ではありません。患者視点の医療を実現するには、幕末に公武合体から大政奉還に至る過程で、討幕派と幕府側の間に立って活躍した、勝海舟のようなコーディネーターが欠かせない。医療界の勝海舟の役割を果たす人材は、多忙を極める急性期病院の医師からは期待できません。第3者を加えた異分野との交流を深め、患者視点の医療を実現するための議論・実践を進めていく中で、第3者的な立場の人から勝海舟が出てくる。
立花 患者視点の医療とは、具体的にどういうことですか。
樋野 私は、これからは医療の共同体の時代だと考えています。患者さんは家族が看るものではありません。他人が看るものです。いかに在宅医療といっても、退院した患者さんを家族が看るのは大変なことです。患者さんは共同体で看る。それが大切なことです。昔は天守閣を中心に城下町があり、その中にいろんなものがあって、庶民の生活は守られていた。だから私は、御茶ノ水をメディカル・タウンにすることを提唱しているのです。
立花 たしかに御茶ノ水周辺には病院が多いですね。それを1つの医療城下町としてシステム化するわけですね。
樋野 はい。現在の日本には、健康ではないけれども、かといって明日死ぬわけでもない、半病人の人が多いわけです。この人たちにどう対応するのかというビジョンが、いまの日本の医療には欠けている。いま御茶ノ水周辺の病院には、そういう人たちを含めて、1日に約1万人の外来が来ています。御茶ノ水をメディカル・タウンにし、その域内にメディカル・レストラン、メディカル・カフェをつくる。レストランやカフェに行って、明るい店内で飲食ができ、しかも病気の相談にも応じてもらえるとなれば、半病人の人たちは病院に行かなくて済むわけです。
立花 がん患者もメディカル・カフェでコーヒーでも飲みながら、樋野さんのような先生に相談を受けてもらえば、気持ちもかなり楽でしょうね(笑)。
樋野 2人に1人ががんになる時代で、がんになっても、「おまえもか」と言われる時代です(笑)。私は「がん哲学外来」を始めてから、末期のがん患者さんと接し、自分自身の人生なんか甘っちょろく見えてきて、がん患者さんでないと1人前ではないような錯覚に陥ることもありますよ。がんは当たり前の病気と受け止めるべきです。がんの50パーセントは治ります。あと2~3年早く見つけることができるようになれば、70パーセントは治るようになります。いずれがんで死なない時代が来ます。がんであっても天寿を全うできる、天寿がんの実現です。そういう時代には、たとえがんになっても、メディカル・タウン内のメディカル・カフェへ行って相談し、専門家に治療の優先順位を付けてもらい、タウン内の病院で治療を受け、天寿を全うすることができるようになる。そうなれば、がん患者さんも落ち着きますよ。
同じカテゴリーの最新記事
- 人間は死ぬ瞬間まで生きています 柳 美里 × 鎌田 實
- 政治も健康も「あきらめない」精神でがんばりたい 小沢一郎 × 鎌田 實
- 自分を客観視する習性が、がん克服に導いてくれたのだと思います なかにし礼 × 鎌田 實 (後編)
- 人間を診ないロボット医師にいのちを預けるわけにはいかない なかにし礼 × 鎌田 實 (前編)
- 検査しないまま収監されていたら、帰らぬ人となっていたかも知れません 鈴木宗男 × 鎌田 實
- 治ると思ってがんに対峙するのと ダメだと思って対峙するのとでは全然違う 与謝野 馨 × 鎌田 實
- 病気にはなったけど 決して病人にはなるまい 田部井淳子 × 鎌田 實
- 神が私を見捨てないから 難治性乳がんにもへこたれない ゴスペルシンガー・KiKi(ゲーリー清美) × 鎌田 實
- 原稿も旅行もゴルフもできるうちは好きなようにやって生きていきたい 作家・高橋三千綱 × 鎌田 實
- 5年、10年と節目をつけ、少しドキドキしながら、娘を見守っていく 女優/タレント・麻木久仁子 × 鎌田 實


