- ホーム >
- 闘病記 >
- 医師ががん患者になったとき
孤独や不安な気持ちを支えたい がん患者のメンタル・サポートが私の最後のライフワーク・竹中文良さん
自分の心の悩みを相談できない
竹中さんはその問いに対する答えを知りたくて、退院後の2年間くらいはむさぼるように本を読んだ。しかし切羽詰まった自分の心の悩みを人に相談することはなかった。「そういう問題を他人に相談するというカルチャーがなかった」からだという。
今でこそ患者会もたくさんあるし、カウンセラーなどに相談する人も多くなってきたが、その当時は、がん患者が他人に自分の心のなかを打ち明けて相談するという習慣も仕組みもなかった。だからそもそも人に相談するという発想自体が出てこなかったのだろう。ただそのころ、竹中さんより少し前にがんにかかった医師の友人がいて、その人とは本音で話し合え、悩みも分かり合えるということには気がついていた。
「手術を受けたあと、将来の仕事に対する不安とか自分もいろいろ悩みや問題があったので、それからは手術した患者に対しては、できるだけゆっくり話を聞いて対応しようと思いました」
とはいいながら、退院後約2カ月で実際に職場復帰したら、なかなかそうもいっていられなかった。外科医の現場は毎日目の回るような忙しさで、そんなことをしている余裕などないのが現実なのだ。それが幸いした一面もある。忙しさに追われているうちに再発や死に対する不安も、いつしか後景に追いやられていったのだ。そして気がつけば手術から3年が経過していた。
「大腸がんでしたから3年たてばまず一安心。これでクリアできただろうと思いました」
ウェルネス・コミュニティーとの出合い
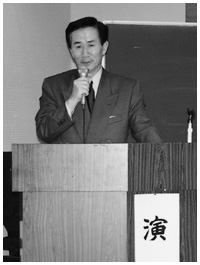
1991年11月、学会発表の場で
やがて竹中さんは日赤医療センターを定年退職するときを迎える。手術からちょうど10年後のことだ。このとき竹中さんはいくつかの病院からの誘いを断り、日赤看護大学の教授に就任した。そのしばらく前に読んだ1冊の本に感銘を受けたからだ。『内なる治癒力』(スティーヴン・ロック著、池見酉次郎監修、創元社刊)という本である。そこでは、アメリカにあるがん患者のメンタル・サポートに関わるザ・ウェルネス・コミュニティーという団体のことが紹介され、メンタル・サポートの有効性についても詳しく書かれていた。これが竹中さんとウェルネス・コミュニティーとの最初の出合いであった。
「このコミュニティーでは重症患��同士がお互いに感情的な援助を与え合い、ほとんどの人が主治医の予測より3年以上長生きしているとありました。私自身の経験も踏まえ、確かに精神的なサポートは強い影響を持つかもしれないと思ったのです。それで医療の世界に戻るのではなく、看護大学でがん患者およびその家族に対するサポート・システムの構築について研究することにしたのです」
この研究の一環で竹中さんはアメリカのサポート・システムを見る研修旅行に参加し、サンフランシスコのウェルネス・コミュニティーを実地に見る機会も得た。さらにその翌年、今度はザ・ウェルネス・コミュニティーからの提案で、竹中さんは約2カ月間現地での研修も受けた。
その結果、竹中さんはウェルネス・コミュニティーのプログラムが日本でも有効であることを確信し、がん患者のメンタル・サポートを自らの「ファイナルライフワーク」にすることを決意。JWを立ち上げたのである。
坐禅、アロマテラピーなどで心の安定を取り戻す
JWのプログラムはアメリカのそれとほぼ同じである。冒頭で紹介したサポートグループの他には、坐禅、自律訓練法、ハーブ・アロマテラピーなどを行っている。
坐禅は月に2回。京都の大徳寺の住職が指導する本格的なものだ。毎回、午前の部と午後の部があり、多いときは20畳ほどの和室に座りきれないほどの参加者がある。
自律訓練法は、心身の緊張状態を緩和することで心にかかるストレスを軽減させるのが目的だ。一般には心身症や神経症など自律神経症状の治療・予防の方法として用いられているが、日常的に再発の不安を抱えているがん患者にとっても、心の安定を取り戻すのに効果があるといわれている。これも専門家の指導のもとに行い、初心者向けと経験者向けの2コースがある。
ハーブ・アロマテラピーは、ハーブなどの自然植物が生み出す芳香の成分を利用して、肉体や精神を健康にするという自然療法の一つ。ストレスなどにより弱まっている自然治癒力を高める効果もあるといわれている。月2回開かれ、アロマテラピーアドバイザーなどの資格を持った人が講師を務めている。
「これらに共通しているのが呼吸法です。坐禅も自律訓練法も腹式呼吸もしくはそれに近い呼吸法をベースにしています。腹式呼吸をすることで副交感神経の働きがよくなり、精神が落ち着き免疫力が高まるという学説もあります」
もう一つ、JWのプログラムで大きなウエイトを占めているのがセカンドオピニオン相談だ。3人の医師ががん患者や家族からの相談に対応するもので、週に2回行っている。
実はこのセカンドオピニオン相談、JWの発足当初は行っていなかった。アメリカのウェルネス・コミュニティーのプログラムにも入っていない。その経緯について竹中さんはこう説明する。
「最初はアメリカと同じやり方をしていました。しかしグループサポートの様子がどうもアメリカとは違う。アメリカでは患者さんがいろいろなことについて話すのですが、日本では医学的な質問ばかりする人が多いのです。日本では診療時間が短く医者との対話が少ないので、患者さんが病気のことや治療のことをよく分かっていないからでしょう。そういうことをきちんと把握していない人に、心のケアだけをしても意味がありません。それでセカンドオピニオン相談をすることにしたのです。医学的なこと以外の相談にも応じるため、私を含めて3人の医師が対応しています。1人は緩和ケア医です」
アクティブな患者になるということ
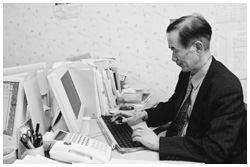
2003年12月、JWは京都大学、明海大学、野村総合研究所と協力し、インターネットを使ってがん患者の心のケアをする「3Dオンラインメディカルフォローアップ」の実証実験を開始した。対象はJWや、乳がん患者のグループ「あけぼの会」に所属する患者30人。実験では、ネット上で患者が医師とやり取りするセカンドオピニオン相談や、患者同士がチャットで会話をするコミュニティーの場を提供する。
「実験がうまくいけば全国的に広げようと考えています。そうすれば遠方の人がわざわざここまでこなくても、メンタル・サポートを受けられるようになります」
そういう竹中さんの目下の悩みの種は、JWの運営資金。アメリカのウェルネス・コミュニティーは運営資金を全額寄付でまかない、会員からは会費も入会金も取っていない。
だが日本ではそうもいかず、入会金2000円、年会費5000円を取っている。セカンドオピニオン相談などのプログラムもサポートグループ以外は有料だ。竹中さんは日赤看護大学の教授を辞めたときの退職金もすべてJWの立ち上げに投じた。
それでもここまでずっと赤字が続いてきた。
「石の上にも3年といいますから、3年もてばなんとかやっていけるだろうと思っています。でもこれ以上赤字を出すようだと、続けるのが難しくなるかもしれません」
竹中さんは手術後、抗がん剤を服用したが、気持ちが悪くなるのですぐにやめてしまった。人に勧められ*丸山ワクチンを試したこともあるが、「注射が痛いので」これも10回くらいでやめた。病気をきっかけに煙草は完全にやめ、酒量も減らした。夜も11時ころには床に就くように心がけている。しかしそれ以外、とくにしていること、気をつけていることなどはないという。
「がんになったことは運が悪かったかもしれません。しかしがんになることで必ずしも不幸になるとは限りません。私もがんにならなかったら今のようなことはしていなかったでしょう。医者を続けていたら会えなかったような人にもたくさん会えましたし、好きなことを話して北海道から沖縄まで回りました。がんを経験したおかげで人生が面白くなりましたよ」
ウェルネス・コミュニティーの考え方の基本は、アクティブな患者になるということ。竹中さんはそれを身をもって実践しているのである。
*丸山ワクチン=丸山千里日本医科大学名誉教授がヒト型結核菌からつくった免疫賦活薬。がんに対する有効性はまだ立証されていない


