- ホーム >
- 闘病記 >
- 医師ががん患者になったとき
進行前立腺がんとの闘い がんとの闘いから学んだこころの持ち方の大切さ
大病院と近所の開業医の「病診連携」が必要
私の「入院サマリー」に書かれた専門的な話はこれくらいにしておきますが、いずれにしても、私は前立腺がんの発病から15年、5回の入院、3回の手術を経て、今日に至っているわけです。そこで、私がこの15年、病院に出たり入ったりする間に感じたことを、いくつかお話したいと思います。
まず病院についてです。大学病院など大病院にはCTやMRIなど立派な医療器械や設備があり、患者にとっては非常に強力な治療の味方と考えられます。しかし一方、あまりにも強大であり、細かい行き届いた治療などを期待することは、少し困難なような気がします。大きな手術や理化学的検査を受けるには、大学病院が非常に有効ですが、小さな医療処置は、むしろ小さな病院か開業医の先生のお世話になったほうが、容易であるように思います。
私はいま開業医のお世話になっていますが、大病院と近所の開業医の両方の先生が、メールなどで相互に連絡を取っていただくことがベストだと思っています。実際、最近「病診連携」ということが言われているようです。まさに大病院と開業医が連携を取りながら医療を行うということです。
独立行政法人化により大学病院が危機的状況に
それから、これはもっと根本的なことですが、私がお世話になったのは大学病院です。最近、大学は独立行政法人になり、とにかく経済的な効率を優先し、利潤を追求しなければならなくなっています。大学の構造改革を進めるためには、それも必要かも知れませんが、医学は例外ではないかと思います。昔から「医術は仁術だ」と言われてきました。「新明解国語辞典」には「医は損得を度外視し、奉仕的に治療することが期待される医道」と解説されています。
また、大学が独立行政法人化され、職員の定員削減が行われたために、医師や看護師が非常に多忙になっている現実があります。私が外来で行きますと、診察室に教授の先生が1人だけでおられます。教授の先生がご自身でカルテを出し、診察し、カルテに書き込み、注射器を出して注射をし、伝票まで書かれます。これではミスをするのは当たり前です。私が外来で行く曜日が決まっていますが、その日は5人の泌尿器科の先生が診察されている中を、1人の看護師さんが走り回っています。こんなことは、おかしいと思います。
医師の先生も看護師さんも献身的に医療、看護に従事されていますが、あまりにも多忙で過重労働になっています。管理行政的に改善していかないと、若い良い人材が医師・看護師さん達になることを避けるようになり、もう2~3年で医療現場は大ピンチに陥るのではないかと心配しています。人材というのは、年代的に少し穴が開きますと、埋めることが難しくなるのです。それと同時に、産婦人科、小児科、外科が減っている現状も、なんとか改善していかなければならないと思います。
病院に関して、もうひとつ感じたことは、先生方の知識があまりにも専門に収斂しているという点です。私が5カ月入院したとき、足が痛くて歩けなくなったことがありました。「整形外科へ行きなさい」と言われ、整形外科でCTやレントゲンを撮ってもらったところ、恥骨が溶けてきている���とがわかりました。しかし、整形外科では原因がわからないから、薬は出せないということで、治療はできませんでした。
そういう場合、患者が入院中に併発するさまざまな問題に対応するGeneral Physicianというような立場の先生が必要ではないかと感じました。
青春のこころを持ち続け 病に負けず幸せに生きる

ここからは末期になった私が現在行っていることです。私はいま手許に、私自身と家内が署名した「終末期医療の中止を求める意思表明書」を持ち歩いています。私はいつ深刻な状態になるかもしれない状況のもとで生活をしています。しかし、終末期になったとき、人工呼吸器を付けないでほしいと思い、担当医の先生にもはっきりそのことを表明しています。
人工呼吸器というのは、一旦付けると簡単には外せません。医師が途中で外した場合、死を促進したとして訴えられる場合もあります。最近は救急車の中で人工呼吸器を付けることができるようになりました。私は絶対に拒否したいと思います。終末期を迎えたら、人工呼吸器を付けないで最期に臨みたいと思います。
私は、健康ということは、自分で呼吸ができ、水が飲め、食べられることだと考えています。酒もタバコもとうにやめましたが、美味しいものを食べることは大好きです。ですから、食べられるうちは、どんどん食べます。しかし、自分で食べられなくなったら、点滴や栄養補給はしないでほしいと思います。
5カ月間入院していたときには、点滴や栄養補給のお世話になりましたが、そのときは普通に意識がありました。しかし、意識がなく、自分で食べられなくなったら、もう点滴や栄養補給を受けるつもりはありません。昇圧薬、脳圧低下薬などの延命措置も同様です。ただ、私が痛みで苦しんでいるときに、モルヒネや麻酔で緩和措置をしていただくのであれば、喜んで治療を受けます。
最後に申し上げたいことは、人間が生きていく上で、精神的な部分が非常に大きいということです。『新約聖書』の「ローマ人への手紙」の中の一節に、「艱難は忍耐を生み出し、忍耐は練達を生み出し、練達は希望を生み出す」という有名な言葉があります。病気をしていると、さまざまな困難がありますが、忍耐してがんばっていると、次第にその苦しみから逃れる方法を見つけます。そして、それによって、先の希望が見えてくるのです。
もうひとつ、サムエル・ウルマンの「青春」という詩を私なりの訳で紹介させていただきます。
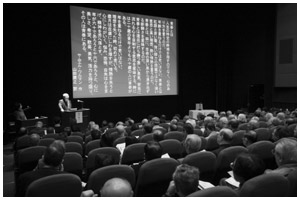
山田さん訳のサムエル・ウルマンの詩、「青春」を読み上げる
青春とは
人生の特定の時期を指すのではなく、心のあり方を言うのだ。
年齢を重ねるだけでは老いはない。
青春とは、紅顔と若い唇、強い脚力の問題ではなく、強い意思と高い理想、熱い情熱を言うのだ。
青春とは、将に、生命の深い泉から湧き出ずる新鮮さを意味するのだ。
青春とは、逡巡に打ち勝つ激しい勇気、安易に流れる心を自制する意思を意味する。時には二十歳の青年よりも六十歳の人に青春がある。
年を重ねるだけでは老いはない。
理想を失った時、初めて老いる。
歳月は皮膚にしわを増すが、情熱を失うと心にしわがいく。悩み、恐怖、自失は心をまげ、精神を芥へ落とす。
年が六十であろうと十六であろうと、心に美しさ、希望、歓喜、勇気、活力を持つ限り、その人は青春にある。
どうか皆さんも、青春のこころをいつまでも持ち続け、病に負けず、幸せに生きていただきたいと思います。
(構成/本誌編集部)


