分子標的薬ががん治療に新しい流れをもたらす これだけは知っておきたい分子標的薬の基礎知識
新しい分子標的薬の登場にイレッサの教訓を生かす
新しい分子標的薬が承認され、医療の現場に登場してくるときには、その薬が安全に使われるように十分な注意が必要となる。前述したように、分子標的薬の治療では、それぞれの薬に特有の副作用が現れてくる。そのため、新しい薬の場合には、十分に対応できない危険性があるのだ。
肺がんの治療薬として登場したイレッサは、『夢の新薬』と期待されたことに加え、内服薬という手軽さも加わり、承認直後から広く使われることになった。ところが、頻度は低いものの、間質性肺炎という重い副作用があり、死亡するケースもあったことから、大きな問題になってしまったのだ。
「イレッサの教訓を生かそうという動きは当然あります。たとえば、昨年、アバスチンが認可されましたが、イレッサのときとはまるで違っていました。まず、安全性の確認試験が行われ、データが分析されています。その確認試験では、血栓症も消化管穿孔も起きていたので、その情報もきちんと開示されています」
さらに、市販後臨床試験も行われた。最初はがん拠点病院や大学病院など、比較的がんの専門性の高い病院に限定して使用を認め、3000例の症例を集めることになったのだ。
「学会はもちろん、医薬品メーカーも、教育に相当力を入れています。安全の教育をきちんと行い、それから使ってもらおうということですね。イレッサが認可された頃の状況とは大きく変わっています。重大な副作用が出た場合には、詳細な調査を行うことになっています。さらに、重大副作用症例に関するデータも公開されています。情報を公開していくことは非常に重要ですね」
アバスチンに関しては、すでに3000例近い症例が集まり、中間報告が出されているという。イレッサの場合、欧米人に比べ、日本人には肺毒性が強く現れたが、アバスチンにはそのような傾向は見られない。現在のところ、副作用に関しては、欧米で報告されているのとほとんど同じ結果が出ているそうだ。
分子標的薬を安全に使うシステム
分子標的薬を使う場合には、安全に配慮する必要がある。まれに重篤な有害事象が起こることがあるからだ。
「化学療法薬の副作用はパターン化しているので、比較的対応しやすいのです。ところが、分子標的薬による治療となると、何が起こるのかが薬ごとに違うため、マネジメントがとても煩雑になってきます。おまけに、ほとんどが外来治療になるので、入院の場合とは違う難しさ��あります」
抗体薬は注射薬なので病院で点滴するが、外来で行うケースが増えている。小分子薬はすべて内服薬。薬を服用するのも、何らかの有害事象が起きるのも自宅ということになる。
「がん薬物療法専門医という専門医制度が始まっています。この資格を取得する段階で、分子標的薬についても相当の教育を受けているので、こういう医師であれば、まずは安心といえるでしょう。分子標的薬を使う場合、専門的な知識や経験を持つ医師と、そうでない医師では大きな実力差があると思います」
ただ、問題は専門医が足りないことだ。今年の4月で3回目の認定が行われたのだが、これまでに専門医として認定されたのは合計205人。年々増えていくが、当面は人数不足の状況が続くことになる。
専門医の不足を補うためには、地域医療連携を確立していく必要がある、と石岡さんは言う。治療方針の決定は、拠点病院の専門医が行う。その病院と連携するサテライト病院や診療所では、きちんとしたクリニカルパスを作っておき、それに従って治療を進めるのだ。こんな副作用が出たら、こう対応する。これ以上の副作用が出たら、拠点病院に送る。この程度なら、休薬や減薬の判断をする。といったことを決めておき、安全に治療を進められるようにするのだ。
「治療を担当する医師がまったく知識がないのでは無理ですが、きちんとしたクリニカルパスがあり、それなりの教育とトレーニングを受けた医師なら、問題なく治療を進められると思います」
がん治療認定医という資格も、今年からスタートしている。講習を受けるだけで取れる資格だが、サテライト病院や診療所の医師が、がん治療認定医なら安心だ。とくに専門医が少ない地方では、こうした地域医療連携が必要になるだろう。
では、分子標的薬治療を受ける場合、患者として注意すべき点はどんなことだろう。石岡さんがあげたのは次の4つだった。
(1)正しい治療を行っている施設を選ぶ
分子標的薬治療においては、医師の力量の差が大きい。正しい治療を行ってくれる病院に行くことがまず大切。
(2)セカンドオピニオンを受ける
主治医が薬物療法の専門医でない場合、自分の受けている治療が正しいかどうか、セカンドオピニオンを受けるとよい。
(3)標準医療を受ける
効果の面からも、副作用のリスクを回避する意味でも、標準治療を受けることが大切。
(4)夜間救急医療を行っている施設を選ぶ
自宅で重い副作用が起きたとき、すぐに対応してもらう必要がある。
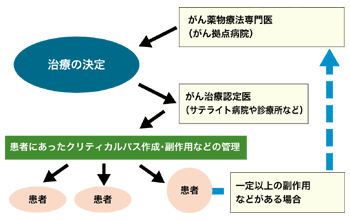
まだまだ新しい薬が登場してくるはず
分子標的薬の研究は、現在もすごい勢いで進められている。
「まだまだ新しい分子標的薬が登場してきます。どうしても、肺がん、乳がん、大腸がんといった患者数の多い分野の研究が先行しますが、これからは、あらゆるがん種について、研究が進められていくと思います。腎臓がんに対する分子標的薬が登場してきたのも、そういった流れを感じさせます。それから、第1世代の薬に続いて、第2世代、第3世代の薬も出始めています。たとえば、イレッサが第1世代だとすると、タルセバ(一般名エルロチニブ)は同じ分子をターゲットとする第2世代薬。そういった形で登場してくる新しい薬もたくさんあります」
さらに、すでに使われている分子標的薬の適応拡大も、盛んに行われることになりそうだという。それも分子標的薬治療を拡大していくことにつながりそうだ。
「ただ、課題もあります。それは、効く人と効かない人をどうやって見分けるか、有害事象の現れる人と現れない人をどう見分けるか、ということです。こうしたことを見分ける優れたマーカーがあれば、無駄な治療を避けることができるし、有害事象のリスクを回避することも可能になります。この分野の研究が進めば、○○がんならこの治療という時代は終わりを迎えるでしょう。ターゲットを絞り込んで、それにあった分子標的薬を使う時代になると思います」
分子標的薬はまだまだ発展途上の段階にあるといえそうだ。ただ、素晴らしいスピードで進歩しているだけに、今後に大きな期待が寄せられている。
同じカテゴリーの最新記事
- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!
- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント
- 世界に先駆け初承認された分子標的薬ロズリートレクの課題 共通の遺伝子変異を標的とする臓器横断的がん治療薬
- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!
- 肺がんに4つ目の免疫チェックポイント阻害薬「イミフィンジ」登場! これからの肺がん治療は免疫療法が主役になる
- 肺がん薬物療法最前線―― 分子標的薬と、オプジーボに代表される免疫チェックポイント阻害薬が、肺がん治療をここまで変えた!
- 第3世代タグリッソ登場で非小細胞肺がん治療はさらに進化
- 分子標的薬投入時期を「Window」で見える化 ホルモン陽性HER2陰性再発転移症例での適切な投与時期を示唆
- 非小細胞肺がん 耐性後は再生検を行い 適切なEGFR-TKIで治療する
- 深い寛解後に 70%が投薬中止可能~慢性骨髄性白血病の治療~


