第2段階に入った分子標的薬の長所と短所 注意しよう! 従来の抗がん剤とは異なる優れた効果と思わぬ副作用
分子標的薬同士による併用療法がスタート
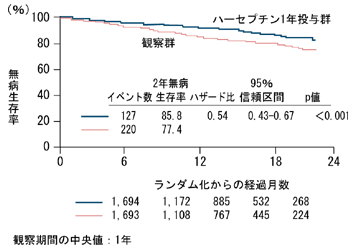
複数の分子標的薬同士による併用療法で、今最も注目されているのはHER2過剰発現の乳がんに対するハーセプチンとタイケルブによる2剤併用療法です。
「HER2は乳がん細胞の表面に突き出た上皮成長因子受容体(EGFR)というタンパクの1つです。乳がん細胞はHER2などを介した増殖シグナルの伝達によって異常な増殖が実現されるため、HER2を標的にその働きを妨げ、増殖シグナルの伝達を断ち切る分子標的薬としてつくられたのがハーセプチンとタイケルブなのです」(佐々木さん)
ただし、ハーセプチンとタイケルブの両者はいずれもHER2を標的にしているものの、HER2に対するアプローチの方法が異なります。すなわちHER2はがん細胞の表面に突き出る形で存在し、細胞の外側の部分と内側の部分に分けられます。ハーセプチンはHER2の外側の部分に結合しその働きを妨げるのですが、タイケルブは細胞の中に入りこみ、HER2の内側の部分に作用してその働きを妨げるのです。
「ハーセプチンは抗体と呼ばれる大分子化合物ですが、タイケルブは細胞の中に入りこむ小分子化合物です。ハーセプチンとタイケルブの2剤併用療法は、HER2という同じ標的に対してがん細胞の外側と内側から攻撃するため、より確実にHER2の働きを妨げて分裂・増殖を抑えることができると期待されているのです」(佐々木さん)
すでに欧米ではタイケルブとハーセプチンの併用療法の有効性を調べる臨床試験が行われています。日本でも埼玉医科大学病院で同様の臨床試験がスタートし、分子標的薬を用いたがん化学療法は新しい、ダイナミックな進歩と展開を繰り広げようとしています。
従来の抗がん剤と異なる治療効果や副作用が出現
このように、分子標的薬によるがん化学療法は飛躍的進歩を遂げていますが、その一方、従来の抗がん剤とは異なる効果や副作用などが出現し、より慎重な対応が求められるようになってきています。とりわけ、がん細胞の中に入りこみ、異常な増殖シグナル伝達を断ち切る小分子化合物の分子標的薬の場合が問題になっています。
「たとえば、『薬の効果や副作用は、日本人と外国人で多少投与量が違っていても異ならない』というのが新薬承認審査の国際的基準を定めたICH(日米EU医薬品規制調和国際会議)の原則です。しかし、イレッサやタイケルブなどの小分子化合物の増殖シグナル伝達阻害剤では、必ずしもその原則はあてはまらないことがわかってきたのです」(佐々木さん)
肺がんに対するイレッサはもともとEGFRを標的としてつくられた分子標的薬ですが、その後、EGFRから変異したEGFRを標的とした分子標的薬であることが研究で突き止められました。変異したEGFRにはいくつもの種類があり、その発現頻度は(1)アジア人、(2)女性、(3)非喫煙者、(4)腺がん(肺がん細胞のタイプ)に高く、変異したEGFRを有する肺がんは総じてイレッサが効きやすく、欧米人よりもアジア人に多いことが明らかにされています。イレッサの国際共同試験(IDEAL-1)で欧米人の奏効率が9.6パーセントにとどまったのに対し日本人の奏効率は27.5パーセントにのぼり、約3倍近くの差が認められたのは、そうした背景があったからだと考えられています。
「治療効果が日本人と欧米人で大きく異なるのは、乳がんに対する小分子化合物の分子標的薬、タイケルブでも同じことが指摘されています。昨年末、米国サンアントニオで行われた乳がんシンポジウムで、転移性乳がんに対するタイケルブの臨床試験の結果が愛知がんセンター乳腺科部長の岩田広治さんから報告されたのですが、それによると欧米人の奏効率は7~8パーセントにとどまったのに、日本人の奏効率は24パーセントと非常に高かったのです」(佐々木さん)
タイケルブについて日本人と欧米人の奏効率に大きな差があったというこの岩田さんの報告は、国際的に非常に大きな注目を集めました。タイケルブでは必ずしも標的タンパクの変異やその発現頻度の民族差、人種差によるものではないと考えられており、今のところその原因は突き止められていないものの、実際の患者さんに用いるときは慎重に配慮しなければならない事柄といえます。
がん患者が注意したい市販後調査の副作用情報
一方、小分子化合物の分子標的薬では副作用の出現頻度やその程度についても、日本人と欧米人の間で大きな差があります。イレッサによる間質性肺炎などの重篤な副作用の発症がその代表的なものです。
2002年、わが国でイレッサが発売されて以降、それによって間質性肺炎や急性肺障害を起こした肺がん患者は1631人、死亡者は643人(06年3月末現在、厚労省調べ)にのぼっています。イレッサによる間質性肺炎の発症メカニズムはまだ突き止められていませんが、確かなのはイレッサによって間質性肺炎を起こす患者が日本人に圧倒的に多いという事実です。日本医科大病院呼吸器内科教授の工藤翔二さんによると、欧米ではイレッサによる間質性肺炎の発症率が0.3パーセントにとどまるのに対して、日本では5.8パーセントにのぼり、約20倍も高いということです。
「最近は数多くの国の患者さんを対象とした新薬の国際共同試験が行われるようになりました。薬の有効性を調べるのに非常に有益なのですが、分子標的薬ではそれですべてがわかるのかというと、そうではありません。とくに日本人のデータが不十分な国際共同試験の場合、その結果だけを頼りにするのではなく、日本人を対象とした臨床試験や市販後の調査などで副作用情報などを蓄積し、すみやかに医療現場にフィードバックしていくことが求められています」(佐々木さん)
| 日本人 | 外国人 | 合 計 | |
|---|---|---|---|
| 奏効率 | 27.5 % (14人/51人) | 9.6 % (5人/52人) | 18.4 % (19人/103人) |
| 病勢コントロール率 | 70.6 % (36人/51人) | 38.5 % (20人/52人) | 54.4 % (56人/103人) |
| 症状改善率 | 48.5 % (16人/33人) | 32.4 % (11人/34人) | 40.3 % (27人/67人) |
| 効果持続期間 中央値 | 114日 (86~128日) | 57日 (55~66日) | 83日 (61~86日) |
先述のイレッサの国際共同試験では、日本人の患者は51人しか参加していませんでした。このわずかな人数から得られたデータをもとに、数パーセントの頻度で生じる副作用をあらかじめ的確に予測するのには無理があります。新薬承認前の臨床試験(治験)の対象患者さんの増員をはからなければならないことはもちろんですが、がん患者とその家族は新薬承認後の市販後の調査がきちんと行われるように厳しく求めていく必要もあるでしょう。
「ハーセプチンとイレッサは同時期に承認された分子標的薬ですが、ハーセプチンは市販後の全例登録調査(投与患者に対する効果や副作用などの使用成績調査)が承認条件とされたにもかかわらず、イレッサは承認条件とされませんでした。イレッサによる間質性肺炎で多数の死亡者が出たのは、発売元の安易な販売政策と、市販後の全例登録調査を承認条件としなかった行政の不適切な対応から生じたといえます」(佐々木さん)
イレッサと同じ肺がんの分子標的薬であるタルセバは、現在、厚労省へ承認申請されています。タルセバはイレッサと異なり臨床試験で延命効果が立証されているものの、イレッサと同様に日本人の肺がん患者には間質性肺炎を引き起こす危険性もあります。承認後の市販後調査がきちんと行われることを望まずにはいられません。
いずれにしても分子標的薬の登場によって、がん化学療法はめざましい進歩を遂げつつあります。もちろん分子標的薬の効果に着目するのもいいのですが、従来の抗がん剤と異なる思わぬ副作用が出現することも想定し、十分な注意を払いながら治療を受けていく必要があると思います。
同じカテゴリーの最新記事
- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!
- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント
- 世界に先駆け初承認された分子標的薬ロズリートレクの課題 共通の遺伝子変異を標的とする臓器横断的がん治療薬
- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!
- 肺がんに4つ目の免疫チェックポイント阻害薬「イミフィンジ」登場! これからの肺がん治療は免疫療法が主役になる
- 肺がん薬物療法最前線―― 分子標的薬と、オプジーボに代表される免疫チェックポイント阻害薬が、肺がん治療をここまで変えた!
- 第3世代タグリッソ登場で非小細胞肺がん治療はさらに進化
- 分子標的薬投入時期を「Window」で見える化 ホルモン陽性HER2陰性再発転移症例での適切な投与時期を示唆
- 非小細胞肺がん 耐性後は再生検を行い 適切なEGFR-TKIで治療する
- 深い寛解後に 70%が投薬中止可能~慢性骨髄性白血病の治療~


