第2世代の薬剤も登場。分子標的薬の長所と短所をきっちり把握しよう 分子標的薬――より効果的な使い方を求めて
劇的な効果が期待!?
そして、患者サイドからみれば、もっとも大きな成果の1つが、「これまで既存の抗がん剤では手も足も出なかったがんに対して、劇的な効果が期待できること」(佐々木さん)です。
それが、たとえば慢性骨髄性白血病やGIST(消化管間質腫瘍)に対するグリベック(一般名イマチニブ)です。グリベックが出て、この2つのがんに対する治療は一変したといってもいいでしょう。慢性骨髄性白血病の場合、グリベック治療による7年生存率は86パーセントと、それまでの治療法をはるかに上回る成績が報告されています。また、腎細胞がんや肝細胞がんは、これまで化学療法の恩恵があまりなかったがんです。腎細胞がんの場合、有効な抗がん剤がなかったので、これまではインターフェロンやインターロイキン2が使われてきましたが、奏効率は15パーセント前後と決して十分な数字ではありませんでした。しかし、がん細胞の増殖に係わる複数のタンパクを標的としたスーテント(一般名スニチニブ)やネクサバール(一般名ソラフェニブ)が登場して治療成績は大きく改善されました。スーテントはインターフェロンなどが効かなくなった患者にも34パーセントの奏効率を示し、ネクサバールはインターフェロンとの比較試験で無増悪生存期間の中央値を5カ月から7カ月に延ばすことが報告されています。
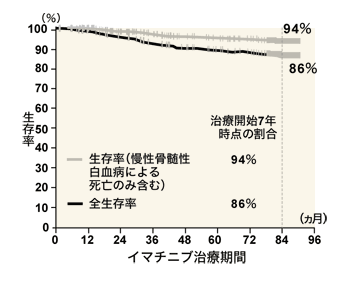
決して「夢の薬」ではない
しかしその反面、決して分子標的薬が「夢の薬」ではないこともはっきりしてきました。確かに、従来型の抗がん剤にあったような副作用は分子標的薬には少ないのですが、多彩な副作用が出現することがわかってきたのです。これは、肺がん治療薬として認可されたイレッサ(一般名ゲフィチニブ)が、間質性肺炎を起こし、大きな薬害を招いたことで、広く知られるところとなりました。ハーセプチンの場合は心毒性が出ることがありますし、アバスチン(一般名ベバシズマブ)は胃腸など消化管の穿孔(穴があくこと)を起こすことがあります。他にも、皮疹や血栓、高血圧など、これまでの抗がん剤ではなかったさまざまな副作用が現れることがわかったのです。
そこで、佐々木さんは「こうした多彩な副作用に迅速に対処するためには、がんの専門家だけでは間に合いません。心臓内科や血管外科、腎臓内科、神経内科、内分泌内科など、がん以外の専門家を充実させることが急務」と語っています。実際に、アメリカのがん専門病院は周囲に総合病院があり、協力体制をとっているところも多いそうです。その点、がんセンターと心臓血管センター、救急センターを持つ埼玉医大国際医療センターは、2キロ離れた大学病院も含め、各科の連携が可能という点で1歩先んじているといえます。そして、こうした他科の医師との連携は「がん治療全体の問題として整備が必要になっている」と佐々木さんは指摘します。患者の高齢化が起きているからです。
日本は、先進国の中でもっとも急激に高齢化が進んだ国です。
「今は、80歳の高齢者がふつうにがん治療に来る時代です。これまでのがん治療のガイドラインは、若くて全身状態がよい患者を対象に作られたもの。今、ガイドラインにのっとって治療ができる患者さんは半分ぐらいしかいないのです」
つまり、ガイドラインのよりどころである大規模臨床試験などのエビデンス(科学的根拠)と実際の患者さんの層との間に乖離が生じているというのです。
たとえば、アバスチンやネクサバール、スーテントは高血圧を引き起こす危険があります。高齢者にはもともと高血圧の方が多い上、さらにがん治療で血圧が上昇する危険もあるのです。人工透析を受けている人も免疫の低下からがんになりやすいといいます。こうした高齢や持病によるハンディを抱えた人をどう治療し、副作用にどう対処するか、これも今の日本が抱える大きなテーマなのです。
| 従来の抗がん剤 | 分子標的薬 | |
|---|---|---|
| 作用の仕組み | DNAなどの合成や修復、細胞の分裂・増殖過程に作用し、がん細胞を殺す | がん細胞の増殖や転移などに関わる分子を標的に阻害し、がんの増殖を抑えたり、進展を阻害する |
| がん細胞への特異的作用 | 低い | 高い |
| 抗腫瘍効果 | 期待 | 期待 |
| 種類 | アルキル化剤 抗生物質 代謝拮抗剤 植物アルカロイド | 血管新生阻害剤 シグナル伝達阻害剤 細胞周期調節剤 抗体製剤 |
| 長期投与 | できない | できる |
| 副作用(全般) | 重篤なものが多い | 従来にない副作用 |
| 骨髄抑制 | 高頻度 | 出るのと出ないものがある |
| 心毒性、腎毒性、脱毛、口内炎 | 高頻度 | 薬により特徴的な副作用 |
| 悪心・嘔吐 | 高頻度 | 消化器症状が出る場合も |
欧米とアジアで奏効率に差
そして、分子標的薬で明らかにされたのが「人種による効果や副作用の違い」です。
「これまでアジア人のがん治療には、欧米人のデータが無条件に受け入れられてきましたが、今は製薬メーカーでもそれは違うと認識しはじめています」と佐々木さん。標的分子によって、効果の現れ方も違うのです。たとえば、イレッサはEGFR(上皮成長因子受容体)をターゲットにした分子標的薬です。ところが、実際には変異したEGFRがターゲットになっていることがわかりました。「東洋人、女性、非喫煙者、腺がん」という条件に該当する人に、イレッサが効きやすいのも、こうした人に変異したEGFRが多いからと見られています。欧米人と日本人では、奏効率が3倍(9.6パーセント対27.5パーセント)も違うのです。逆に、間質性肺炎の発現率も日本人は欧米人の20倍も高いことがわかっています。
分子標的薬にも、抗体薬のように高分子の薬と、イレッサやタイケルブ(一般名ラパチニブ)など、小分子化合物で細胞内の増殖シグナルの伝達を阻害する薬があります。こうした人種差は、後者ではっきりと現れています。転移性乳がんを対象に開発されたタイケルブの場合も、欧米での奏効率が7~8パーセントだったのに対し、日本では24パーセントと報告されています。そのため、「一部の研究者は、グローバルスタディへの参加を強調するあまり、安全性をみる第1相臨床試験は、欧米と別にアジアで行う必要はないと発言してきましたが、日本はアジアのリーディングカントリーとして、もっと頑張ってデータを出していかないといけないのです」と佐々木さんは語っています。
これまで、ドラッグラグは日本の患者さんにとって大きなロスと考えられてきましたが、日本人における安全性確認の重要さがわかった今、最低限のタイムラグができても日本人の安全性を確認する必要があるといえるのです。
同じカテゴリーの最新記事
- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!
- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント
- 世界に先駆け初承認された分子標的薬ロズリートレクの課題 共通の遺伝子変異を標的とする臓器横断的がん治療薬
- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!
- 肺がんに4つ目の免疫チェックポイント阻害薬「イミフィンジ」登場! これからの肺がん治療は免疫療法が主役になる
- 肺がん薬物療法最前線―― 分子標的薬と、オプジーボに代表される免疫チェックポイント阻害薬が、肺がん治療をここまで変えた!
- 第3世代タグリッソ登場で非小細胞肺がん治療はさらに進化
- 分子標的薬投入時期を「Window」で見える化 ホルモン陽性HER2陰性再発転移症例での適切な投与時期を示唆
- 非小細胞肺がん 耐性後は再生検を行い 適切なEGFR-TKIで治療する
- 深い寛解後に 70%が投薬中止可能~慢性骨髄性白血病の治療~


