食事と運動の重要性を示したエビデンスも がん治療の効果を高めるためにも食事は重要!
治療と同時に食生活も重視したい
がんの治療を受けている場合、食事内容が治療効果や副作用に影響することがある。次のような研究があるそうだ。
乳がんで転移があり、化学療法〈5-FU+ファルモルビシン(一般名エピルビシン)+エンドキサン(一般名シクロホスファミド)〉を受けている患者さんを対象に、DHA(ドコサヘキサエン酸)が効果や副作用にどう影響するかを調べた試験がある(09年)。DHAは魚の脂肪に豊富な成分だが、この試験では、1日1800ミリグラムをカプセルで投与している。投与期間は化学療法開始前の7~10日間と、化学療法中の5カ月間。DHAが血中に多く取り込まれた「高DHA群」と、取り込み量が少なかった「低DHA群」で比較が行われた。
その結果、無増悪期間中央値は、高DHA群が8.7カ月、低DHA群が3.5カ月。全生存期間中央値は、34カ月と18カ月だった(図7)。高DHA群の人たちは、治療効果が高く、がんの進行が抑えられ、生存期間も延長したのだ。
副作用に関しては、高DHA群は、好中球減少、貧血、血小板減少などで、低DHA群より軽い傾向を示した。
「治療効果を高めようとすると、治療を優先して考えがちです。しかし、食生活も重要と考えられる結果になっています」
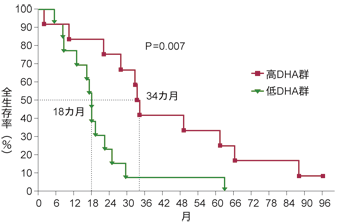
低栄養では化学療法の副作用が増強
化学療法に関しては、低栄養だと副作用が増強することを証明した研究も報告されている(08年)。非小細胞肺がんで化学療法〈タキソール(一般名パクリタキセル)+ランダ/ブリプラチン(一般名シスプラチン)〉を受けている患者さんを対象に、栄養状態と副作用の関係を調べた研究である。
その結果、低栄養の指標である血中アルブミンが低い患者さんや、栄養異常がある患者さんは、栄養状態に問題のない患者さんに比べ、副作用が増強することが明らかになった。
「抗がん剤は体にとって明らかな毒物です。それから体を守るためには、きちんと栄養をとっておく必要があります。また、最近は薬の効果や副作用と遺伝子異常を調べる研究が盛んですが、検査が一般的ではありません。この研究が明らかにしたように、簡単な検査で副作用を予測できれば、臨床現場でおおいに役立つと思われます」
ビタミンEの摂取が、放射線療法の副作用や効果にどのような影響を及ぼすかを調べた研究もある(05年)。この研究では、頭頸部がんで放射線療法を受ける人を対象に、ビタミンE(αトコフェロールを1日400国際単位)とβカロテンを3年間摂取する群(βカロテンは研究途中で中止)と、プラセボ群に分け、放射線療法の副作用と効果について比較が行われた。放射線療法の副作用としては、口腔粘膜の障害があるが、活性酸素などラジカルと呼ばれる物質が原因と考えられている。そこで、抗酸化作用を持つビタミンEが、副作用軽減に役立つと考えられたわけだ。
研究の結果、「ビタミンE投与群」は、「非投与群」に比べ、放射線療法実施中の副作用が軽くなることが確認された。ところが、その後追跡調査を行ったところ、生存率では有意差はないものの、投与群のほうが低くなる傾向を示していたのだ(図8)。
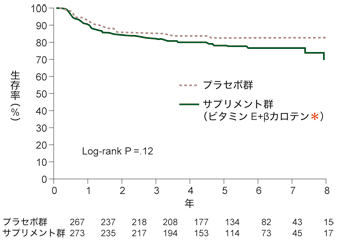
*βカロテンは研究途中で中止
「放射線の効果は、主に活性酸素などのラジカルの作用で現れます。ビタミンEでそれを除去したことにより、副作用は軽くなったけれど、効果も弱まってしまったわけですね」
この研究により、高用量のビタミンEを3年間にわたって服用することは、生存率を考えればむしろマイナスであることが示唆されたことになる。
サプリメントの摂取では十分な効果は得られない
必要な栄養を効率よく摂取するには、サプリメントを利用するのが効率的なように思える。しかし、実際にはなかなかうまくいかないことが多い。たとえば、野菜や果物を多く食べることが、がんのリスクを低下させるというデータがある。しかし、野菜や果物に含まれるβカロテンやビタミンCを、サプリメントで摂取しても、狙った効果は得られないことが多いのだ。
抗酸化サプリメントの効果をメタ分析という方法で評価した研究がある(05年)。βカロテン、ビタミンA、ビタミンE、ビタミンC、セレニウムといった抗酸化物質のサプリメントについて、「投与群」と「プラセボ群」に分けて比較した信頼性の高い研究を集め、データを統合して分析したのだ。
その結果、いずれのサプリメントもがん予防の効果はなく、βカロテン、ビタミンA、ビタミンEに関しては、投与群の死亡率が高くなるという結果になった。ビタミンCとセレニウムは、死亡率には影響がなかった。
ビタミンサプリメントのがん予防への影響を調べた研究もある(08年)。マルチビタミン、ビタミンC、ビタミンE、葉酸のサプリメントの使用状況と、喫煙状況と、肺がんの発生との関連を調べたものだ。
その結果、マルチビタミン、ビタミンC、ビタミンE、葉酸のサプリメントを使用しても、肺がんの発生率は低下しないことがわかった。それどころか、ビタミンEに関しては、1日の摂取量が100ミリグラム増える毎に、わずかながら肺がんのリスクが高まるとの結果が出た。
「これらの研究結果を考えると、食事で不足する栄養を補うためのサプリメント利用はいいとしても、がんを防ぐためにサプリメントで栄養を大量摂取することは勧められません。βカロテンを豊富に含む野菜を食べることと、サプリメントで大量のβカロテンを摂取することは同じではないと思われます」
安易にサプリメントに頼らずまずは食事から
瀬戸山さんは、サプリメントを利用する意味があるのは、次のような場合だという。
- 食事が不十分で、検査によって栄養(ビタミンDやB2)の不足が明らかなとき。
- 栄養の摂取状況が推奨されるレベルより低いとき。
- 骨の健康のためにカルシウムやビタミンDが必要なとき。
- 妊娠を考えている女性や妊娠中の女性で、葉酸を必要としているとき(ただしがん治療に問題ない場合)。
- がん治療に関連する骨減少などの合併症があるとき。
「がんの患者さんでも、食べることができるのであれば、食物から必要な栄養を摂取するのが理想的です。サプリメントが有用なのは、食物から十分な栄養をとれない場合だと考えていいでしょう」
最後に瀬戸山さんはこう語る。
「がん治療でも食事(栄養摂取)や運動などの健全な生活が重要になると思われます。
がん治療だけに大きな期待をするのではなく、適切な食事や運動を行って、よりよいがん医療を受けていただきたいと願っています」
同じカテゴリーの最新記事
- 高血糖や肥満は放っておかない インスリン増加とがん化促進の関係がわかってきた
- 腸内細菌、歯周病菌が大腸がんの進行にも関与⁉︎ 大腸がん再発予防は善玉菌を減らさない食事とリズム感ある生活で
- 高齢進行がん患者の悪液質を集学的治療で予防・改善 日本初の臨床試験「NEXTAC-ONE」で安全性と忍容性認められる
- 第3回(最終回)/全3回 夫が命をかけて私に残してくれたもの
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 第2回/全3回 〝噛めなくてもおいしく食べられるごはん〟 アイデアが次々に沸いてきた!
- 第1回/全3回 ある日突然、夫が普通のごはんを食べられなくなった――
- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 栄養補助食品を利用して食べる意欲へつなげる


