症状を抑えることで生存にもよい影響が がん患者をやせ衰えさせる「悪液質」には適切な栄養管理を!
悪液質で失われる栄養素
もちろん、過剰な水分やエネルギーの投与を抑える一方で、必要な栄養素の投与を行います。悪液質の患者さんに必要な栄養素とは何かというと、がんやその治療で失われる栄養素だといいます。
「がんは自分が生きるために独特のエネルギー供給のための代謝サイクルを持っています」
東口さんによると、このサイクルを働かせるために放出されるのがサイトカインや生理活性物質であり、その結果、脂肪は分解されるし、肝臓に内蔵されるグリコーゲンも分解され、患者さんの筋肉もどんどん弱っていきます。
細胞のエネルギー生産システムは、栄養として摂取したグルコース(ブドウ糖)、脂肪酸やタンパク質(アミノ酸)を分解してATP(アデノシン3リン酸)を作り出す代謝過程を経てエネルギーを生み出します。欠かせないのはビタミンB群であり、補酵素のコエンザイムQ10、亜鉛、脂肪酸代謝にかかわるL-カルニチン、それと分岐鎖アミノ酸(BCAA:バリン、ロイシン、イソロイシンの総称)などですが、悪液質になるとこれらがどんどん減っていきます。
終末期の患者さんの足腰が立たなくなるのは、筋肉が崩壊するだけでなく、“ 原料不足” によって細胞でエネルギーがつくれなくなるからです。 また、老廃物の代謝が困難となり、そのために体はだるくなり、吐き気や食欲減退で食べられなくなり、髪の毛は抜けるし肌はボロボロ。そんな自分の姿を鏡で見て、心も病むようになる――という悪循環に陥るのです。
それなら、たとえば足りなくなったBCAAを補ってあげたらどうかというと、たしかにBCAA投与によって筋タンパクの崩壊を抑えることができます。さらにアルブミンなどのタンパク質の合成も増えるようになります。
ほかに、蓄積した乳酸をエネルギーに変換して倦怠感を改善するため、クエン酸の投与が有効です。また、亜鉛や銅といったものも重要な役目をしていますが、これらをバラバラではなく、まとめて投与すると、いったん止まりかかっているエネルギーの生産サイクルが再び動き出します、と東口さんは語ります。
このような考え方に立って、BCAAやコエンザイムQ10、L-カルニチン、亜鉛、クエン酸などを配合した栄養機能食品(「インナーパワー」という商品名で発売)を開発。治療に役立てているといいます。
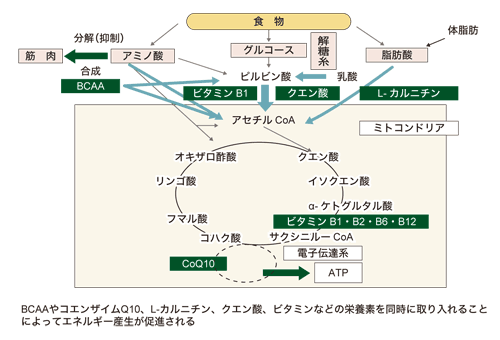
EPA食品の効果は?
イワシやサバなど青背の魚に多く含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)というオメガ3系不飽和脂肪酸も有効とされています。
EPAは血液の循環をよくするなどの効用がいわれていますが、炎症性サイトカインであるインターロイキン6の産生を抑制して筋タンパクの崩壊を抑える働きがあるとして、悪液質の患者さんに用いられています。
「オメガ3系脂肪酸は、タンパクの喪失を抑制してくれるというのでヨーロッパなどを中心に使われています。私も悪液質にいたる前段階なら、オメガ3系が有効と考えています」
日本では「プロシュア」などの商品名で販売されています。
薬によるアプローチも研究中
一方、薬によるアプローチはどこまで進んでいるでしょうか。
食欲に関連するホルモンとして、脂肪組織から分泌されるレプチンと、胃から分泌されるグレリンがあります。両者は反する作用を持ち、「もうおなかがいっぱい」と満腹信号を発信するのがレプチン。これに対してグレリンは「もっと食べたい」と食欲増進の働きをします。
そこで、悪液質の患者さんに抗レプチン薬を与えれば、「おなかいっぱい」の信号が出なくなってもっと食べるようになるし、グレリンを投与すれば食欲がモリモリと湧いてくるのではないかと、研究が進んでいます。
このうちグレリンについては、そろそろ臨床試験が行われるような段階だそうです。
カロリーをちゃんととりなさい
東口さんが強調するのは、まずはカロリーをちゃんととりなさい、ということです。
「好きなものでも何でも結構です。偏ってもいいからまず食べられるものを食べてください。ケーキが好きなら毎日ケーキでもかまいません。基本的に日本人の食事はバランスがとれているので、多少、偏食をしてもそれほどひどくはならない。だからまず自分が食べたいものを食べて、きちんとエネルギーを供給することが大切です」
そこから1歩進んで、がん治療をもっと効果的にしようと思ったら、専門家に相談してほしいと東口さん。最近は、全国の1500を超える医療施設に栄養サポートチーム(NST)が設置されるようになったので、積極的に利用するといいでしょう。
適切な栄養管理を行えば、患者さんのQOL(生活の質)向上につながるだけでなく、予後にもプラスになります。
70歳の喉頭がん患者Aさん(男性)の例では、首が腫瘍で倍ぐらいに腫れ上がり、肺転移もあって寝たきりとなり、余命1カ月といわれたものの、東口さんの所に入院後、きちんとした栄養管理を行った結果、徐々に回復し、ついには歩けるようにまでなりました。さらに在宅医療にて帰宅できるまでになり、ご自宅で奥さんと毎日、お風呂に入るようになり、残された人生を堪能されて5年後にお亡くなりになりました。
「それまで新婚時代も含めて一緒にお風呂に入るなんてことはなかったのに、5年間、毎日お風呂に入れて幸せでした」とは奥さんの言葉です。
そこで東口さんから患者さんへのアドバイス。
「もっと自分を、自分の健康な部分を信じてほしいですね。たとえがんであっても、そのがん以外の健康な部分をどうやって鍛えるかが重要です。Aさんのように、抗がん剤も効かなくなり、余命1カ月といわれた人でも5年間も長生きしました。その間、われわれは何をしたかというと、健康な部分にしっかりとエネルギーなど必要なものを投与して、悪液質などの症状が出ないようにしてあげただけです。そうして毎日3度のごはんを食べて、食べられなかったら別の栄養素をとってもらうようにして、痛みもなるべく起こさないようにしてあげることで、長生きできるものなのです。
Aさんのような亡くなり方こそ、年齢を超えた天寿といえるのではないでしょうか。70歳であろうと50歳であろうと、本人も家族も十分に生きた、納得した、と思える人生こそ大切です。それをサポートするのが“ 食” の役目だと思います」
同じカテゴリーの最新記事
- 高血糖や肥満は放っておかない インスリン増加とがん化促進の関係がわかってきた
- 腸内細菌、歯周病菌が大腸がんの進行にも関与⁉︎ 大腸がん再発予防は善玉菌を減らさない食事とリズム感ある生活で
- 高齢進行がん患者の悪液質を集学的治療で予防・改善 日本初の臨床試験「NEXTAC-ONE」で安全性と忍容性認められる
- 第3回(最終回)/全3回 夫が命をかけて私に残してくれたもの
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 第2回/全3回 〝噛めなくてもおいしく食べられるごはん〟 アイデアが次々に沸いてきた!
- 第1回/全3回 ある日突然、夫が普通のごはんを食べられなくなった――
- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 栄養補助食品を利用して食べる意欲へつなげる


