これまでの食事を見直し改善していくことは大切 がんになってからの食事療法は何がよいか
低脂肪食で再発が減った
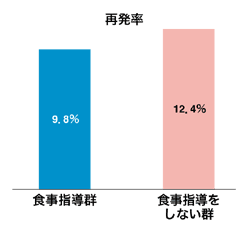
・脂質エネルギー比 15%が目標の低脂肪食
結果
・食事指導群の再発率は9.8%と有意に低下している〔再発率の危険性(相対リスク)が24%減った〕
・1年後の脂質エネルギー比
食事指導群20.3% vs しない群29.2%
・1年後の体重
食事指導群70.6kg vs しない群72.8kg
2007年には、乳がんの患者を対象にした興味深い2つ報告されているという。どちらもアメリカで行われた研究だ。
1つめの研究は、手術後の乳がん患者2437人(ステージ4や3Bなど末期の人は含まない)を対象としている(図1)。この人たちをランダムに低脂肪食の食事指導群(975人)と食事指導をしない群(1462人)に分けた。
がん患者の脂質エネルギー比(摂取エネルギーに占める脂質エネルギーの割合)は30パーセント程度の高脂肪だが、食事指導群は15パーセントを目標に低脂肪食を指導している。これで60カ月間の追跡調査を行ったところ、食事指導群の再発率が低下するという結果が得られたのである。食事指導をしない群の再発率は12.4パーセント、食事指導群は9.8パーセント。ぎりぎりのところで有意差があるという。
「脂質エネルギー比を見ると、食事指導群では目標の15パーセントにはなっていませんが、20.3パーセントでした。アメリカ人の平均から見ると、かなり脂肪を減らした食事だったことになります。それに対して、食事指導をしない群は29.2パーセント。脂質エネルギー比に大きな差があったことになります。ただ、体重も食事指導群のほうが2キログラム余り低くなっているので、低脂肪食の効果なのか、減量の効果なのか、はっきりしないというのが、問題点といえば問題点かもしれません」
この研究はきわめて画期的なものだったという。なぜなら、がんになってからの食事療法で、再発率や生存率が改善することを実証した初めての大規模試験だったからだ。ところが、この研究が出てから半年もたたないうちに、もう1つの研究結果が報告されたのである。
低脂肪食を施しても徹底しないと効果があがらない
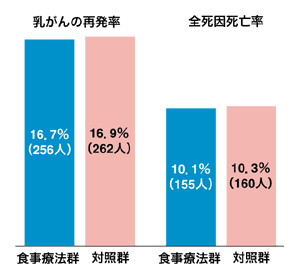
両群ともほとんど差がなかった
こちらの研究は手術後の早期乳がん患者3088���を対象にしている。この人たちをランダムに食事療法群(1537人)と食事療法をしない群(1551人)に分け、食事療法群には、「野菜・果物・食物繊維を多く食べ、脂肪を制限する食事療法」を指導した。こうして、平均7.3年の追跡調査を行い、両群の乳がん再発率や全死因死亡率を調べたのだ。その結果は、どちらもほとんど変わらないというものだった(図2)。つまり、前に紹介した大規模試験とは、矛盾する結果になってしまったのだ。
この研究の脂質エネルギー比は、食事療法群が27.1パーセント、食事療法をしない群が31.4パーセントになっている。前に紹介した研究ほどはっきりした差にはなっていない。つまり、食事指導は行ったが、十分に低脂肪食を達成できなかったために、効果が現れなかった可能性がありそうだ。また、体重は、食事指導群が74.2キログラムで、食事療法しない群が74.1キログラム。体重が減少しなかったことも、効果が現れなかった原因になっているのかもしれない。
乳がんになった人を対象にした食事療法の大規模試験が2つ行われ、一方では「低脂肪食が再発率を下げる」ことが明らかになり、もう一方では、「食事療法が再発率も死亡率も改善しない」ことが明らかになった。どう解釈すればいいか難しいところだが、これが研究の現状である。
3時間の運動で乳がんの死亡率は半分に
前向きコホート研究でも、興味深い結果が報告されているそうだ。
2005年には、乳がん患者を対象にして、運動が死亡率を低下させることを明らかにした追跡調査の結果が報告された。乳がんと診断された2987人を対象にした研究で、余暇における運動量を調べ、平均8年間の追跡調査を行ったのだ。食事療法ではないが、日常生活の改善でどのような効果が現れるかを調べた研究として興味深い。
運動の種類は、ウォーキング、ジョギング、水泳などさまざまだが、エネルギー消費量をウォーキングの時間数に換算することで、運動量を比較できるようにした。
その結果、「週1時間未満群」の乳がん死亡率を1.00とすると、「週1~2.9時間群」の死亡率は0.90、「週3~4.9時間群」は0.50、「週5~7.9時間群」は0.56、「週8時間以上群」は0.60となった。運動することで、乳がんによる死亡率が低下するという結果だった(ただし、この研究1つで「明らかになった」わけではない)。
「この結果から、週に3時間以上のウォーキングに相当する運動をすると、乳がん死亡率が半分くらいになることがわかります。ただ、がんばって5時間以上にしても、死亡率はそれほど変わらないということですね」
このような前向きコホート研究では、各群に偏りが生じることがある。たとえば、がんと診断された後にたくさん運動している人は、運動していない人に比べ、もともとよく運動していたかもしれないし、食事も健康的かもしれない。そういう影響を完全には除外できていない。このあたりが前向きコホート研究の弱点でもある。
2007年には、大腸がんの患者を対象にした前向きコホート研究も報告されている。北米の手術後の進行結腸がん患者1009人を対象にした研究で、平均5.3年間の追跡調査を行ったものだ。
この研究によると、牛肉や豚肉、デザート、乳製品、フライドポテトなどを多く食べる欧米風の食生活をしていたグループは、食事指導群に比べ、再発率が2.85倍になったという。がんの患者を対象にした前向きコホート研究としては、ごく新しいデータである。この研究からも魚油を除く動物性脂肪の摂取はがんの再発にかなり影響するといえるだろう。
罹患予防の研究結果も参考にするとよい
2003年にアメリカ対がん協会が出した指標を基本に、最新の研究成果を加えたとしても、がんになってからの食事療法に関して、科学的に推奨されることはさほど多くない。けれども、健康体重を維持する、運動を増やす、脂肪(とくに飽和脂肪酸)の摂取を減らす、野菜や果物の摂取を増やすなどが、がん患者とって重要であることにかわりはない。
健康な人ががんになるのを防ぐ罹患予防に関しては、はるかに多くの研究が行われてきた。そうした情報も参考したほうがよい、と坪野さんは言う。
「がんになってからの再発予防と、健康な人の罹患予防では、食事療法の内容が異なる可能性はあります。しかし、現在の段階では、がんの発生から進展にいたる段階で、どの栄養素がどのように働くのかということは、ほとんどわかっていません。そういう状況ですから、すでにがんになっている人が、罹患予防の情報も参考にするのは、それなりに意味のあることだと思います」
罹患予防の食事の指標となるのは、2003年にWHO(世界保健機関)が出した食べ物とがん予防に関する判定だという。ぜひ表4も参考にしてほしい。
また、2007年11月には、ワールド・キャンサー・リサーチ・ファンド報告書の第2版が刊行されることになっている。10年ぶりの改訂だが、そこには、がんの罹患予防と再発予防に関して、信頼性の高い最新の情報が網羅されることになるという。がんになってからの食事療法に関心を持つ人にとって、重要な情報源になることは間違いない。
| リスクを下げる | リスクを上げる | |
|---|---|---|
| 確実 | 運動(結腸がん) | 肥満(食道がん・大腸がん・乳がん・子宮体がん・腎臓がん) アルコール(口腔がん・咽頭がん・喉頭がん・食道がん・肝臓がん・乳がん) アフラトキシン(カビ毒)(肝臓がん) 塩漬魚(鼻咽頭がん) |
| おそらく確実 | 野菜と果実(口腔がん・食道がん・胃がん・大腸がん) 運動(乳がん) | 加工肉(大腸がん) 塩と塩漬食品(胃がん) 熱い飲食物(口腔がん・咽頭がん・食道がん) |
| 可能性に留まる/ 根拠不十分 | 食物繊維、大豆、魚類、n-3脂肪酸、カロテノイド、ビタミン(B2、B6、B12、C、D、E)、葉酸、カルシウム、亜鉛、セレン、非栄養性植物機能成分(含硫化合物、フラボノイド、イソフラボン、リグナン等) | 動物性脂肪 多環芳香族炭化水素 ニトロサミン |
同じカテゴリーの最新記事
- 高血糖や肥満は放っておかない インスリン増加とがん化促進の関係がわかってきた
- 腸内細菌、歯周病菌が大腸がんの進行にも関与⁉︎ 大腸がん再発予防は善玉菌を減らさない食事とリズム感ある生活で
- 高齢進行がん患者の悪液質を集学的治療で予防・改善 日本初の臨床試験「NEXTAC-ONE」で安全性と忍容性認められる
- 第3回(最終回)/全3回 夫が命をかけて私に残してくれたもの
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 第2回/全3回 〝噛めなくてもおいしく食べられるごはん〟 アイデアが次々に沸いてきた!
- 第1回/全3回 ある日突然、夫が普通のごはんを食べられなくなった――
- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 栄養補助食品を利用して食べる意欲へつなげる


