何か1つだけを食べてもダメ。バランスのとれた食生活が大切 未精製の穀物、野菜ががんの予防、再発防止につながる
未精製の穀物に含まれる人間に必要な栄養分
人間の長い間の食生活の基本に戻る食事療法は、がんの予防、がんの再発防止に適している。未精製の穀物主体の食事にし、野菜や海草をしっかり摂り、肉や乳製品はほどほどにする。これが食事療法の基本と言っていい。
世界がん研究基金が1997年に「がん予防のための提言」を行っている。その中で、食生活に関しては、精製度の低い炭水化物、野菜・果物・豆類を積極的に摂り、砂糖、アルコール類、肉類、動物性脂肪、塩分などは控えめにすることが提言されている。
また、ハーバード大学のウォルター・ウィレット教授が、2001年に作成した「ハーバード大学健康食事ピラミッド」(図1参照)でも、まず、運動をして体重をコントロールすることを重視した上で、積極的に摂るべきは、未精製の穀物・植物性オイル、野菜・果物、ナッツ・豆類、魚・鶏・卵の順になっている。
逆に、赤肉・バター・白米・白パン・ジャガイモ・パスタ・菓子類はできるだけ少なく、乳製品・カルシウムなどはほどほどにと位置づけられている。
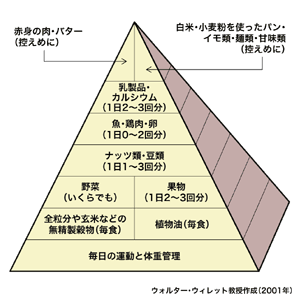
- 体重に注意する
- よい脂肪を多く摂り、悪い脂肪を少なくする
- 精製した炭水化物をより少なく、全粒の炭水化物をより多く摂る
- 健康によいタンパク質を選択する
- 野菜と果物はたくさん摂り、ジャガイモは控える
- アルコールは適量を
- 複合ビタミン剤を念のため摂る
The Harvard Medical School Guide to Healthy Eating 2001、WC Willett 『太らない、病気にならない、おいしいダイエット ハーバード・メディカル・スクール公式ガイド』ウォルター・ウィレット著(光文社)
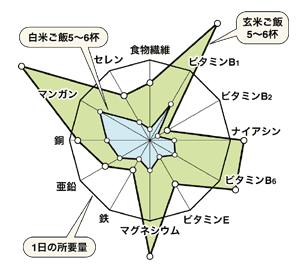
玄米は白米に比べマンガンなどの微量栄養成分が豊富
加藤さんは、「こうした提言は、疫学という研究成果から言われており、未精製の穀物や野菜が健康全般に良いことは、国際的なコンセンサスとなっています。がん患者であっ���も普通に生活ができ、食事が摂れる場合は、こうした健康によい食生活をするのが基本です」とアドバイスする。
そして、「なぜ未精製の穀物が大事かと言えば、そこからビタミン、ミネラルなど、人間の健康に必要な栄養分が摂取できるからです。玄米を主食にすれば、多くの種類の微量栄養成分は主食で補えます(図2参照)から、おかずの内容に悩まなくて済みます。つまり、食事の量も少なくて済み、肥満防止にもなるのです」と付け加える。
野菜は火を通すとビタミンやミネラルが壊れるから、生野菜で食べる人も少なくないが、加藤さんは「火を通さないと、量がかさばって大変です。多少ビタミンが壊れても、火を通してでも量的に多く食べたほうがいいと思います」と言う。
ライ麦入りの黒パンが常識になったドイツ
また、食生活の基本として、よく噛むことも大切だ。加藤さんは20回噛むことを奨めている。健康時には4~5回噛むだけで飲み込んでしまうが、病気の場合は20回ほど噛んだほうが胃に入る量が少なくなり、消化にもいい。
「特に玄米などは、白米に比べて堅いので、何回も噛まないと消化しません。肥満の患者にとっては、玄米をよく噛んで食べれば、食べる量は少量で済みますし、よく噛まないと消化されませんから、玄米は一石二鳥です」と、加藤さんは玄米食を推奨する。
もちろん玄米でなくても、麦飯でも胚芽米でもいいし、雑穀を入れて炊くのもいい。加藤さんは今年9月にドイツを視察した。「ドイツでは白いパンでなく、ライ麦の入った黒パンを食べるのが、一般的な常識になっていました」と言う。砂糖も白砂糖より黒糖がいいようだ。
白米や白砂糖に代表されるように、文明の進歩にともなって、人間は食物をどんどん純粋化して食べる方向に進んできた。そうしたほうが美味しいと言われてきた。しかし、「それは、動物としての人間の本来の食生活に合っていないのかも知れません」と加藤さんは推測する。
「人間はもともと食べ物からさまざまな微量栄養成分を取り込んでいました。しかし、食べ物を純粋化する過程で、多くの微量な栄養成分がそぎ落とされます。それが健康を害する1つの要因になっていると、十分考えられます」
例えば、白米を食べるようになって、微量の栄養分がそぎ落とされたために、ビタミンB1が欠乏して脚気になる。そこで、白米を食べながら、欠乏したビタミンB1は別の方法で摂取するという方向に進んできた。
しかし、ここ10~20年の間に、世界がん研究基金にしても、ウィレット教授にしても、原点に戻って未精製の穀物を摂ることによってビタミンを補うという、人間本来の食生活にそった考え方に変わってきている。
こっそりと下ろされた「1日30品目」の看板
この流れは、日本では「玄米菜食」「穀物菜食」「自然食」「正食」などとも呼ばれている「マクロビオティック」に通底する。もともとマクロビオティックは和食にルーツを持ち、1970年代にアメリカで見直された食事法で、最近では日本に逆輸入された形になっている。
加藤さんは20代の頃からマクロビオティックの考え方に共感を覚え、関心を持ち続けてきた。その後、さまざまな臨床的統計が出され、玄米など未精製の穀物が健康に良いということが、世界の公的機関から提言されるようになった。だから、加藤さんは「この30年間、私の栄養に対する考え方にブレはありません」と胸を張る。
結局、食事療法といっても、何か1つのものを食べればいいというものではない。
「健康とはそんな単純なものではありません。大事なことは、いかにバランスのとれた食事をするかということです。人間の身体は許容量があり、そのバランスのとれる範囲は結構広いのですが、がんや慢性の病気をかかえた人は、そのバランスの幅が狭くなってくるから、健康な人以上にバランスに気をつけるべきです」と、加藤さんは忠告する。
同時に、加藤さんは情報を発信する側の責任を指摘する。
「乳製品や肉を食べることが健康に良いと信じて食べ続け、それで健康を害するのでは、あまりにもかわいそうです。情報は正しく伝えなくてはなりません」

30品目弁当は体に良いと言われてはいたけれど…
そういう意味で、加藤さんが国の誤りを指摘するのは、「1日30品目」の情報についてである。1985年、当時の厚生労働省は、現代人の食生活はビタミン、ミネラル、鉄、カルシウムなどが足りないとして、「欠乏の栄養食」の観点から、「1日30品目」を提唱した。
ところが、その後、「1日30品目」を実践すると、炭水化物はやや不足するが、脂肪過剰、タンパク質過剰で、肥満につながることがわかった。そこで厚労省は2000年に、「1日30品目」の看板を下ろし、「多様な食品を組み合わせましょう」と言うようになった。
現在では、「食事バランスガイド」で、「主食・副菜が大事。乳製品はほどほどに」などと、ウィレット教授の受け売りを行っている。
しかし、「1日30品目」の看板をなぜ下ろすのか、その明確な理由を明かさないまま、こっそり下ろしたために、コンビニエンス店では今も「30品目サラダ」「50品目弁当」といった商品がまかり通っている。健康に関わる情報は、修正するときにも、周知徹底に万全を期してもらいたいものだ。
いずれにしても、人間の健康によい本来の食生活のあり方は、国際的にコンセンサスを得た形で示されている。
加藤さんは、「がんを防ぐためにも、がん再発を抑止するためにも、人間本来の食生活を守ることが大切だと思います」と締めくくった。
同じカテゴリーの最新記事
- 高血糖や肥満は放っておかない インスリン増加とがん化促進の関係がわかってきた
- 腸内細菌、歯周病菌が大腸がんの進行にも関与⁉︎ 大腸がん再発予防は善玉菌を減らさない食事とリズム感ある生活で
- 高齢進行がん患者の悪液質を集学的治療で予防・改善 日本初の臨床試験「NEXTAC-ONE」で安全性と忍容性認められる
- 第3回(最終回)/全3回 夫が命をかけて私に残してくれたもの
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 第2回/全3回 〝噛めなくてもおいしく食べられるごはん〟 アイデアが次々に沸いてきた!
- 第1回/全3回 ある日突然、夫が普通のごはんを食べられなくなった――
- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 栄養補助食品を利用して食べる意欲へつなげる


